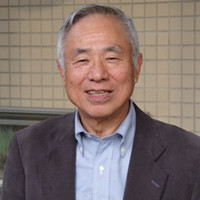石飛幸三医師の
特養で死ぬこと・看取ること
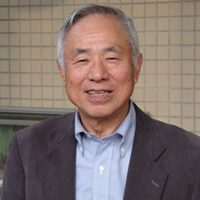
終末期の胃ろうなどの行きすぎた延命治療の是非について問題提起し、ベストセラーとなった『「平穏死」のすすめ』の著者が、特養での“看取り”を語り尽くします。
穏やかな最期を迎えるためにどうすればよいか? 職員と家族の関係はどうあるべきか? これからの特養の使命とは? 施設で働く介護、看護職に贈る「看取り」の医師からの熱いエール!
- プロフィール石飛 幸三(いしとび こうぞう)
-
特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医。
1935年広島県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業。1970年ドイツのフェルディナント・ザウアーブルッフ記念病院で血管外科医として勤務。帰国後、1972年東京都済生会中央病院勤務、1993年東京都済生会中央病院副院長を経て、2005年より現職。診療の傍ら、講演や執筆などを通して、老衰末期の看取りのあり方についての啓発に尽力している。
主な著書に『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか』(講談社)、『「平穏死」という選択』(幻冬舎ルネッサンス新書)などがある。
第11回 看取りに携わる職員の思い
介護施設で看取りを行っていく上での、阻害要因(配置医の問題と家族の思い)について述べてきましたが、看取りに携わる施設の職員の力量や思いといった部分も当然ながら重要です。
看取りの施設として芦花ホームは全国的にも有名になりましたが、最初は、職員にも戸惑いがありました。とりわけ、坂を下っている人たちに、これ以上頑張らせてどうするんだとか、無理に食べさせて誤嚥性肺炎にしてどうするんだ、といったようなことに対しては、“頑張らせて、食べさせて元気にしたい”という思いを持ってる職員から、戸惑いや反論の声が出ました。
私は自分の考えを押しつけるつもりはなく、みんなで一緒に考えよう、というスタンスで勉強会を開いて、みんなで学んで、その上で、最後まで頑張らせるのではなく、最後までどう支えてあげるかをしっかり考えるようになっていったと思います。
介護士の言葉
新米の若い介護士(女性)が書いてくれた言葉を紹介します。初めは、人の死を見たことがなくて、看取りが恐ろしいって泣いていた彼女が、ここで看取りを体験して、初めて書いてくれたのが、この言葉です。
「大切なのは死の瞬間だけではない。看取りは入所の時から始まっている。入所者がどうこれまで生きてきたのか、家族とここへきてどうかかわってきたか、それが最後に結実する」
これは、特養だけではなくて介護施設の役割の本質をついていると思います。本人と家族の人生の最終章をどう支えて、どう最後を迎えてもらうか。これは、介護施設のこれからの使命だと思いますよ。
元気にして家に帰すなんて建前は捨てて、施設に入るまで家族介護で大変だっただろうなぁと本人や家族の苦労に思いをはせ、その苦労を少しでも取り除いてあげよう、本人には最後まで穏やかに生活してもらって、平穏な看取りを迎えられるようにしてあげよう…。
前述の言葉を書いてくれた介護士はもちろん、芦花ホームの職員には、こうした思いが浸透しているように感じます。
本人の思い…
本人の思いと簡単に言っても、例えば、認知症の方であれば、なかなかその思いに応えるのは難しいかもしれません。
80歳に近いHさんは、脳梗塞とアルツハイマーで、胃ろうをつけて7年ほど過ごされていました。アルツハイマーは時間の経過とともに確実に人格の崩壊と能力の低下を伴います。Hさんも例外ではなく、何も理解できず、口を半分開けて、ほとんど植物人間のような状態でした。
ある時、そのHさんが、棚の上を指さしていました。そこには、ビールが大好きだったお父さんのために、と娘さんが置いておいたビールの小瓶が乗っていたのです。その行動をみた職員が、どうやら飲みたいのかも?、というので、それじゃあということで、飲ませてみることにしたのです。介護士、作業療法士等々スタッフが集まって、本人を車いすに座らせて、ビールをHさんの手に持たせました。すると…、グビッ、グビッと本当に美味しそうにビールを飲まれたのです。
これには本当に驚きました。ほとんど何も反応しないHさんが、まさかビールをあんなに美味しそうに飲まれるとは、人間はわからないものです。これを目の当たりにしたご家族も大変に喜ばれましたよ。
意思の疎通が難しい場合、こうしたことは滅多に起こらないかもしれませんが、本人の思いが引き出せる瞬間、その機会を逸しないようにしたいものですね。
これは、マニュアル通りやっていてはダメで、その人その人をどう支えていくか、考えている職員だからこそ、気づけることなのではないかと思っています。
→→→第12回へつづく。