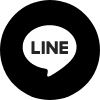社会福祉士・精神保健福祉士 月イチ確認テスト(11月)
2025.11.14
問1
知的障害者福祉法における「知的障害者」とは,児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
答え
正解
知的障害者福祉法において「知的障害者」の定義はなされていない。なお,療育手帳の交付対象者は「児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者」とされている(厚生事務次官通知「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号))。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
知的障害者福祉法において「知的障害者」の定義はなされていない。なお,療育手帳の交付対象者は「児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者」とされている(厚生事務次官通知「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号))。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
知的障害者福祉法において「知的障害者」の定義はなされていない。なお,療育手帳の交付対象者は「児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者」とされている(厚生事務次官通知「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号))。
問2
放課後等デイサービスは,障害児の生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進などを図るためのサービスを提供することをいう。
答え
正解
放課後等デイサービスとは,学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき,放課後又は休日に児童発達支援センターその他の施設に通わせ,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他を行うことをいう。
不正解正しい答えは「 ○ 」
放課後等デイサービスとは,学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき,放課後又は休日に児童発達支援センターその他の施設に通わせ,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他を行うことをいう。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
放課後等デイサービスとは,学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児につき,放課後又は休日に児童発達支援センターその他の施設に通わせ,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他を行うことをいう。
問3
国や地方公共団体は,法定雇用率を上回るよう障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度の対象外である。
答え
正解
国や地方公共団体も障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度の対象である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
国や地方公共団体も障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度の対象である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
国や地方公共団体も障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度の対象である。
問4
「障害者優先調達推進法」により,国は,障害者就労施設,在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。
答え
正解
設問のとおり(障害者優先調達推進法第3条)。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり(障害者優先調達推進法第3条)。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり(障害者優先調達推進法第3条)。
問5
国民健康保険団体連合会は,市町村から委託を受けて介護給付費等の支払業務を行う。
答え
正解
設問のとおり。国民健康保険団体連合会は,市町村から委託を受けて,介護給付費,訓練等給付費,特定障害者特別給付費,地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。国民健康保険団体連合会は,市町村から委託を受けて,介護給付費,訓練等給付費,特定障害者特別給付費,地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。国民健康保険団体連合会は,市町村から委託を受けて,介護給付費,訓練等給付費,特定障害者特別給付費,地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。
問6
保護司の職務は,保護観察事件に限定されない。
答え
正解
設問のとおり。保護司は,犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動,民間団体の活動への協力,地方公共団体の施策への協力などにも従事している。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。保護司は,犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動,民間団体の活動への協力,地方公共団体の施策への協力などにも従事している。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。保護司は,犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動,民間団体の活動への協力,地方公共団体の施策への協力などにも従事している。
問7
保護司は,保護観察官とは異なり,職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
答え
正解
保護司法第9条第2項に「保護司は,その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し,その名誉保持に努めなければならない」とある。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
保護司法第9条第2項に「保護司は,その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し,その名誉保持に努めなければならない」とある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
保護司法第9条第2項に「保護司は,その職務を行うに当って知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重し,その名誉保持に努めなければならない」とある。
問8
高齢又は障害により自立が困難な矯正施設退所者等に対し,退所後直ちに福祉サービスにつなげるなど,地域生活に定着をはかるため,地域生活定着支援センターが設置された。
答え
正解
設問のとおり。事業内容は,①帰住地調整支援(コーディネート業務),②施設定着支援(フォローアップ業務),③地域定着支援(相談支援業務)の3点である。各都道府県に1か所(北海道のみ2か所)設置されている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。事業内容は,①帰住地調整支援(コーディネート業務),②施設定着支援(フォローアップ業務),③地域定着支援(相談支援業務)の3点である。各都道府県に1か所(北海道のみ2か所)設置されている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。事業内容は,①帰住地調整支援(コーディネート業務),②施設定着支援(フォローアップ業務),③地域定着支援(相談支援業務)の3点である。各都道府県に1か所(北海道のみ2か所)設置されている。
問9
精神保健観察は,刑法上の全ての犯罪行為に対して適用される制度である。
答え
正解
医療観察制度における精神保健観察の対象となるのは,重大な他害行為を行い,心神喪失又は心神耗弱であることが認められ,不起訴処分又は無罪等の確定裁判を受けた者で,入院によらない医療を受ける者である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
医療観察制度における精神保健観察の対象となるのは,重大な他害行為を行い,心神喪失又は心神耗弱であることが認められ,不起訴処分又は無罪等の確定裁判を受けた者で,入院によらない医療を受ける者である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
医療観察制度における精神保健観察の対象となるのは,重大な他害行為を行い,心神喪失又は心神耗弱であることが認められ,不起訴処分又は無罪等の確定裁判を受けた者で,入院によらない医療を受ける者である。
問10
地域社会における精神保健観察は,保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。
答え
正解
精神保健観察は社会復帰調整官によって行われ,地域において継続的な医療を確保することを目的として,本人の通院状況や生活状況を見守り,必要な指導その他の措置を講ずるものである(医療観察法第106条第2項)。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
精神保健観察は社会復帰調整官によって行われ,地域において継続的な医療を確保することを目的として,本人の通院状況や生活状況を見守り,必要な指導その他の措置を講ずるものである(医療観察法第106条第2項)。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
精神保健観察は社会復帰調整官によって行われ,地域において継続的な医療を確保することを目的として,本人の通院状況や生活状況を見守り,必要な指導その他の措置を講ずるものである(医療観察法第106条第2項)。
問11
全米ソーシャルワーカー協会の発足時に,それまで分散して活動していたソーシャルワーク関係の諸団体が統合された。
答え
正解
全米ソーシャルワーカー協会は1955年に結成され,既存のソーシャルワーク関係7団体を吸収統合することにより,専門職の統一的組織となった。
不正解正しい答えは「 ○ 」
全米ソーシャルワーカー協会は1955年に結成され,既存のソーシャルワーク関係7団体を吸収統合することにより,専門職の統一的組織となった。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
全米ソーシャルワーカー協会は1955年に結成され,既存のソーシャルワーク関係7団体を吸収統合することにより,専門職の統一的組織となった。
問12
トール(Towle, C.)は,「ケースワークは死んだ」という論文を発表し,社会問題へ目を向けることを提唱した。
答え
正解
「ケースワークは死んだ」という論文を発表したのはパールマン(Perlman,H.)である。トールは,クライエントが人としての共通のニーズをもっているという視点を基盤とし,ケースワークと公的扶助との関係を論じることで,ソーシャルワークの発展に貢献した人物である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
「ケースワークは死んだ」という論文を発表したのはパールマン(Perlman,H.)である。トールは,クライエントが人としての共通のニーズをもっているという視点を基盤とし,ケースワークと公的扶助との関係を論じることで,ソーシャルワークの発展に貢献した人物である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
「ケースワークは死んだ」という論文を発表したのはパールマン(Perlman,H.)である。トールは,クライエントが人としての共通のニーズをもっているという視点を基盤とし,ケースワークと公的扶助との関係を論じることで,ソーシャルワークの発展に貢献した人物である。
問13
ホリス(Hollis, F.)は,「状況の中の人」という視点で,心理社会的アプローチを提唱した。
答え
正解
ホリスはアメリカのソーシャルワーク研究者で,「状況の中の人」あるいは「人と状況との全体性」を焦点化し,常に人を状況との相互作用という枠組みで理解しようとした。
不正解正しい答えは「 ○ 」
ホリスはアメリカのソーシャルワーク研究者で,「状況の中の人」あるいは「人と状況との全体性」を焦点化し,常に人を状況との相互作用という枠組みで理解しようとした。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
ホリスはアメリカのソーシャルワーク研究者で,「状況の中の人」あるいは「人と状況との全体性」を焦点化し,常に人を状況との相互作用という枠組みで理解しようとした。
問14
レヴィ(Levy, C.)は,倫理とは,人間関係とその交互作用に対して価値が適用されたものであるとした。
答え
正解
レヴィは,著書『ソーシャルワーク倫理の指針』において,人間関係と人間交互作用に価値が適用されたものが倫理であると規定し,倫理も選択されたものであるが,人間関係における行動に直接影響を及ぼす点に特色があると述べている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
レヴィは,著書『ソーシャルワーク倫理の指針』において,人間関係と人間交互作用に価値が適用されたものが倫理であると規定し,倫理も選択されたものであるが,人間関係における行動に直接影響を及ぼす点に特色があると述べている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
レヴィは,著書『ソーシャルワーク倫理の指針』において,人間関係と人間交互作用に価値が適用されたものが倫理であると規定し,倫理も選択されたものであるが,人間関係における行動に直接影響を及ぼす点に特色があると述べている。
問15
竹内愛二は,著書『社會事業と方面委員制度』において,ドイツのエルバーフェルト制度を基に方面委員制度を考案した。
答え
正解
竹内愛二は,アメリカのケースワーク理論を日本に導入した研究者で,日本で最初のケースワークの体系的な著書ともいわれる『ケース・ウォークの理論と實際』(1938年(昭和13年))を著した。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
竹内愛二は,アメリカのケースワーク理論を日本に導入した研究者で,日本で最初のケースワークの体系的な著書ともいわれる『ケース・ウォークの理論と實際』(1938年(昭和13年))を著した。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
竹内愛二は,アメリカのケースワーク理論を日本に導入した研究者で,日本で最初のケースワークの体系的な著書ともいわれる『ケース・ウォークの理論と實際』(1938年(昭和13年))を著した。
問16
グループワークは,個々のメンバーの社会的に機能する力を高めるために行う。
答え
正解
グループワークは,グループメンバーや地域社会の成長を促し,グループの特徴を活かして問題解決を図り,個人の社会的に機能する力を高めるために実施する。
不正解正しい答えは「 ○ 」
グループワークは,グループメンバーや地域社会の成長を促し,グループの特徴を活かして問題解決を図り,個人の社会的に機能する力を高めるために実施する。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
グループワークは,グループメンバーや地域社会の成長を促し,グループの特徴を活かして問題解決を図り,個人の社会的に機能する力を高めるために実施する。
問17
グループワークにおけるプログラム活動の実施は,手段ではなく目的である。
答え
正解
プログラム活動の実施は,目的ではなく手段である。プログラム活動は,グループ目標を達成するための手段としてメンバー同士の結束力を強化し,グループ内の相互作用を深める。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
プログラム活動の実施は,目的ではなく手段である。プログラム活動は,グループ目標を達成するための手段としてメンバー同士の結束力を強化し,グループ内の相互作用を深める。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
プログラム活動の実施は,目的ではなく手段である。プログラム活動は,グループ目標を達成するための手段としてメンバー同士の結束力を強化し,グループ内の相互作用を深める。
問18
グループワークにおいて,終結期には,メンバー間の感情の表出や分かち合いを避ける。
答え
正解
終結期には,メンバーは,グループの解散や,ほかのメンバーとの離別から,寂しさや喪失感を覚える。ソーシャルワーカーは,メンバーの抱える複雑な気持ちを受容し,分かち合えるように援助することが重要である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
終結期には,メンバーは,グループの解散や,ほかのメンバーとの離別から,寂しさや喪失感を覚える。ソーシャルワーカーは,メンバーの抱える複雑な気持ちを受容し,分かち合えるように援助することが重要である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
終結期には,メンバーは,グループの解散や,ほかのメンバーとの離別から,寂しさや喪失感を覚える。ソーシャルワーカーは,メンバーの抱える複雑な気持ちを受容し,分かち合えるように援助することが重要である。
問19
スーパーバイジーとは,スーパーバイズされる立場の人のことである。
答え
正解
設問のとおり。一方,スーパーバイズする立場の人をスーパーバイザーという。スーパーバイザーはクライエントに直接サービスを提供するわけではないが,サービスを提供するスーパーバイジーにはたらきかけることでサービスの質に間接的に影響を及ぼす。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。一方,スーパーバイズする立場の人をスーパーバイザーという。スーパーバイザーはクライエントに直接サービスを提供するわけではないが,サービスを提供するスーパーバイジーにはたらきかけることでサービスの質に間接的に影響を及ぼす。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおり。一方,スーパーバイズする立場の人をスーパーバイザーという。スーパーバイザーはクライエントに直接サービスを提供するわけではないが,サービスを提供するスーパーバイジーにはたらきかけることでサービスの質に間接的に影響を及ぼす。
問20
複数のスーパーバイジーがスーパーバイザーの同席なしに行うスーパービジョンの形態は,ピア・スーパービジョンである。
答え
正解
ピア・スーパービジョンとは,仲間や同僚だけで行うスーパービジョンのことである。本来,スーパービジョンはスーパーバイザーが行うものであるが,スーパーバイザーが不在のときに代替方法として行う変則的な形態である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
ピア・スーパービジョンとは,仲間や同僚だけで行うスーパービジョンのことである。本来,スーパービジョンはスーパーバイザーが行うものであるが,スーパーバイザーが不在のときに代替方法として行う変則的な形態である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
ピア・スーパービジョンとは,仲間や同僚だけで行うスーパービジョンのことである。本来,スーパービジョンはスーパーバイザーが行うものであるが,スーパーバイザーが不在のときに代替方法として行う変則的な形態である。