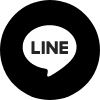ケアマネ 月イチ確認テスト(10月)
2025.10.09
問1
マクロ・ソーシャルワーク(地域援助)として:地域の聴覚言語障害者に対して適切に情報提供が行われるよう、要約筆記者、手話通訳者の配置などを自治体に働きかける。
答え
正解
よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集、広報、啓発活動を展開するうえで、適切に情報提供が行われるように専門家の配置などがなされるようにすることも重要である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集、広報、啓発活動を展開するうえで、適切に情報提供が行われるように専門家の配置などがなされるようにすることも重要である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
よりよい福祉サービスの制度化に向けての情報収集、広報、啓発活動を展開するうえで、適切に情報提供が行われるように専門家の配置などがなされるようにすることも重要である。
問2
ソーシャルワークの観点から、クライエントの自立支援を行う上で:クライエントの意欲を高めるためには、日常の小さな事柄から始める自己決定の体験が効果的である。
答え
正解
クライエント本人の意欲を高めるために最も効果的なのは、小さな事柄から始める自己決定の体験である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
クライエント本人の意欲を高めるために最も効果的なのは、小さな事柄から始める自己決定の体験である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
クライエント本人の意欲を高めるために最も効果的なのは、小さな事柄から始める自己決定の体験である。
問3
ソーシャルワークの観点から、クライエントの自立支援を行う上で:クライエントの可能性を広げ、意欲を高めていくことが大切である。
答え
正解
社会的接触の幅を広げるなど、クライエントの可能性を広げ、自立への意欲を引き出すことが大切である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
社会的接触の幅を広げるなど、クライエントの可能性を広げ、自立への意欲を引き出すことが大切である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
社会的接触の幅を広げるなど、クライエントの可能性を広げ、自立への意欲を引き出すことが大切である。
問4
相談援助者の職業倫理について:事例検討の内容があまりにもつらいものであったため、自宅でその具体的な内容を家族に話した。
答え
正解
面接場面で語られたことにとどまらず、関連する公式資料から得られる情報はもちろん、ほかの専門職から会議などの場で得られた情報、家庭訪問のなかで観察した事柄、本人の表情、家族の様子などについても、本人の承諾なしに他人に漏らすことがないよう堅く守る必要がある。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
面接場面で語られたことにとどまらず、関連する公式資料から得られる情報はもちろん、ほかの専門職から会議などの場で得られた情報、家庭訪問のなかで観察した事柄、本人の表情、家族の様子などについても、本人の承諾なしに他人に漏らすことがないよう堅く守る必要がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
面接場面で語られたことにとどまらず、関連する公式資料から得られる情報はもちろん、ほかの専門職から会議などの場で得られた情報、家庭訪問のなかで観察した事柄、本人の表情、家族の様子などについても、本人の承諾なしに他人に漏らすことがないよう堅く守る必要がある。
問5
相談援助者の職業倫理について:相談援助者が守るべき秘密の内容は、クライエントが面接場面で語ったことだけであり、関連資料から得られるものは含まれない。
答え
正解
相談援助者が守るべき秘密の内容は、面接場面で語られたことにとどまらず、関連公式資料から得られる情報はもちろん、ほかの援助専門職から会議などの場で得られた情報、家庭訪問のなかで観察した事柄、本人の表情、家族の様子なども含まれる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
相談援助者が守るべき秘密の内容は、面接場面で語られたことにとどまらず、関連公式資料から得られる情報はもちろん、ほかの援助専門職から会議などの場で得られた情報、家庭訪問のなかで観察した事柄、本人の表情、家族の様子なども含まれる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
相談援助者が守るべき秘密の内容は、面接場面で語られたことにとどまらず、関連公式資料から得られる情報はもちろん、ほかの援助専門職から会議などの場で得られた情報、家庭訪問のなかで観察した事柄、本人の表情、家族の様子なども含まれる。
問6
ソーシャルワークに関して:同居家族がいるクライエントからの訪問介護サービスの利用希望に対しては、まず家族による支援を受けるよう指導する。
答え
正解
クライエントや家族、関係者の意見や行動を相談援助者の価値観や社会通念から一方的に評価して、相談を相談援助者の側から打ち切ってしまうことがないようにすることが求められる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
クライエントや家族、関係者の意見や行動を相談援助者の価値観や社会通念から一方的に評価して、相談を相談援助者の側から打ち切ってしまうことがないようにすることが求められる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
クライエントや家族、関係者の意見や行動を相談援助者の価値観や社会通念から一方的に評価して、相談を相談援助者の側から打ち切ってしまうことがないようにすることが求められる。
問7
相談援助者の職業倫理について:個人情報の扱いについてクライエントに説明し、了解を得た上で、訪問介護事業者にクライエントの家族歴、生活歴に関する情報を提供した。
答え
正解
家族との連絡方法、緊急時の連絡方法、援助専門職間の連携にあたっての情報管理など、どの種類の個人情報をどの範囲の人々の間で共有するかについて、クライエント本人の了解をとっておくことが求められる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
家族との連絡方法、緊急時の連絡方法、援助専門職間の連携にあたっての情報管理など、どの種類の個人情報をどの範囲の人々の間で共有するかについて、クライエント本人の了解をとっておくことが求められる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
家族との連絡方法、緊急時の連絡方法、援助専門職間の連携にあたっての情報管理など、どの種類の個人情報をどの範囲の人々の間で共有するかについて、クライエント本人の了解をとっておくことが求められる。
問8
面接場面におけるコミュニケーションの技術について:部屋の雰囲気やいすの位置、相談援助者の服装などの外的条件は、円滑なコミュニケーションのためには重要ではない。
答え
正解
面接の場所の設定、部屋の雰囲気、いすの位置、相談援助者の服装、書類の形式、あらかじめ記入を求めるものがあればそれについての説明などの外的条件も、円滑なコミュニケーションを可能にするよう配慮されなければならない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
面接の場所の設定、部屋の雰囲気、いすの位置、相談援助者の服装、書類の形式、あらかじめ記入を求めるものがあればそれについての説明などの外的条件も、円滑なコミュニケーションを可能にするよう配慮されなければならない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
面接の場所の設定、部屋の雰囲気、いすの位置、相談援助者の服装、書類の形式、あらかじめ記入を求めるものがあればそれについての説明などの外的条件も、円滑なコミュニケーションを可能にするよう配慮されなければならない。
問9
面接場面におけるコミュニケーションについて:波長合わせとは、相談援助者が、自らの態度、言葉遣い、質問の形式等をクライエントの反応に合わせて修正していくことである。
答え
正解
波長合わせとは、傾聴の過程で相談援助者が、自身の予測と違ったクライエントの反応に対し、自らの態度、言葉遣い、時には話題や質問の形式等を軌道修正していく過程を意味する。クライエントの側がしだいに自分の思い込みや誤解を解いて姿勢を変更する過程と、それを相談援助者が受け止める過程も含まれる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
波長合わせとは、傾聴の過程で相談援助者が、自身の予測と違ったクライエントの反応に対し、自らの態度、言葉遣い、時には話題や質問の形式等を軌道修正していく過程を意味する。クライエントの側がしだいに自分の思い込みや誤解を解いて姿勢を変更する過程と、それを相談援助者が受け止める過程も含まれる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
波長合わせとは、傾聴の過程で相談援助者が、自身の予測と違ったクライエントの反応に対し、自らの態度、言葉遣い、時には話題や質問の形式等を軌道修正していく過程を意味する。クライエントの側がしだいに自分の思い込みや誤解を解いて姿勢を変更する過程と、それを相談援助者が受け止める過程も含まれる。
問10
インテーク面接について:情報収集のため、アセスメント項目の順番に従って、すべて質問する。
答え
正解
インテーク面接における情報提供は受容的・非審判的態度で傾聴することが大切であり、双方向的なものでなければならず、何の事前聴取もなしにアセスメント項目等の順番に沿ってすべて質問することは望ましくない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
インテーク面接における情報提供は受容的・非審判的態度で傾聴することが大切であり、双方向的なものでなければならず、何の事前聴取もなしにアセスメント項目等の順番に沿ってすべて質問することは望ましくない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
インテーク面接における情報提供は受容的・非審判的態度で傾聴することが大切であり、双方向的なものでなければならず、何の事前聴取もなしにアセスメント項目等の順番に沿ってすべて質問することは望ましくない。
問11
支援困難事例への基本的アプローチとして:本人の人生、人生観、生き方、価値観等について、理解をより深めることが重要である。
答え
正解
本人のこれまでの人生、人生観、生き方、生きざま、価値観、今の生活世界、感情等に近づき、本人がどのような世界に生き、何を感じながら生活しているのかについて本人の内側の世界から理解を深めることが重要である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
本人のこれまでの人生、人生観、生き方、生きざま、価値観、今の生活世界、感情等に近づき、本人がどのような世界に生き、何を感じながら生活しているのかについて本人の内側の世界から理解を深めることが重要である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
本人のこれまでの人生、人生観、生き方、生きざま、価値観、今の生活世界、感情等に近づき、本人がどのような世界に生き、何を感じながら生活しているのかについて本人の内側の世界から理解を深めることが重要である。
問12
支援困難事例への基本的アプローチとして:自尊心が傷つき、敗北感を抱えた人に対しても、本人が現実と向きあい、自分の環境に働きかけられるよう、支えていく必要がある。
答え
正解
自信を失い、自尊心が傷つき、自己評価が低下した人や、劣等感や敗北感、無力感などを抱えた人に対して、それでも存在することに意味と価値があることを本人自身が認識できるように働きかけなければならない。
不正解正しい答えは「 ○ 」
自信を失い、自尊心が傷つき、自己評価が低下した人や、劣等感や敗北感、無力感などを抱えた人に対して、それでも存在することに意味と価値があることを本人自身が認識できるように働きかけなければならない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
自信を失い、自尊心が傷つき、自己評価が低下した人や、劣等感や敗北感、無力感などを抱えた人に対して、それでも存在することに意味と価値があることを本人自身が認識できるように働きかけなければならない。
問13
介護支援専門員が活用する社会資源について:社会資源の活用に際しては、要介護者本人及び家族との協働が求められている。
答え
正解
介護支援専門員は、要介護者本人や家族の主体性を尊重し、協働により社会資源の活用を図っていく。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護支援専門員は、要介護者本人や家族の主体性を尊重し、協働により社会資源の活用を図っていく。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
介護支援専門員は、要介護者本人や家族の主体性を尊重し、協働により社会資源の活用を図っていく。
問14
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について:平成24年の改正によって、「障害程度区分」は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められた。
答え
正解
障害支援区分は、区分1から6の6段階からなり数字が大きいほど必要とされる支援の度合が高い状態となる。障害支援区分の定義は、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとされている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
障害支援区分は、区分1から6の6段階からなり数字が大きいほど必要とされる支援の度合が高い状態となる。障害支援区分の定義は、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
障害支援区分は、区分1から6の6段階からなり数字が大きいほど必要とされる支援の度合が高い状態となる。障害支援区分の定義は、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとされている。
問15
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び介護保険法について:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、原則として、介護保険の被保険者となる。
答え
正解
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、原則として介護保険の被保険者となる。ただし、障害者支援施設等に入所している者については、介護保険の被保険者にならないこととされている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、原則として介護保険の被保険者となる。ただし、障害者支援施設等に入所している者については、介護保険の被保険者にならないこととされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している障害者は、原則として介護保険の被保険者となる。ただし、障害者支援施設等に入所している者については、介護保険の被保険者にならないこととされている。
問16
生活保護制度について:住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等にともなう住宅を維持するための補修費用は含まれない。
答え
正解
住宅扶助は、「住居の確保」及び「補修その他住宅の維持のために必要なもの」が対象となる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
住宅扶助は、「住居の確保」及び「補修その他住宅の維持のために必要なもの」が対象となる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
住宅扶助は、「住居の確保」及び「補修その他住宅の維持のために必要なもの」が対象となる。
問17
生活保護制度について:介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として、介護扶助から支給される。
答え
正解
生活保護受給者が介護保険施設に入所している場合、日常生活に必要な費用については生活扶助により、介護施設入所者基本生活費を支給する。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
生活保護受給者が介護保険施設に入所している場合、日常生活に必要な費用については生活扶助により、介護施設入所者基本生活費を支給する。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
生活保護受給者が介護保険施設に入所している場合、日常生活に必要な費用については生活扶助により、介護施設入所者基本生活費を支給する。
問18
生活保護制度について:医療扶助による医療の給付は、入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。
答え
正解
医療扶助による医療の給付は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われ、現物給付を原則としている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
医療扶助による医療の給付は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われ、現物給付を原則としている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
医療扶助による医療の給付は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われ、現物給付を原則としている。
問19
生活保護制度について:介護保険の介護保険料は、生活扶助として給付される。
答え
正解
介護保険の介護保険料は、生活扶助の介護保険料加算によって給付される。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護保険の介護保険料は、生活扶助の介護保険料加算によって給付される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
介護保険の介護保険料は、生活扶助の介護保険料加算によって給付される。
問20
生活保護制度について:介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。
答え
正解
介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。また介護扶助の対象となる居宅介護は、居宅介護支援計画に基づいて行われるものに限られる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。また介護扶助の対象となる居宅介護は、居宅介護支援計画に基づいて行われるものに限られる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。また介護扶助の対象となる居宅介護は、居宅介護支援計画に基づいて行われるものに限られる。