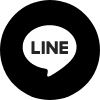精神保健福祉士 月イチ確認テスト(1月)
2026.01.15
問1
クライエントが希望する支援を受けられるように別の機関へつなぐことを、リファーラルという。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問2
ストレングスモデルの提唱者は、トーマス,E.である。
答え
正解
ストレングスモデルの提唱者は、ラップ,C.A.である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
ストレングスモデルの提唱者は、ラップ,C.A.である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
ストレングスモデルの提唱者は、ラップ,C.A.である。
問3
家族の感情表出が低いほど、統合失調症の再発率が上がるとされている。
答え
正解
家族の感情表出が高いほど、統合失調症の再発率が上がるとされている。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
家族の感情表出が高いほど、統合失調症の再発率が上がるとされている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
家族の感情表出が高いほど、統合失調症の再発率が上がるとされている。
問4
精神保健福祉士は、多職種協働におけるコーディネーターとしての役割を担っている。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問5
すべての人々を社会の構成員として包み支えあうことを、ソーシャルエクスクルージョンという。
答え
正解
すべての人々を社会の構成員として包み支えあうことを、ソーシャルインクルージョンという。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
すべての人々を社会の構成員として包み支えあうことを、ソーシャルインクルージョンという。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
すべての人々を社会の構成員として包み支えあうことを、ソーシャルインクルージョンという。
問6
社会資源の開発や法制度の改善を自治体へ要望することは、協議会の機能に含まれる。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問7
スケーリングクエスチョンやミラクルクエスチョンは、認知行動療法的アプローチで用いる面接法である。
答え
正解
スケーリングクエスチョンやミラクルクエスチョンは、解決志向アプローチで用いる質問である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
スケーリングクエスチョンやミラクルクエスチョンは、解決志向アプローチで用いる質問である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
スケーリングクエスチョンやミラクルクエスチョンは、解決志向アプローチで用いる質問である。
問8
SWOT分析とは、環境を「強み、弱み、機会、脅威」のマトリックスでクロス分析するものである。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問9
支援が終結した際に、実施したソーシャルワークの過程全体を事後評価することを、ターミネーションという。
答え
正解
支援が終結した際に、実施したソーシャルワークの過程全体を事後評価することを、エバリュエーションという。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
支援が終結した際に、実施したソーシャルワークの過程全体を事後評価することを、エバリュエーションという。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
支援が終結した際に、実施したソーシャルワークの過程全体を事後評価することを、エバリュエーションという。
問10
タックマン,B.W.は、チームビルディングの形成過程を五つの段階に分けた。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問11
リハビリテーションの目標はリカバリーであり、機能障害以外は回復できるという視点が重要である。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問12
認知行動療法では、認知のゆがみに気づき、自身のスキーマを修正することを目指す。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問13
障害者雇用促進法における精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳を交付されている者に限定されている。
答え
正解
障害者雇用促進法における精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳を交付されている者に限定されない。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
障害者雇用促進法における精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳を交付されている者に限定されない。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
障害者雇用促進法における精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳を交付されている者に限定されない。
問14
DARC(ダルク)は、アルコール依存症の回復支援施設であり、居住型と通所型がある。
答え
正解
DARC(ダルク)は、薬物依存症の回復支援施設であり、居住型と通所型がある。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
DARC(ダルク)は、薬物依存症の回復支援施設であり、居住型と通所型がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
DARC(ダルク)は、薬物依存症の回復支援施設であり、居住型と通所型がある。
問15
従業員101人以上の障害者雇用率未達成企業は、障害者雇用納付金を納めなければならない。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問16
措置入院の対象は、自傷他害のおそれがある精神障害者である。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問17
就業面と生活面の両方を支援するために、障害者雇用促進法に基づいて設置されている機関を、障害者就業・生活支援センターという。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問18
厚生年金保険加入者で、障害厚生年金3級の障害よりやや軽い障害が残ったときには、特別障害者手当が支給される。
答え
正解
厚生年金保険加入者で、障害厚生年金3級の障害よりやや軽い障害が残ったときには、障害手当金が支給される。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
厚生年金保険加入者で、障害厚生年金3級の障害よりやや軽い障害が残ったときには、障害手当金が支給される。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
厚生年金保険加入者で、障害厚生年金3級の障害よりやや軽い障害が残ったときには、障害手当金が支給される。
問19
72時間以内の入院であれば、1名の精神保健指定医の診察により緊急措置入院の手続きをとることができる。
答え
正解
設問のとおりである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
設問のとおりである。
問20
医療観察法に基づく鑑定入院の後に、保護観察所の社会復帰調整官による生活環境調査が行われる。
答え
正解
医療観察法に基づく鑑定入院と同時に、保護観察所の社会復帰調整官による生活環境調査が行われる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
医療観察法に基づく鑑定入院と同時に、保護観察所の社会復帰調整官による生活環境調査が行われる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
医療観察法に基づく鑑定入院と同時に、保護観察所の社会復帰調整官による生活環境調査が行われる。