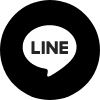保育士 月イチ確認テスト(1月)
2026.01.15
問1
子どもへの虐待による死亡は、1歳未満が約半数を占める。
答え
正解
「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」では、0歳児の占める割合は6割強と報告されている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」では、0歳児の占める割合は6割強と報告されている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」では、0歳児の占める割合は6割強と報告されている。
問2
社会的に孤立し援助者が少ない場合、虐待は起こりやすい。
答え
正解
妊娠期から保健師等の専門職がきめ細かな対応や医療機関と連携し、地域のネットワークを活用して支援を行うことが重要である。
不正解正しい答えは「 ○ 」
妊娠期から保健師等の専門職がきめ細かな対応や医療機関と連携し、地域のネットワークを活用して支援を行うことが重要である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
妊娠期から保健師等の専門職がきめ細かな対応や医療機関と連携し、地域のネットワークを活用して支援を行うことが重要である。
問3
妊婦健診や乳幼児健診を受診していない場合、子どもを虐待していることが多い。
答え
正解
乳幼児健診の未受診の子どもたちをどのようにフォローするか、自治体の大きな課題となっている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
乳幼児健診の未受診の子どもたちをどのようにフォローするか、自治体の大きな課題となっている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
乳幼児健診の未受診の子どもたちをどのようにフォローするか、自治体の大きな課題となっている。
問4
保育所保育指針第1章「総則」の2「養護に関する基本的事項」のア「生命の保持」では、子どもの生命を守り、子どもが快適に、そして健康で安全に過ごすことができるようにするとされている。
答え
正解
(ア)「ねらい」の①及び②に当てはまる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
(ア)「ねらい」の①及び②に当てはまる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
(ア)「ねらい」の①及び②に当てはまる。
問5
保育所保育指針第1章「総則」の2「養護に関する基本的事項」のア「生命の保持」では、子どもの生理的欲求が十分に満たされ、健康増進が積極的に図られるようにするとされている。
答え
正解
(ア)「ねらい」の③及び④に当てはまる。
不正解正しい答えは「 ○ 」
(ア)「ねらい」の③及び④に当てはまる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
(ア)「ねらい」の③及び④に当てはまる。
問6
愛着の個人差を測定するために、エインズワース(Ainsworth, M. D. S.)が考案したのがサークル・オブ・セキュリティ(安全感の環)であった。
答え
正解
エインズワースが考案したのは、ストレンジ・シチュエーション法(新奇場面法)である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
エインズワースが考案したのは、ストレンジ・シチュエーション法(新奇場面法)である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
エインズワースが考案したのは、ストレンジ・シチュエーション法(新奇場面法)である。
問7
エインズワースによれば、養育者への子どものアタッチメント(愛着)は3つの型に分類される。A型は抵抗(アンビバレント)型、B型は安定型、C型は回避型であった。
答え
正解
A型は回避型、B型は安定型、C型は抵抗(アンビバレント)型。このほかに、D型の無秩序(無方向)型がある。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
A型は回避型、B型は安定型、C型は抵抗(アンビバレント)型。このほかに、D型の無秩序(無方向)型がある。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
A型は回避型、B型は安定型、C型は抵抗(アンビバレント)型。このほかに、D型の無秩序(無方向)型がある。
問8
乳幼児と養育者の関係性は、乳幼児の社会・情緒的発達に影響を与える。
答え
正解
乳幼児と養育者のかかわりは、発達に大きな影響を与える。
不正解正しい答えは「 ○ 」
乳幼児と養育者のかかわりは、発達に大きな影響を与える。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
乳幼児と養育者のかかわりは、発達に大きな影響を与える。
問9
養育者のもつ子どもについての認知、イメージ、表象は、子どもの親に対する行動のパターンには、ほとんど影響を与えない。
答え
正解
養育者のもつ子どもについての認知等は、子どもの親への行動パターンに影響を与える。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
養育者のもつ子どもについての認知等は、子どもの親への行動パターンに影響を与える。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
養育者のもつ子どもについての認知等は、子どもの親への行動パターンに影響を与える。
問10
保育士と乳幼児との関係性は、小学校、中学校での社会・情緒的発達に影響を与えない。
答え
正解
乳幼児期にかかわりのあった保育士との関係は、その後の人間関係にも影響を与えうる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
乳幼児期にかかわりのあった保育士との関係は、その後の人間関係にも影響を与えうる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
乳幼児期にかかわりのあった保育士との関係は、その後の人間関係にも影響を与えうる。
問11
内発的動機づけを構成する要素で、自分の知らないことに興味をもったり、興味をもったものを深く探究したりしようとすることを「知的好奇心」という。
答え
正解
内発的動機づけは、知的好奇心が原動力となる。動機づけは「やる気」、あるいは「モチベーション」のことである。
不正解正しい答えは「 ○ 」
内発的動機づけは、知的好奇心が原動力となる。動機づけは「やる気」、あるいは「モチベーション」のことである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
内発的動機づけは、知的好奇心が原動力となる。動機づけは「やる気」、あるいは「モチベーション」のことである。
問12
ある行動をすると、特定の環境変化が引き続いて生じることに気づいて、その行動を繰り返し行うようになることを「スクリプト」という。
答え
正解
ある行動の結果が、次の行動へつながるのは、オペラント学習という。例えば挨拶をしてほめられたことを経験し、自分から進んで挨拶をするようになるといったことである。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
ある行動の結果が、次の行動へつながるのは、オペラント学習という。例えば挨拶をしてほめられたことを経験し、自分から進んで挨拶をするようになるといったことである。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
ある行動の結果が、次の行動へつながるのは、オペラント学習という。例えば挨拶をしてほめられたことを経験し、自分から進んで挨拶をするようになるといったことである。
問13
育児不安とは、親が育児に自信をなくし、育児の相談相手がいない孤立感や、何となくイライラするなど、育児へのネガティブな感情や育児困難な状態であることをいう。育児ノイローゼや育児ストレスという表現も用いられる。
答え
正解
育児に対する負担感や不安感については、「育児不安」「育児ストレス」といった用語で概念化されている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
育児に対する負担感や不安感については、「育児不安」「育児ストレス」といった用語で概念化されている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
育児に対する負担感や不安感については、「育児不安」「育児ストレス」といった用語で概念化されている。
問14
産後うつ病は、いわゆるマタニティブルーズと呼ばれるものであり、出産後急激に女性ホルモンが減少することによって情緒不安定になり、訳もなく涙が出る、不安感や抑うつ感などの精神症状、また不眠などを示す一過性の症状である。
答え
正解
産後うつ病とマタニティブルーズは別のものである。マタニティブルーズは2週間程度で改善するといわれているが、産後うつ病はうつ病の1つであるため、長期化する場合は医療機関において治療が必要となる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
産後うつ病とマタニティブルーズは別のものである。マタニティブルーズは2週間程度で改善するといわれているが、産後うつ病はうつ病の1つであるため、長期化する場合は医療機関において治療が必要となる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
産後うつ病とマタニティブルーズは別のものである。マタニティブルーズは2週間程度で改善するといわれているが、産後うつ病はうつ病の1つであるため、長期化する場合は医療機関において治療が必要となる。
問15
養護性(ナーチュランス)とは、「小さくて弱いものを見ると慈しみ育もうという気持ち」になる心の働きをいう。養護性は性別に限らず誰もが持っている特性である。
答え
正解
最近では「父性」「母性」という表現から、性別問わず持っている「養護性」という呼び方に置き換えられるようになってきている。
不正解正しい答えは「 ○ 」
最近では「父性」「母性」という表現から、性別問わず持っている「養護性」という呼び方に置き換えられるようになってきている。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
最近では「父性」「母性」という表現から、性別問わず持っている「養護性」という呼び方に置き換えられるようになってきている。
問16
乳幼児における言語の発達について、1歳頃になると、初めて意味のある言葉を発するようになるが、これをジャーゴンという。
答え
正解
設問は、初語の説明である。ジャーゴン(ジャルゴン)とは、言葉以前にあらわれる、母国語にリズムやイントネーションがそっくりの発声のことをいう。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
設問は、初語の説明である。ジャーゴン(ジャルゴン)とは、言葉以前にあらわれる、母国語にリズムやイントネーションがそっくりの発声のことをいう。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
設問は、初語の説明である。ジャーゴン(ジャルゴン)とは、言葉以前にあらわれる、母国語にリズムやイントネーションがそっくりの発声のことをいう。
問17
乳幼児における言語の発達について、1歳半頃には、ものの名前を尋ねるようになるが、これを第二質問期という。
答え
正解
設問は、第一質問期(命名期)の説明である。第二質問期は幼児期後期にみられ、「どうして?」「なんで?」など、物事のしくみや因果を尋ねるようになる。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
設問は、第一質問期(命名期)の説明である。第二質問期は幼児期後期にみられ、「どうして?」「なんで?」など、物事のしくみや因果を尋ねるようになる。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
設問は、第一質問期(命名期)の説明である。第二質問期は幼児期後期にみられ、「どうして?」「なんで?」など、物事のしくみや因果を尋ねるようになる。
問18
ヴィゴツキー(Vygotsky, L. S.)は、子どもは環境の中に埋め込まれている情報を見出しながら行動を起こしており、環境は子どもが関わるものにとどまらず、環境が子どもに働きかけていると指摘した。
答え
正解
環境が子どもに働きかけているという考え方は、ギブソン(Gibson, J. J.)のアフォーダンス理論である。
不正解正しい答えは「 ✕ 」
環境が子どもに働きかけているという考え方は、ギブソン(Gibson, J. J.)のアフォーダンス理論である。
回答が未選択です。正しい答えは「 ✕ 」
環境が子どもに働きかけているという考え方は、ギブソン(Gibson, J. J.)のアフォーダンス理論である。
問19
ヴィゴツキーは、子どもの発達には、他者の援助がなくても独力で達成できる水準と、他者の援助があれば達成できる水準の2つがあり、他者との関わり合いの中で発達は促されていくと指摘した。
答え
正解
2つの水準の間を発達の最近接領域と呼ぶ。一人ひとりの領域を見きわめ、この領域に適切に働きかけることが大切だと考えた。
不正解正しい答えは「 ○ 」
2つの水準の間を発達の最近接領域と呼ぶ。一人ひとりの領域を見きわめ、この領域に適切に働きかけることが大切だと考えた。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
2つの水準の間を発達の最近接領域と呼ぶ。一人ひとりの領域を見きわめ、この領域に適切に働きかけることが大切だと考えた。
問20
ヴィゴツキーは、子どものひとりごとは、他者に向かうコミュニケーションのための言葉が、自分に向かう思考のための言葉となっていく過程で現れると指摘した。
答え
正解
コミュニケーションの言葉を外言と呼び、思考の言葉を内言と呼ぶ。
不正解正しい答えは「 ○ 」
コミュニケーションの言葉を外言と呼び、思考の言葉を内言と呼ぶ。
回答が未選択です。正しい答えは「 ○ 」
コミュニケーションの言葉を外言と呼び、思考の言葉を内言と呼ぶ。