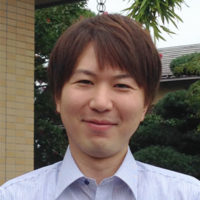介護職に就いた私の理由(わけ)
さまざまな事情で介護の仕事に就いた方々の人生経緯と、介護の仕事で体験したエピソードを紹介していきます。「介護の仕事に就くことで、こんなふうに人生が変わった」といった視点からご紹介することで、さまざまな経験を経た介護職が現場には必要であること、そして、それが大変意味のあることだということを、あらためて考えていただく機会としたいと考えています。
たとえば、「介護の仕事をするしかないか・・」などと消極的な気持ちでいる方がいたとしても、この連載で紹介される「介護の仕事にこそ自分を活かす術があった・・」というさまざまな事例を通して、「介護の仕事をやってみよう!」などと積極的に受け止める人が増えることを願っています。そのような介護の仕事の大変さ、面白さ、社会的意義を多くの方に理解していただけるインタビュー連載に取り組んでいきます。

花げし舎ホームページ:
http://hanagesisha.jimdo.com/
- プロフィール久田恵の主宰する編集プロダクション「花げし舎」チームが、各地で取材を進めていきます。
久田 恵(ひさだ めぐみ) -
北海道室蘭市生まれ。1990年『フイリッピーナを愛した男たち』(文藝春秋)で、第21回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。
著書に『ニッポン貧困最前線-ケースワーカーと呼ばれる人々』(文藝春秋・文庫)、『シクスティーズの日々』(朝日新聞社)など。現在、読売新聞「人生案内」の回答者、現在、産経新聞にてエッセイを連載中。
第84回 看護師から介護施設運営、講座開設へ
どんより介護からハッピー介護へ もっと楽になる考え方を伝えたい

林 炎子 さん(41歳)
にこにこハート株式会社
代表取締役
(埼玉・川越)
取材・文:原口美香
利用者の方に「お母さん」と話しかけるのが仕事
私が小学5年生の頃、両親が自宅を開放して、幼児や障害者、高齢者のケア施設を始めたのです。中学1年生の時には、母親に頼まれて、認知症のおばあさんに「お母さん」と話しかけるのが私の仕事でした。「お母さん」と話しかけると、そのおばあさんの表情がすごく和らいで、介護を受け入れてくれるようになるのです。私のことを娘だと思っているんですね。最初はとても嫌だったのですが、いつの間にか、楽しくなっていました。両親の役に立っていることもうれしかったのですが、私がそう言うことで、そのおばあさんや、周りの利用者の方が笑顔になっていくことがうれしくて。そんな生活が高校を卒業するまで続きました。それが私にとって初めての「介護」で、原点だと思います。
看護よりも介護をしたかった
もともと母が看護師だったので、私も小さな頃から看護師になろうと思っていました。高校を卒業して看護学校に入り、実家を離れました。看護師の仕事は、とてもおもしろかったんです。病気の方が元気になって退院していくのは、いつでも私の喜びでした。だけど看護師というのは、どうしても命を救うべくやらなければいけないことが優先です。それよりも私は、認知症の方の介護や、気持ちに寄り添うようなことをしたいと思うようになっていきました。それで看護師を辞めて実家に戻り、両親の施設を手伝うようになったのです。その後、新しくグループホームを始めようとしていたのですが、坂戸市にはすでにたくさんのグループホームがありました。それでデイサービスを作ることにしたのです。6年前の2011年、35歳の時に「陽気な鶴さん」を始めました。
私は施設しか知らなかったので、最初は戸惑いました。施設は入居してくれた方に対して、いい関係を築いていけば、その方もどんどん心を開いてくれる、いい方向に変わってきてくれるんです。だけど「デイサービス」というのは施設と違って、毎日とは限りませんし、通ってきてくれるのが途切れ途切れだと、ご家族との関係性にも左右されると感じました。ご自宅でもいい関係性ができていないと、認知症の「BPSD」と呼ばれるものが、例えば、徘徊だったり、暴力であったりが、なかなか良くならないんですね。デイサービスに来ているときは良くても、離れちゃうと戻ってしまったり。それでご家族も含めて、認知症の方の頭の中で何が起こっているのか、あまり知られていないんだということに気が付きました。
認知症の方の頭の中で起こっていることを知る
認知症の方と関係性を作るときには、段階があると思うのですが、まずは認知症の方の頭の中を知らないと、いい介護ができないと思うのです。
例えば、ここに「定規」があったとして、「定規」は線を引いたり、物の大きさを測ったりしますよね。でも極端なことをいえば、認知症の方には、この「定規」が「草原」に見えているのです。だから「これは定規だよ」と言っても、「草原に見えるけど、定規なのかな」と思ってしまう。そう思ったときに気持ち悪いし、これが「草原」なのか、「定規」なのか分からない。そんな状態が認知症の方には一日中、起こっているのです。だからいつも答えを探してしまうし、困っているんです。ただの物忘れという単純なものではないんですね。そればかりではなく、物の名前や、やり方も忘れてしまうのです。洋服の着方を忘れる。眠り方を忘れる。セーターやズボンが着るものだということが分からなければ、渡されても着ることができないんです。それをミカンだと思っていれば、食べてしまう。見えているものが違うんですね。そういうことを忘れてできなくなってしまうから、それを知らないと、ご家族は怒ってしまいますよね。「なんでできないの?」って。でもその本質を理解できれば、「やり方を忘れてできなくなったなら、着れなくても仕方ないよね」と受け入れられることもあります。相手の違ってしまった認識が何なのかを、知ることが大切だと思うのです。
隣に寄り添って一緒に歩いていく
それで今は、私が介護に携わってきた28年間の知識を、みなさんに知っていただけたらと思い、講座をやらせていただいています。考え方ひとつ変えるだけで、介護のつらさが、おもしろくなったりすることもあると思うんです。実際に講座を受けてくださった方から、ご家族の中の関係性が変わったと報告をいただいたことがありますが、私はそういうスイッチになりたいんです。「関わり方」を変えることで、介護する側も、介護される側も笑顔になれる、おだやかな介護の方法を一人でも多くの方に知っていただけたらうれしいです。
認知症になって「できなくなっちゃったお父さん」は悲しいけれど、「お父さん」が「お父さん」でなくなった訳ではないんですよね。「今までのお父さん」っていう立ち位置から、お父さんを見るのではなくて、隣に寄り添って見てあげれば、また違った景色が見えてくるんです。その方のことを想像して、一番合った方法を提供してあげるというのは、とてもクリエイティブなことだと思うのです。心を使う、ってとても大変なことではありますが、すごく楽しい仕事でもあると思います。
100年後、200年後には、認知症っていう概念すらなくなっている世の中になっていてほしいと思っています。「認知症があってよかった」とまでは言えなくても、「認知症があってもいいことあるよね」と思えるようにしたいですね。
- 林炎子さん公式ブログ
http://ninchishouch.jp/ - 無料小冊子プレゼント
認知症介護歴28年の看護師がお伝えする
「絶対に知っておいてほしい認知症介護を楽にする5つのテクニック」
http://ninchishouch.jp/present/ - 「目からウロコの認知症セミナー」について
http://ninchishoucare.jp/wp/


- 【久田恵の視点】
- 認知症が社会問題として提起されたのは、1972年に出版された有吉佐和子の小説「恍惚の人」が最初と言われています。当時194万部にも及ぶ大ベストセラーになりましたが、認知症への認識はなかなか進みまず、悩んでいるのは介護家族だけみたいな時期が長く続きました。それが超高齢社会になって、急速に認知症がどういうものか知られられるようになりました。その背景には、林さんのような現場で学んだ介護職の方たちの地道な活動があってのことだと実感されます。