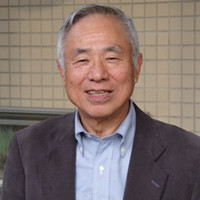石飛幸三医師の
特養で死ぬこと・看取ること
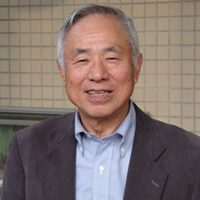
終末期の胃ろうなどの行きすぎた延命治療の是非について問題提起し、ベストセラーとなった『「平穏死」のすすめ』の著者が、特養での“看取り”を語り尽くします。
穏やかな最期を迎えるためにどうすればよいか? 職員と家族の関係はどうあるべきか? これからの特養の使命とは? 施設で働く介護、看護職に贈る「看取り」の医師からの熱いエール!
- プロフィール石飛 幸三(いしとび こうぞう)
-
特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医。
1935年広島県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業。1970年ドイツのフェルディナント・ザウアーブルッフ記念病院で血管外科医として勤務。帰国後、1972年東京都済生会中央病院勤務、1993年東京都済生会中央病院副院長を経て、2005年より現職。診療の傍ら、講演や執筆などを通して、老衰末期の看取りのあり方についての啓発に尽力している。
主な著書に『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか』(講談社)、『「平穏死」という選択』(幻冬舎ルネッサンス新書)などがある。
第7回 特養の配置医について考える~根本にある問題~
これまでの連載では、芦花ホームが“看取りの施設”へと変化してきた過程について紹介してきましたが、ここからは、全国の特養で看取りを広めていくために必要なことについて考えていきたいと思います。第7回と第8回では、特養の配置医について考えます。
ベースにある問題
特養の成り立ちはもともと、身よりのない高齢者を受け入れる『養老院』が、昭和38年、老人福祉法の制定で『老人ホーム』と改称され、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームへとわかれたことに始まります。それから措置入所時代を経て、平成12年に介護保険法が施行されると、契約に基づく入所へと変わり、介護が必要な高齢者を元気にして、また家に帰すための「自立支援」が法の理念に謳われたわけです。でも現実は違いました。
私が芦花ホームに来て、9年目に入りましたが、この9年間、元気になって帰っていった人はただの1人もいません。結局、現実にそぐわないということで、平成18年に看取り介護加算ができて、施設での看取りが推進されるようになりましたが、そもそも、医療の介入がない人たちの生活の質を向上させて、しっかり食べさせてオムツを外して家に帰すという名目がありましたから、医療は完全に切り分けて、医療が必要になったらあくまで医療施設へ送るというベースが出来上がっていました。介護保険の制定当時から、医療と介護の縦割りという根深い問題が存在していたわけです。
こうした背景から、「特養の配置医は医療機関所属のものでなくてはいけない。特養に常勤医を置いてもよいがその行為は限定され、医療行為を行っても医療保険は使えず、医療保険が使えるのは医療機関に所属している配置医のみ」ということになっているのですが、常勤の配置医に保険診療ができないというのは、実際に大きな問題です。ホームの入所者にちょっとした医療行為が必要になっても、私が行う医療行為にはお金が支払われないのです。どうしたって医療行為、薬を出したり検査したりするほうにインセンティブが働きますよ。
特養に入ってくる人たちは、老いて衰えて病気の百貨店のような方たちですから、どこまで老衰という自然の摂理に対して医療行為を行うのか? このことをきちんと考える必要があるのですが、今の配置医の制度ではそれが置き去りにされていると思います。
ましてや病院の医者は一点の接点だけですから、(医療に)やれることがあるならやっておけばよい、延命しておけばよいという発想になりがちです。そうではなくて、特養の配置医に求められるのは、いかに医療を加減[1]するか、ということだと思っています。このことは次回改めて書きますが、そうした医療の加減ができるのは、常勤でいつも利用者さんを見ていればこそですよ。これは、施設不在の医療機関所属の配置医ではとてもできません。
まっとうな配置医の制度に
ベースにある問題から、配置医の制度自体に医師会の利権が絡んでいます。配置医になれば、一度に数十人~100人単位の顧客ができるようなものです。病院経営も苦しい時代ですから、ここを押さえておきたいという医師会の思惑が透けてみえます。しかも、やり方次第でいくらでも診療報酬が稼げます。適当に病名をつけてしまえばいいのですから…。今の制度のあり方ははっきりおかしいと思いますよ。
こんな変な制度ではなく、例えば、今までCさんという患者を診ていた開業医の先生(かかりつけ医)がいたとして、Cさんがそう遠くない施設に入所するのだとすれば、その開業医の先生がその後も施設に来て診ればよいのです。それまでの経過をすべて知っているのですから、患者さんも安心できるはずです。こうした外づけでかかりつけ医が入れるようにするか[2]、そうでなければ、常勤の配置医の制度を整備して保険診療が行えるようにして、常勤医を増やすことが、今後の特養の配置医を考える上での正道だと思います。
実際、制度は整備されていませんが、常勤の配置医がぽつぽつと増えてきているようです。「平穏死のすすめ」の読者からも、「定年後は私も配置医をやります」といった心強いメールがきたりします。これも一つの流れではないでしょうか。
平穏死を叶えるために
常勤の配置医になれば、みんな特養で求められていることがわかると思いますよ。
医療の加減をすることなんです。意味がないことをやってもかえって本人を苦しめることになるんだってことがよくわかりますよ。そして医療の加減が“平穏死”につながるのです。本人が望む「平穏死」を叶えるためには、方法(医療)があっても、それをやらなくても医師が責任をとらなくていいようにするべきなのですが(老衰に対する延命治療をやらなくても刑法219条に問われないようにする)、こうした国民的な議論が早く進められることを願っています。
→→→第8回へつづく。
補足解説
1.^医療の加減・・・不要な医療は行わない(不要な胃ろう等の造設は薦めないといったこと)、過剰な栄養、過剰な水分、不要な薬を無くして、自然な看取りへ導くこと。
2.^かかりつけ医が入れる・・・有料老人ホームやグループホームでは、利用者が希望すれば、かかりつけ医の受診が可能。利用者にとって安心ではあるが、緊急対応が困難であるなど、一長一短がある。