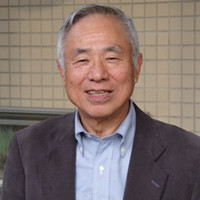石飛幸三医師の
特養で死ぬこと・看取ること
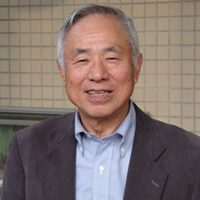
終末期の胃ろうなどの行きすぎた延命治療の是非について問題提起し、ベストセラーとなった『「平穏死」のすすめ』の著者が、特養での“看取り”を語り尽くします。
穏やかな最期を迎えるためにどうすればよいか? 職員と家族の関係はどうあるべきか? これからの特養の使命とは? 施設で働く介護、看護職に贈る「看取り」の医師からの熱いエール!
- プロフィール石飛 幸三(いしとび こうぞう)
-
特別養護老人ホーム・芦花ホーム常勤医。
1935年広島県生まれ。慶應義塾大学医学部卒業。1970年ドイツのフェルディナント・ザウアーブルッフ記念病院で血管外科医として勤務。帰国後、1972年東京都済生会中央病院勤務、1993年東京都済生会中央病院副院長を経て、2005年より現職。診療の傍ら、講演や執筆などを通して、老衰末期の看取りのあり方についての啓発に尽力している。
主な著書に『「平穏死」のすすめ 口から食べられなくなったらどうしますか』(講談社)、『「平穏死」という選択』(幻冬舎ルネッサンス新書)などがある。
第4回 延命治療に警鐘を鳴らした2つのきっかけ
私に胃ろうや経管栄養について考えるきっかけを与えてくれたのが、以下に紹介する「三宅島の自然な死への考え方」であり、職員の気づきをもたらし、食事介助のあり方を改めるきっかけを与えてくれたのが、「現代のサムライ」の行動でした。
三宅島の自然な死への考え方
2000年に三宅島で噴火が起きた際に、避難してきた高齢者を何名か芦花ホームでお預かりしました。それから6年後(私が芦花ホームに着任して半年後)、噴火の際に入所された当時87歳の女性のAさんが、誤嚥性肺炎を起こして病院へ入院されまして、肺炎が落ち着いた後に、入院先の病院からAさんの息子さん(噴火から5年経っていたので、息子さんは三宅島に戻って仕事をしていました)へ電話が入りました。「口から食べると、また誤嚥性肺炎を起こす可能性があるので胃ろうにしましょう」と言われた息子さんは、「三宅島ではそんなことはしません。歳をとったら、それが寿命だから水だけあげていただければそれでいいです」と返答されたそうです。病院は、息子さんの了承が得られないのに勝手に胃ろうをつけるわけにはいきませんので、経鼻胃管を施して芦花ホームへ帰しました。
その後、息子さんが島から施設にやってきた時のことです。鼻から管を入れられている母親の姿をみて、息子さんは号泣されました。「三宅島では、食べられなくなったら水を与えるだけです。水だけで1か月は保ちますし、苦しまずに静かに息を引き取ります」と涙ながらに語る息子さんをみて私はハッとしました。
それまでは脳卒中の後、一時的に鼻から管を入れることはなんてことない当然のことだと思っていましたが、その息子さんの姿や三宅島の考え方に触れて教えられた思いです。それまで、寿命を延ばすことに手を尽くしてきた私にとって大きな気づきとなりました。
姉さん女房を看取った現代のサムライ
もう一つのきっかけは、8歳年上の姉さん女房を介護していたBさん[1]です。芦花ホームに入所するまでの5年間に三度奥さんの首に手をかけたほどの介護地獄だったそうです。ようやく入所されたわけですが、しばらくして、奥さんが誤嚥性肺炎で病院に入院されました。病院から胃ろうにするしかないと言われたのですが、「本人が元気で生きたいなら、なんでもしてあげたいが、認知症で自分のことも、誰のことも、何もわからなくなっているのに胃に穴をあけてまで生かし続けるというのは、恩を仇でかえすようなものだ」ときっぱりと胃ろうを拒否されたのです。その芯の強さに、現代のサムライの意気を感じました。
そしてそのまま奥さんを連れて芦花ホームに戻ってくるということで、ホームで一悶着起こりました。ただでさえ、口うるさい家族だったBさんでしたので、裁判のトラウマが癒えていない職員は、「誰が食べさせるのか?」と拒否反応が起こったのです。また、誤嚥をさせて訴えられてはたまらない、と言うのです。
そこは、さすがに現代のサムライでした。Bさんは奥さんを連れて帰ると決めた時から、食事介助はすべて自分でやると決めておられたのです。連れて帰ってきたその日に、奥さんを椅子に座らせて、Bさんが食べさせたわけですが、その様子を職員が固唾を飲んで見守りました。Bさんはほっぺたを撫でて、口腔マッサージをしてから、おもむろにゼリーを口に入れたところ、奥さんはそれをごっくんと飲み込んだのです。その瞬間、周りでみていた職員は一斉に手を叩いて喜びました。目に涙を浮かべる職員すらいたほどです。
その後、Bさんと看護職、介護職とで食事介助を続けていくことになるのですが、驚いたことに一日600キロカロリーの栄養で1年半、自分の口で食べて生き続けることができました。この経験を通じて、芦花ホームでの食事介助のあり方が変わったのです。
延命治療の是非
このようにお話をしてきますと、胃ろうや経鼻栄養が悪者のように感じられるかもしれませんが、これらの医療処置がいけないと言っているのではありません。口から食べられない子どもや、回復の見込みがある状態での一時的な手段として大切な医療処置です。
しかし、病院の医師が「方法があるのにやらなかった」と責任を負わされることを怖れて、その後の患者や家族の行く末も考えずに漫然と胃ろう等の処置を行っている現在のあり方は絶対におかしいと思うのです。責任逃れの胃ろうだとすれば、患者も家族も悲劇ですよ。
三宅島での自然な死のあり方やBさんの奥さんの看取りを通じて、芦花ホームが変わっていったことは確かです。特養とは看取りを行う場なんだ、という意識が職員に芽生えていきました。そうして、現在では、病院で亡くなる方が激減し、ほとんどの方を芦花ホームで看取るようになり、そのことで全国から見学者がやってくる施設になったのです。
→→→第5回へつづく。
補足解説
1.^Bさん・・・太平洋戦争から帰ってきて、慕っていた近所のお姉さんと念願叶って結婚。8歳年上の奥さんには、戦争の間、自分の母親と妹の面倒をみてもらい、家族と無事に再会できたことに深い恩義を感じていた。