誌上ケース検討会 第89回 自殺をほのめかす利用者を支援するソーシャルワーカーにスーパーバイザーとしてどうサポートすればよいのか (2007年10月号掲載)
2025/10/14
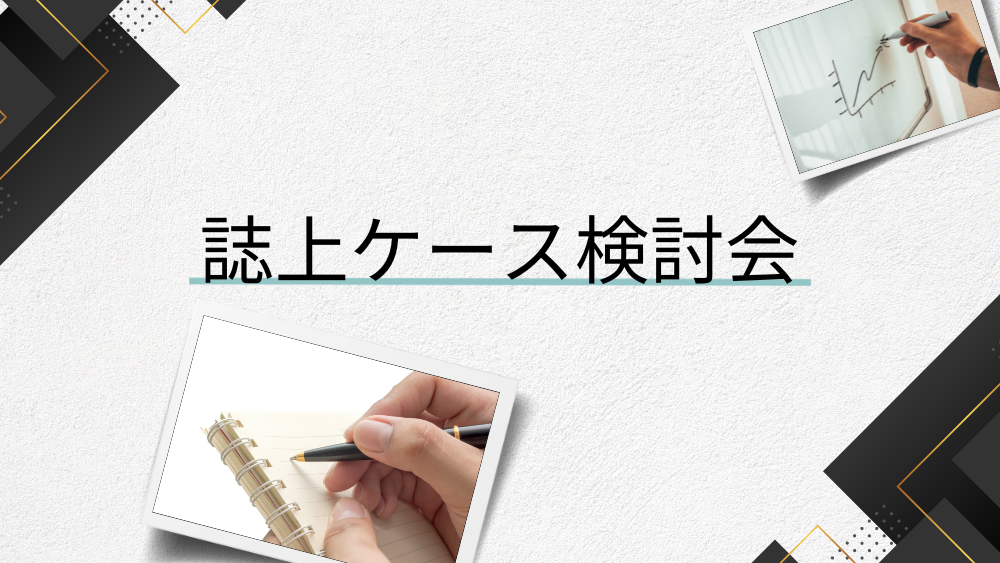
このコーナーは、月刊誌「ケアマネジャー」(中央法規出版)の創刊号(1999年7月発刊)から第132号(2011年3月号)まで連載された「誌上ケース検討会」の記事を再録するものです。
同記事は、3人のスーパーバイザー(奥川幸子氏、野中猛氏、高橋学氏)が全国各地で行った公開事例検討会の内容を掲載したもので、対人援助職としてのさまざまな学びを得られる連載として好評を博しました。
記事の掲載から年月は経っていますが、今日の視点で読んでも現場実践者の参考になるところは多いと考え、公開することと致しました。
スーパーバイザー
高橋 学
(プロフィールは下記)
事例提出者
Kさん(地域包括支援センター・主任ケアマネジャー)
提出理由
本ケースを担当しているのは、当包括センターの社会福祉士(25歳・女性、以下「SW」と表記)です。彼女は福祉系の大学を卒業後、施設での介護職を経て、昨春の包括センターの開設と同時に異動(出向)となりました。そのため、相談業務の経験はまだ1年数カ月です。
利用者のBさんは、精神的不安定さやアルコール依存の傾向もあり、「死にたい」といった言葉を何度も繰り返します。長くかかわっているヘルパーや訪問看護師などのサービス担当者は「言葉だけで実際に死ぬことはない」と語り、「実務経験の短い若いSWだから、本人の言葉を真に受けて心配しているのだろう」と受けとめている様子です。しかし、この1年の間にSWの担当していた利用者で、自殺してしまった方がいるため(SWのかかわりが自殺を引き起こしたわけではありませんが)、彼女(及び私)は「口先だけのことと、軽く流してはいけない」という思い(恐怖心)と、「その言葉に振り回されて、自立を妨げるような過剰援助をしてしまってはいけない」という思いの間で日々葛藤している状態です。
そういった彼女(SW)をいかに支援していくかを考えるなかで、彼女と同じように「せめて自殺だけは……」という思いが、現在の私の一番強い願いとなっています。今後、どのようにこのケースをとらえ、彼女をサポートしていけばよいのか、助言をいただければと思います。
ここから先は、誌面の PDFファイル にてご覧ください。
プロフィール
高橋 学(たかはし まなぶ)
1959年生まれ。早稲田大学大学院博士後期課程満期退学。東邦大学医学部付属大森病院、北星学園大学を経て昭和女子大学大学院福祉社会研究専攻教授。専門は、医療福祉研究、精神保健福祉学、スーパービジョン研究、臨床倫理など。
