誌上ケース検討会 第88回 包括センターは地域の関係機関や利用者とどうかかわるべきなのか (2007年9月号掲載)
2025/09/30
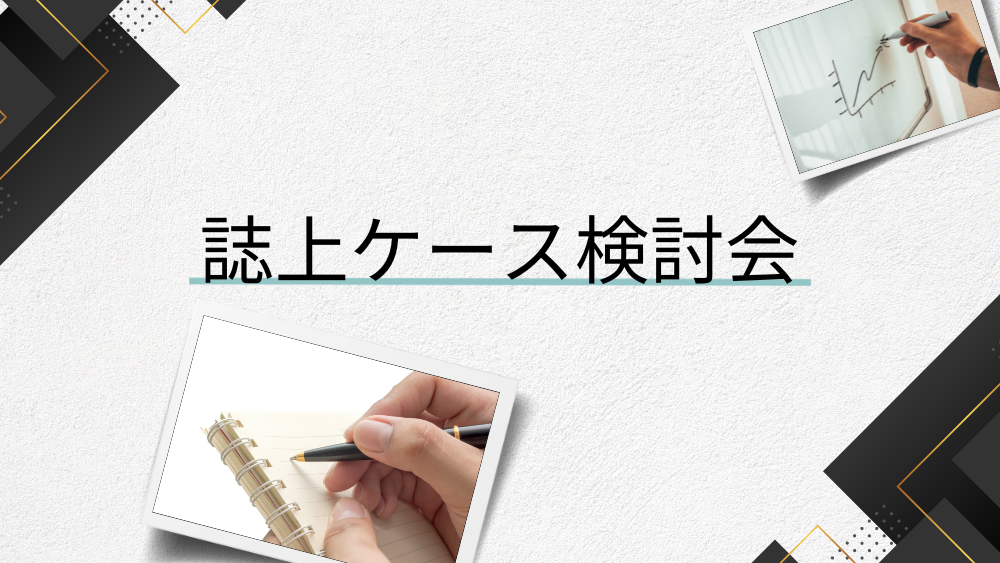
このコーナーは、月刊誌「ケアマネジャー」(中央法規出版)の創刊号(1999年7月発刊)から第132号(2011年3月号)まで連載された「誌上ケース検討会」の記事を再録するものです。
同記事は、3人のスーパーバイザー(奥川幸子氏、野中猛氏、高橋学氏)が全国各地で行った公開事例検討会の内容を掲載したもので、対人援助職としてのさまざまな学びを得られる連載として好評を博しました。
記事の掲載から年月は経っていますが、今日の視点で読んでも現場実践者の参考になるところは多いと考え、公開することと致しました。
スーパーバイザー
奥川 幸子
(プロフィールは下記)
事例提出者
Jさん(地域包括支援センター・社会福祉士)
提出理由
H18年度の介護保険法改正では、新たに要支援1・2が加えられ介護予防の必要性が強調された。この間、地域包括支援センター(以下、包括センター)の社会福祉士として立ち上げにかかわり、包括センターの一通りの業務を行ってきた。
要支援認定者の介護予防ケアプラン(以下、予防プラン)の「三者契約」(包括センターが居宅介護支援事業所のケアマネジャーに業務委託をしながら予防プランの立案・相談支援を行う形態)というかたちで利用者にかかわるなかで、ほとんどのケアマネジャーや訪問介護事業所から「この利用者は要支援なのですから、必ず利用者とともに行う、というかたちでないとプラン作成はできないのではないですか?」と言われた。必ずしもそのような規定はなく、決して「介護予防=サービス時間に一緒に作業すること」ではないと考えてきた私は、ケアプランの承認をする際にケアマネジャーと意見がずれることも多々あった。
介護予防、また自立した生活とは「自分のことは自分でできて、要介護認定から卒業できること」で、「そのための意欲のない人は怠け者」という(間違った?)認識が広がっていると感じる場面が多かったが、介護予防の考え方とはそのような狭いものなのか。また、包括センター職員として他の事業所とチームを組んで仕事をするときに、どのように考えを共有していったらいいのか。こうした点についてご示唆いただければと思います。
所属機関(包括センター)について
・所属機関の所在するS市には全部で7カ所の包括センターがあり、そのすべてが医療法人か社会福祉法人(特養)への 委託運営である。ほぼすべてが在宅介護支援センター業務を行っていた法人が引き継ぐかたちとなった。
・各包括センターの担当地域は行政が割り振りを行い、当包括センターの担当は在宅介護支援センター時代とは異なる地域となった。したがって、地域のケアマネジャーやサービス事業所と一日も早く「顔の見える関係づくり」を行うことが課題であった。
・包括センターの業務は主に4つ(予防プランの作成、総合相談、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント)あるが、立ち上げ1年目ということもあり、まずは3名全員ですべての業務を均等に行う形態をとった。
ここから先は、誌面の PDFファイル にてご覧ください。
プロフィール
奥川 幸子(おくがわ さちこ)
対人援助職トレーナー。1972年東京学芸大学聾教育科卒業。東京都養育院附属病院(現・東京都健康長寿医療センター)で24年間、医療ソーシャルワーカーとして勤務。また、金沢大学医療技術短期大学部、立教大学、日本社会事業大学専門職大学院などで教鞭もとる。1997年より、さまざまな対人援助職に対するスーパーヴィジョン(個人とグループ対象)と研修会の講師(講義と演習)を中心に活動した。主な著書(および共編著)に『未知との遭遇~癒しとしての面接』(三輪書店)、『ビデオ・面接への招待』『スーパービジョンへの招待』『身体知と言語』(以上、中央法規出版)などがある。 2018年9月逝去。
