誌上ケース検討会 第87回 知的障害のある24歳の男性と母親の在宅生活を支援する (2007年8月号掲載)
2025/09/16
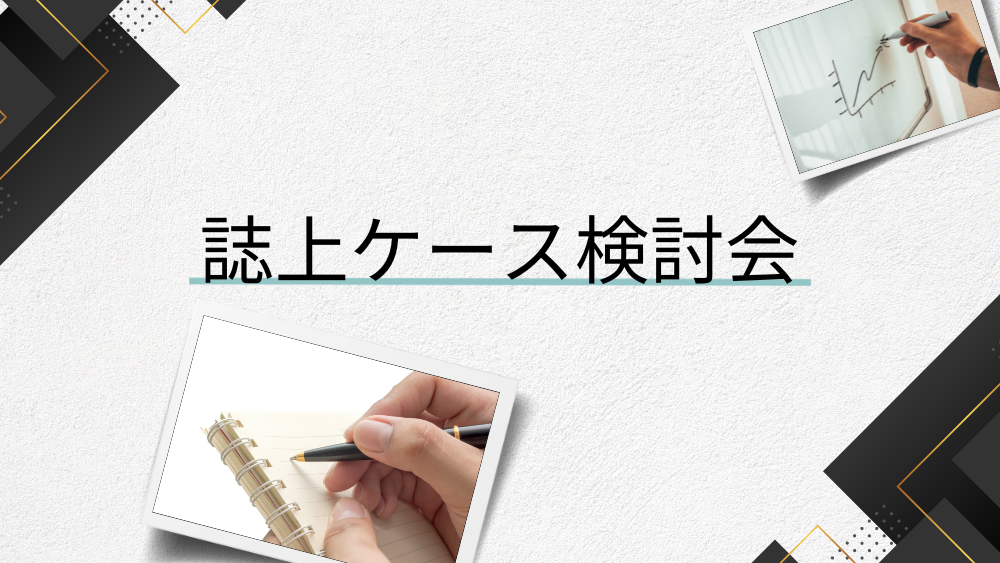
このコーナーは、月刊誌「ケアマネジャー」(中央法規出版)の創刊号(1999年7月発刊)から第132号(2011年3月号)まで連載された「誌上ケース検討会」の記事を再録するものです。
同記事は、3人のスーパーバイザー(奥川幸子氏、野中猛氏、高橋学氏)が全国各地で行った公開事例検討会の内容を掲載したもので、対人援助職としてのさまざまな学びを得られる連載として好評を博しました。
記事の掲載から年月は経っていますが、今日の視点で読んでも現場実践者の参考になるところは多いと考え、公開することと致しました。
スーパーバイザー
野中 猛
(プロフィールは下記)
事例提出者
Yさん(地域生活支援センター・ソーシャルワーカー)
クライアント
Mさん(24歳・男性)
障害・疾病状況
知的障害(療育手帳4度、H18年3月取得)。定期通院などはなし。
家族構成
母(48歳)と二人暮らし。妹(21歳・療育手帳4度)もいるが、H17年11月にグループホームに入居。父親はH13年、自宅で脳出血で倒れ死亡。父母はMさん出生時より養育能力の低さを指摘されている。
生活状況
持ち家(3DKのマンション)に暮らす。母のパート収入(10万円強)と年金(遺族年金とMさんの2級障害基礎年金・H18年5月に申請)での生活。しかしながら、Mさんの奨学金や学費などの返済に追われ、またMさんより「生活費」と称して遊ぶお金を要求されることも多く、家計は逼迫している(低所得2で非課税)。
Mさんは、母から食事代として¥1,000/日と、自己口座への年金¥30,000/月で生活している。
日々の生活時間は不規則で、昼夜逆転しており、遅くまでテレビ、ラジオを観ている。日中は寝ているかと思えば、ふらふらと遊びに出ていることも多く、無断外泊もあり。時々、母に対して(以前は妹にも)暴力が出る。
家族・親族との関係性
母はMさんと強い共依存関係にあり、Mさんに強く指導できない。また、関係機関に支援を求めるかと思えば、八つ当たり的に支援を拒否することもある。
母方の祖父母の所在・関係は不明。父方の実家の話はよく出てきており、叔父(父親の弟)が時折本人を遊びに連れて行ったりしている様子。
母親は判定は受けていないが、問題処理能力・理解力ともに低い。
ここから先は、誌面の PDFファイル にてご覧ください。
プロフィール
野中 猛(のなか たけし)
1951年生まれ。弘前大学医学部卒業。藤代健生病院、代々木病院、みさと協立病院、埼玉県立精神保健総合センターを経て、日本福祉大学社会福祉学部教授。専攻は臨床精神医学、精神障害リハビリテーション、地域精神保健、精神分析学など。主な著書に『心の病 回復への道』(岩波新書)、『図説ケアマネジメント』『ケア会議の技術』『多職種連携の技術(アート)』(以上、中央法規出版)、『ソーシャルワーカーのための医学』(有斐閣)などがある。 2013年7月逝去。
