誌上ケース検討会 第86回 ターミナル期の患者の真意を理解する(2007年7月号掲載)
2025/09/02
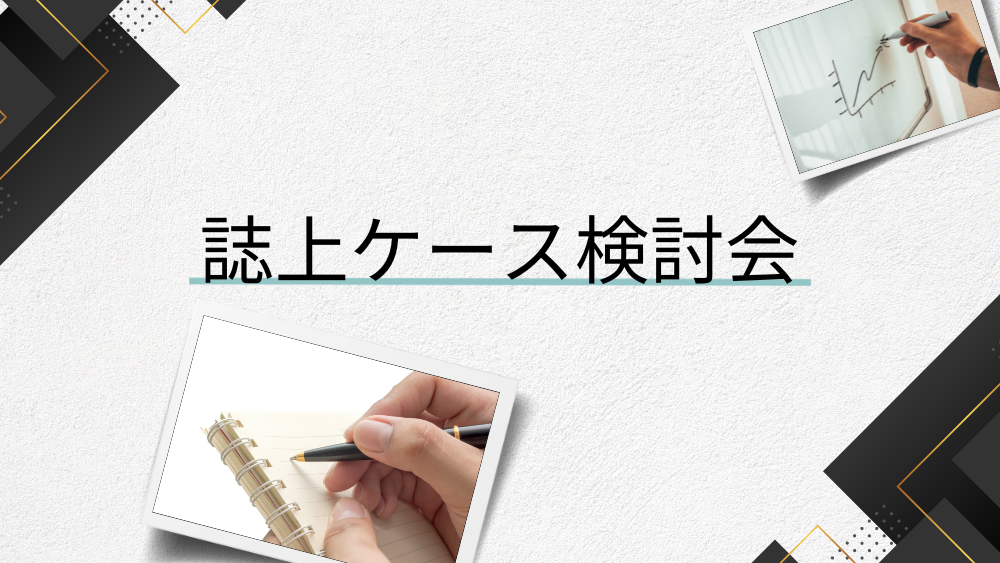
このコーナーは、月刊誌「ケアマネジャー」(中央法規出版)の創刊号(1999年7月発刊)から第132号(2011年3月号)まで連載された「誌上ケース検討会」の記事を再録するものです。
同記事は、3人のスーパーバイザー(奥川幸子氏、野中猛氏、高橋学氏)が全国各地で行った公開事例検討会の内容を掲載したもので、対人援助職としてのさまざまな学びを得られる連載として好評を博しました。
記事の掲載から年月は経っていますが、今日の視点で読んでも現場実践者の参考になるところは多いと考え、公開することと致しました。
スーパーバイザー
高橋 学
(プロフィールは下記)
事例提出者
Bさん(総合病院・MSW)
提出理由
入院患者Aさんの在宅生活再開に向け、約3年半の間、退院援助を繰り返してきたケースです。自宅での生活を熱望し、努力をしてきたAさんでしたが、先日、当院で命の終わりを迎えました。看取りに向け、できる限りのことを取り組んできました。しかし、かかわりを振り返り、過去の退院援助の場面で後悔の想いが残っています。
それまでは、何の疑問もなく「A氏の意志決定を支えてきた」と自負していました。しかし、最後の入院時に聞いたAさんの言葉をきっかけに、「かかわりが長くなったぶん、わかったつもりになり、本当の声に耳を傾けていないのではないか」と考えるようになりました。Aさんは「今までの生活は本当に苦しかった。夢も希望もない。どうでもいい」と表現。それまでAさんの考えを実現するために取り組んできましたが、その生活が「苦しかった。辛かった」と顔をくしゃくしゃにしながら表現する姿を見て、今までの援助が間違っていたのか、と考えるようになりました。
Aさんとのかかわりは終了しましたが、今後同じような疾患や医療依存度の高い方との出会い、かかわりを考えると、しっかり振り返ることの必要性を感じています。
Aさんのニーズは何か、Aさんにとっての安住の地で生活再開に向けどんなことを整える必要があったかについて学び、次の援助につなげていきたいと考え、本事例を提出いたします。
ここから先は、誌面の PDFファイル にてご覧ください。
プロフィール
高橋 学(たかはし まなぶ)
1959年生まれ。早稲田大学大学院博士後期課程満期退学。東邦大学医学部付属大森病院、北星学園大学を経て昭和女子大学大学院福祉社会研究専攻教授。専門は、医療福祉研究、精神保健福祉学、スーパービジョン研究、臨床倫理など。
