どこまでがケアマネジャーの業務範囲? ケアマネ業務の実際と考え方
2025/10/06
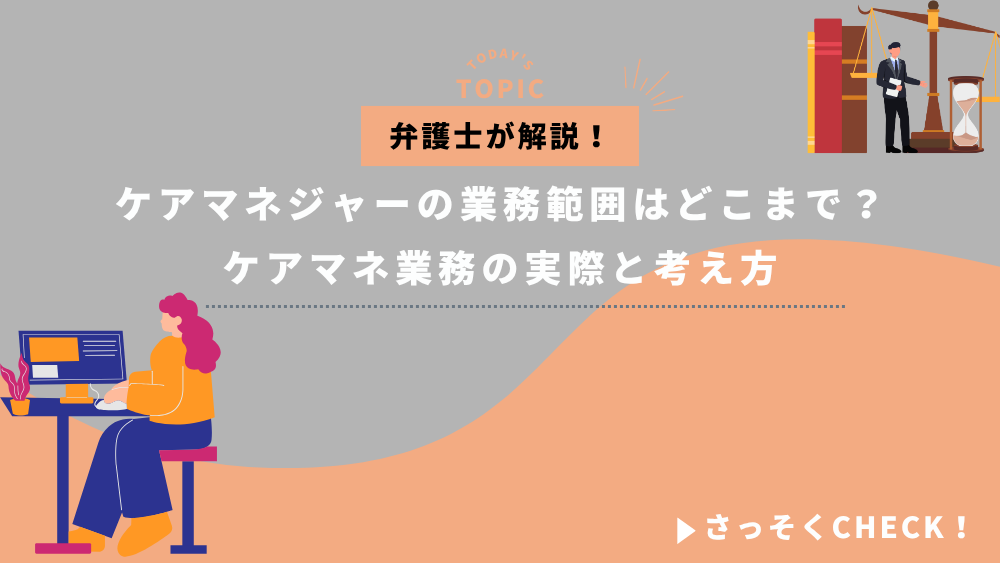
2024年4月から行われている厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(以下、検討会)において、ケアマネジャー(以下、ケアマネ)の業務範囲について議論されています。本来のケアマネ業務とは何か、そして業務負担増の一因でもある、“グレーゾーンな業務”について考えてみましょう。
【記事の監修者】
外岡 潤(そとおか・じゅん)
弁護士法人おかげさま代表弁護士(第二東京弁護士会所属)、ホームヘルパー2級、ガイドヘルパー、保育士、レクリエーション介護検定2級など。
東京大学法学部卒。平成21年、介護・福祉系のトラブルに特化した法律事務所「おかげさま」を開設。財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント。平成24年より一般社団法人介護トラブル調整センター代表理事。令和4年、法人化により名称を「弁護士法
人おかげさま」に変更。近著に『介護職六法 介護現場のモヤモヤに弁護士が答える』(中央法規出版、2025年)。
「遠くの親戚より近くのケアマネ」現象が起こっている!?
「遠くの親戚より近くの他人」という言葉をご存じでしょうか。「いざという緊急時には、遠方に住む親戚よりも、近隣住民など身近にいる他人のほうが頼りになる」という意味なのですが、ケアマネの現場では「遠くの親戚より近くのケアマネ」になっているようです。
考えてみれば、少子化・高齢化に伴い核家族化、「おひとりさま」が増えつつあることは明らかであり、これまで、サザエさん一家のような「家族」が担ってきた役割を誰かが肩代わりしなければ、高齢者が住み慣れた地域で暮らしていくことは不可能です。
しかし、一方で、当然のことですが、ケアマネは利用者の家族などではありません。あくまで契約により、専門職として利用者にかかわるわけですから、請け負う業務にも限界はあります。
法的にみたケアマネ業務
では、法的にみてケアマネの本来の業務範囲はどのように区切られるのでしょうか。法令には次のとおり定められています。
介護保険法第7条第5項
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス(中略)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者(中略)等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして(中略)介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
ここでのキーワードは、「連絡調整」です。すなわち、ケアマネは自らが動いて利用者の問題を解決するのではなく、全体を俯瞰するコーディネーターとして、各関係機関に連絡・調整を行い、利用者につなげることが本来の役割といえるでしょう。しかし、これだけでは手がかりになりません。ケースごとに解釈を交え、あるいは別の法律や考え方を駆使する必要がある場合もあります。
「誰かがやらなければならない」葛藤と難しさ
次に、現場のケアマネが判断に迷う具体的な業務をみていきましょう。たとえば、次のような業務は、ケアマネが対応する業務といえるでしょうか。
①郵便・宅配便等の発送、受け取り
②書類作成・発送
③代筆・代読
④救急搬送時の同乗
⑤部屋の片づけ・ごみ出し、買い物などの家事支援
⑥福祉サービスの利用や利用料支払いの手続き
⑦預貯金の引き出しや振込
⑧財産管理
⑨入院中・入所中の着替えや必需品の調達
⑩徘徊時の捜索
⑪死後事務
⑫医療同意
ここで挙げた業務は、いずれも厚生労働省の検討会においてケアマネジャーの業務範囲に該当するか議論された業務です。検討会では、これらのうち、①~④は「保険外サービスとして対応しうる業務」、⑤~⑪は「他機関につなぐべき業務」、⑫は「対応困難な業務」に整理・分類されており、いずれもケアマネジャーの法定業務ではないとされた業務です。そして、検討会の中間整理では、市町村が主体となり関係者を含めて地域課題として協議することとしています。
とはいうものの、現場のケアマネにとってはそう簡単に割り切れるものではなく、「業務範囲ではない」と認識・理解しつつも、利用者や家族からの要望を断り切れずに、グレーゾーンな業務に対応している現状にあります。これは、「誰かがやらなければどうにもならない」という部分に大いに関係しています。法令を根拠に「ケアマネの業務ではないから断るべき」と結論づけることは簡単にできます。しかし、ケアマネがそれを断れば、結局目の前の利用者やその家族の悩み(ニーズ)は放置されたままです。最後の最後で、「目の前の利用者・家族は困っており、ケアマネである私に助けを求めている。そのような状況で利用者・家族を見捨てるわけにはいかない」と判断をせざるを得ないというのが、現実なのではないでしょうか。一方で、最大限頑張り続けるスタンスでは、現実問題として、対応する業務が増え、その分時間と労力がかかることも事実です。
ケアマネの業務範囲を取り巻く問題は、法令を根拠にスパッと割り切れる性質のものではなく、常に葛藤が付きまといます。最終的にどうするかはケアマネ一人ひとりの判断にゆだねられますが、その際に自分なりに納得して判断できるよう、参考書をヒントにしながら考えていきましょう。
もっと詳しく知りたい方に! おすすめの書籍
本記事の内容は、下記書籍の内容をもとに編集・作成しております。書籍では36の事例をもとに、判断ポイントを詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
