対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第14回 「問題」よりも「問題解決」に焦点を当てるコーチング<後編>
2025/10/02
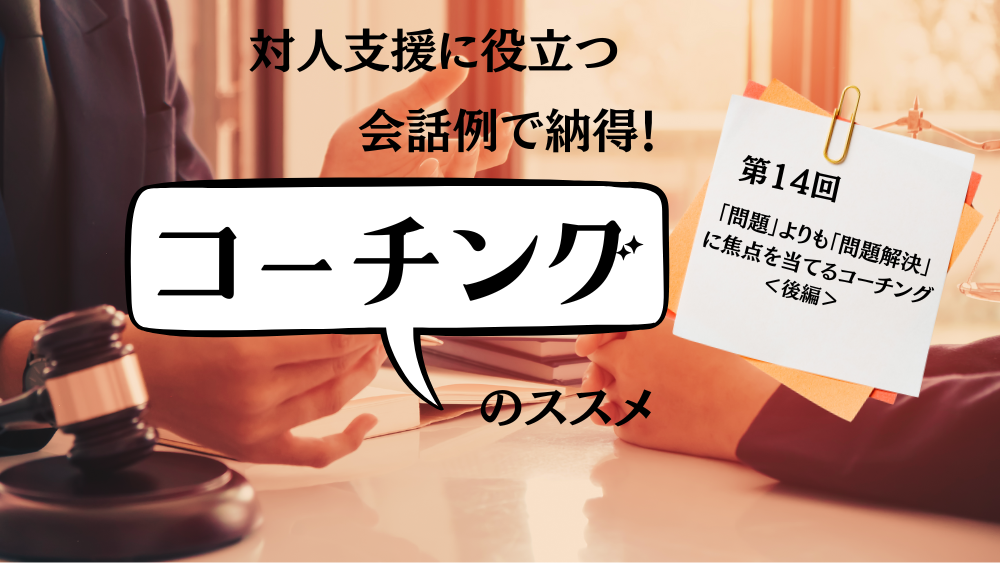
ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。
この記事の監修者
眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)
1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。
前回は、問題に直面した時の考え方やコーチングの手法について、NG例を紹介しました。今回はOK例を紹介します。
「問題解決」に焦点を当てたセルフクエスチョン
パフォーマンスが高く成果が出やすい人は、目の前にある「問題」ばかりに気をとられることなく、問題の向こう側にある「問題解決」を見据えての問いを自分自身に語りかけます。
問題解決を見据える人のセルフクエスチョン【OKバージョン】
〇「この問題の解決策を3つ挙げるとしたら、それは何か?」
→「まずは今考えられる最善策を挙げてみることから始めよう」と前向きにとらえています。
〇「問題を解決するのに、どの程度の時間をかけることができるか?」
→限られた時間のなかで、これまでの経験や全体の仕事のバランス等から解決にかかる見込み時間を今決めよう」と問題解決に自ら期限を設けています。
〇「相談するとしたら、誰に相談するか?」
→「一人で抱え込まず、自ら考えた解決案の妥当性や実効性を信頼できる人に評価してもらおう」と解決策の精度を上げています。
〇「この問題を解決できたら、自分にとってどんなよいことがあるだろうか?」
→「問題解決後のビジョンを明確にしよう」と自身への成果や影響を見通しています。
〇「仕事への熱意ややる気はどこからもってこられるだろうか?」
→「問題解決の困難さに引っ張られることなく、高いモチベーションを維持しよう」という強い意気込みとリスクヘッジ(危険回避)を示しています。
〇「自分はどんな人として周りに記憶されたいだろう?」
→「問題解決までのストーリーをヒーロー(ヒロイン)として語り継がれるための最大限の努力をする」という自分への鼓舞と固い決意を表しています。
〇「1年後の自分はどうなっているか?」
→「現状維持を避け、新しい困難にチャレンジすることで成功を引き寄せよう」と将来の自分自身の成長した姿を思い描いています。
〇「もし自分だけしか解決の鍵を持っていないとしたら、それは何か?」
→「自分自身を問題解決のための最大の社会資源として活かすためにできる限りの力を発揮しよう」と人任せにしない主体的な立場を堅持しています。
これらの質問は、具体的に問題を解決する糸口を見つけることに注意が向いています。NGバージョン(第13回参照)との差は歴然です。自分の思考の傾向に気づき、自分に対する問いかけを少し変えるだけで、大きな変化と成果を体感できるのです。
しかし、頭ではわかっていても行動につながらないのが多くの人の弱みです。そこで、問題や課題に直面している人に対して、仲間同士のコーチングによりお互いを支援することができます。「問題」ではなく「問題解決」にフォーカスできるように気づきを促すコーチングの例をみていきましょう。
会話例で深堀り!仲間が問題に直面した時のコーチング【OKバージョン】
ケアマネA:Bさんが直面している事業所内のコミュニケーションの問題は何ですか?…①
ケアマネB:自分が忙しくてなかなか部下とかかわる時間がとれないことです
ケアマネA:そうですか、私も同じ問題をもっています。ところで、Bさんは部下とのかかわりの頻度や時間をどの程度までつくれたらよいとお考えですか?… ②
ケアマネB:一人ひとりの部下に週に最低1回5分から10分程度の面談が継続できたらと考えています
ケアマネA:なるほど。それでは、Bさん、日々忙しいなかでも時間がとれていると感じられるのはどのようなときですか?… ③
ケアマネB:そうですねぇ……、比較的時間がとれるのは、午前中の事業所会議のあとや夕方16時半以降です。どちらも訪問を入れないでデスクワークの予定にしていますから……。そうか、部下もほぼ同じスケジュールだから、
そのあたりの時間を活用すれば何とかなりそうですね
ケアマネA:本当ですね。部下のなかでも特に誰との時間がとれないと思っていますか?… ④
ケアマネB:ケース担当が一番多いCさんがとても気になっています
ケアマネA:Cさんとの時間調整で工夫できることは何ですか?… ⑤
ケアマネB:今思いつきましたが、一番予定しづらいCさんとの約束を優先的に調整することです。それなら、できそうですね
ケアマネAは、①~⑤の5つの問いかけをケアマネBにしています。①の質問だけが「問題」を明らかにする質問でした。②以降は、その問題に対する「問題解決」関連の質問に特化しています。
うまく解決できなかった問題に注目していたケアマネBは、問題解決のアイデアを具体的に口に出すことで意識が変わっていきました。自分のアイデアにオートクライン(自分で話した言葉が自分自身に作用すること)が起こり、問題解決に対する気づきがもたらされています。

視点を変える質問で気づきを引き出し行動につなげる
コーチングでは、質問は単にわからないことを尋ねるためのものではありません。お互いの視点を変えること、また先のビジョンや今の問題点を明らかにすることが大切です。さらに、本人さえも気がついていないアイデアを引き出すこと、問題解決の資源を見つけることも重要な目的になります。
なかでも、効果的なのは、相手の視点を変える質問です。相手の行動に影響を与えるからです。それがタイミングよく適切にできると、新しい可能性や価値ある情報を引き出すことができ、相手の行動を変えるきっかけになります。
コーチングには次のような公式があります。
望んでいる状態(目標)=現在の状態+行動
思いや言葉だけをいくら重ねても目標は実現しません。
目標に到達するには、現在の状態にどれだけ「行動」を重ねていくかが重要な鍵になります。
