対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第13回 「問題」よりも「問題解決」に焦点を当てるコーチング<前編>
2025/09/18
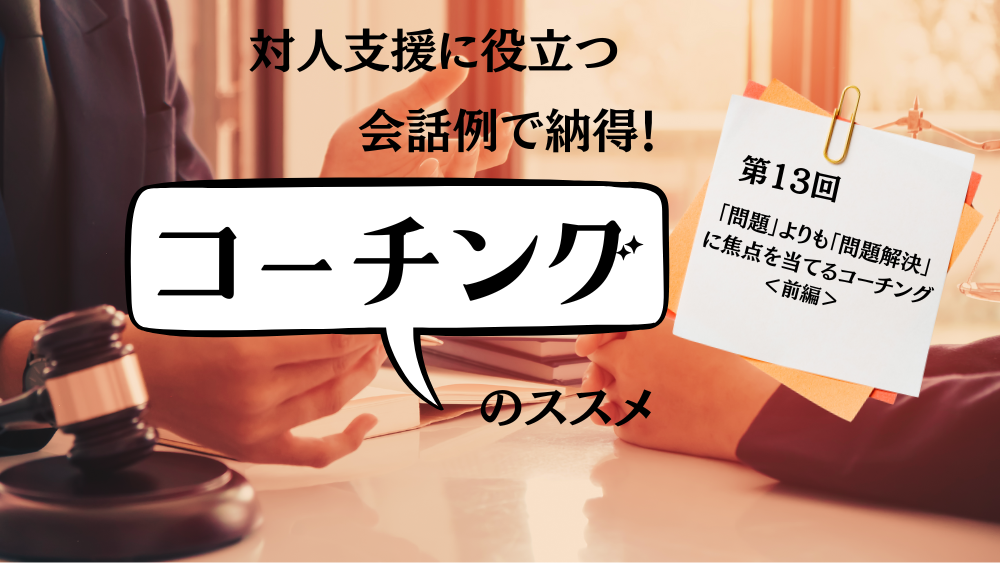
ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。
この記事の監修者
眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)
1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。
「問題解決」より「問題」が好きな人
仕事を進めていくなかで、大きな壁に直面し、行き詰まってしまうような経験はおそらくどんな人にもあるでしょう。そのような場合に、安易にあきらめてしまうのか、自分は悪くないと正当化するのか、一人で悩みを抱えてしまうのか、何とか乗り越えようとするのか、人によってさまざまな反応があります。
いずれにしても、仕事は紆余曲折しながらも一つひとつの問題を解決し前に進める必要があります。
しかし、一部の人々は「問題解決」よりも目の前の「問題」に心が奪われがちです。これでは、解決までの時間が遅れ、仕事の生産性は下がるばかりです。
問題に直面した時の反応【NGバージョン】
問題ばかりに目を向ける人は、障害にぶつかったとき、とっさに自分に対して次のような問いかけをする習性があります。
×「一体どうすればいいのか?」
→「これからどうするかまったく手に負えない」八方塞がりの状態を嘆いています。
×「なぜこんなことをしてしまったのだろう?」
→「やらなければよかった」という後悔の念に押しつぶされています。
×「本当は自分には才能がないのではないか?」
→「自分には力がない」という自信喪失や自己否定に陥っています。
×「どうして同じ失敗ばかり繰り返しているのだろう?」
→「何度やってもダメだ」という挫折感や無力感に打ちひしがれています。
×「なぜ、あのときにあれをしておかなかったのだろう?」
→「リスクやほかの選択肢を無視して突っ走ってしまった」という罪悪感や負い目に苛まれています。
×「なぜ私は幸せではないのだろう?」
→「こんなに頑張っているのに報われない」という徒労感や恨みに近い感情を抱いています。
×「私はこのままでいいのか?」
→「今のままの自分では嫌だ」という漠然とした不安や焦りに襲われています。
×「どうして誰も教えてくれなかったのか?」
→「私のせいではない」といった責任転嫁や無反省の態度でやや開き直っています。
これらすべての質問に共通しているのは、問題解決への歩みを一時的もしくは完全に止めてしまうことです。当然、行動は萎縮してしまい、気持ちも明るくなりません。
会話例で深掘り!仲間が問題に直面した時のコーチング【NGバージョン】
職場や地域には、問題に直面している人に対して気づきを引き出すために支援を惜しみなく提供する人がいるものですが、うまくアプローチできず、支援者もろとも問題の深みにはまっていく場合があります。
よくありがちな一つの例を紹介しましょう。ケアマネAは地域包括支援センターの主任介護支援専門員、ケアマネBは居宅介護支援事業所の管理者です。
ケアマネA:Bさんが直面している事業所内のコミュニケーションの問題は何ですか?
ケアマネB:自分が忙しくてなかなか部下とかかわる時間がとれないことです
ケアマネA:そうですか、私もそうなんです。同じ問題をもっていますね。たとえば、朝のミーティングで話す時間はとれないですか?
ケアマネB:そうですね。ちょっとはあるかもしれませんが、部下のケアマネはすぐに訪問に出かけてしまうので……
ケアマネA:そうですか。それはうまくいきませんね。では、帰って来たタイミングで話すのはどうでしょうか?
ケアマネB:何人かは話すことができますが、自分もサービス担当者会議やモニタリングで外に出てしまっていて、全員と話すのは難しいんですよ
ケアマネA:そうですかぁ、いやぁ、なかなか難しいですね
ケアマネB:そうなんです。難しいんですよ
この対話では、ケアマネAがケアマネBに対して問題解決のためのアプローチを試みましたが、結局ケアマネA、Bもろとも問題の深みにはまってしまいました。
「自分で解決」を導く!″引き出す”コーチングで成長を促す
先の例でケアマネA、B両者が問題を解決できなかった原因は、本来のコーチングの機能がうまく働いていなかったことによります。
対話からはケアマネAの「自分がケアマネBの問題を解決する」という目的が読み取れます。しかし、本来のコーチングでは、支援者は部下や同僚など仲間の問題を「解決する」のではなく、「自分自身で問題を解決できるように話を引き出す」ことが重要です。相手に気づきを促すことを意識した会話がコーチング成功の秘訣です。

次回は、「問題解決」に焦点を当てたコーチングの手法を紹介します。
