独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.6 独立・開業の準備
2025/10/10
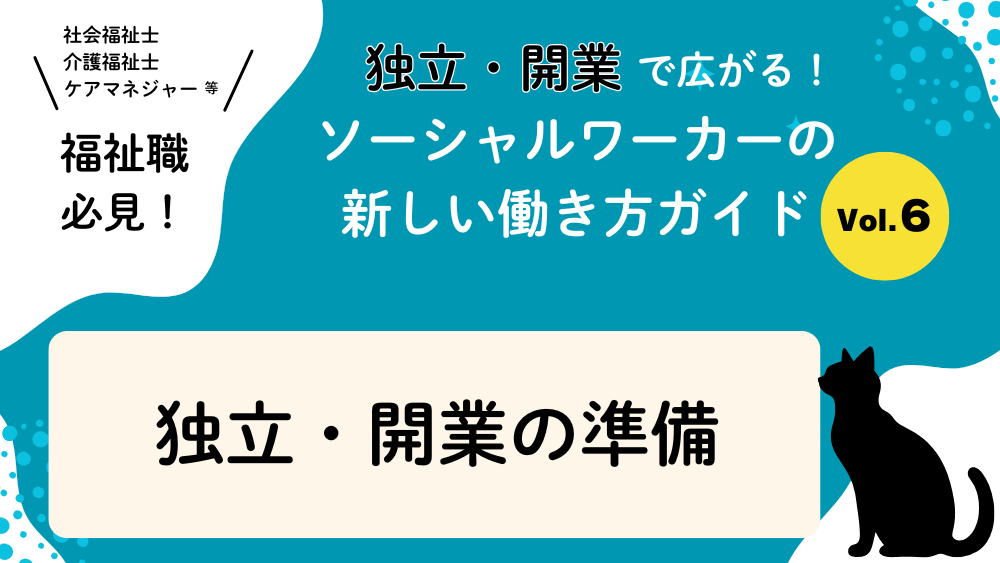
福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!
この連載は、介護や福祉の仕事に熱い想いをもち、これから資格取得を目指している方、あるいはすでに資格をもっていて、さらなるスキルアップを考えている方に向けてお届けします。
今回は、Vol.5でご紹介した、他業界から福祉に飛び込み、ソーシャルワーカーとして個人事務所を開設した松谷さんのケースから、独立・開業の準備について整理します。
著者
小川 幸裕(弘前学院大学社会福祉学部教授)
横田 一也(株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ代表)
Vol.5では、一般企業の勤務や専業主婦を経て福祉の世界に転身し、個人事務所を設立した松谷さんのケースをご紹介しました。松谷さんの経験からは、独立・開業を成功に導くための周到な「準備」の重要性が見えてきます。今回はその内容を基に、独立前に整えておくべき①「スキル」、②「事業計画」、③「資金」、④「事務所」という4つの視点から解説します。
1.必要なスキル・経験? ――実践知と「つながる力」
松谷さんの経歴は、福祉現場での実践経験が独立の土台となることを示しています。施設の役割の限界や、利用者家族を含めた支援の必要性を肌で感じた「実践知」こそが、松谷さんの活動の原点です。
しかし、松谷さんの事例がより教えてくれるのは、専門スキルに加えて不可欠な「ソフトスキル」の重要性です。特に以下の3つが挙げられます。
(1)ネットワーク構築力
松谷さんは、独立前の2年半を準備期間と捉え、社会福祉士会の活動などを通じて意図的にネットワークを築きました。これが精神的な支えになっただけでなく、ワークライフバランスを保ちながら活躍する先輩との出会いが独立・開業への決意を後押ししています。
「独立・開業する際に押さえておいてほしいこと」として最初に「ネットワークづくり」を挙げている通り、これは孤立を防ぎ、情報を得て、新たな仕事に繋げるための生命線です。
(2)自己管理能力
自身のオーバーワークが独立のきっかけの1つであったように、健康や業務量を管理し、ワークライフバランスを保つ能力は必須です。
個人事業主は、自分が倒れると事業が停止するリスクを常に抱えています。仕事とプライベートのメリハリをつける意識が、持続可能な活動の鍵となります。
(3)課題解決能力(開拓性)
松谷さんは「困難な状況において、自ら課題を見つけて解決策を考え、行動に移せる人」を独立・開業に向いている人物像として挙げています。
これは、既存のしくみを変え、新たな挑戦を楽しむ「開拓性」ともいえるでしょう。
2.事業計画の立て方――ブレない「軸」としてのビジョン・ミッション・パッション
松谷さんは、準備段階で最も重要なことの1つとして「独立・開業する趣旨を明確にすること」を挙げています。これが事業計画の根幹をなす「ビジョン・ミッション・パッション」の明確化に他なりません。
松谷さんの事業の軸は、以下の3点に集約されます。
パッション(情熱)
「なぜ、自分はこの事業をやりたいのか?」という根源的な問いへの答えであり、困難を乗り越えるエネルギー源となります。松谷さんの場合、「その人らしい生活とは?」という問いから生まれた「家族まるごと支援したい」という熱い想いが、まさにこのパッションにあたります。
ビジョン(実現したい社会)
パッションを社会に向け、未来の理想像として描いたものです。「この事業を通じて、どんな世界を実現したいのか?」を示します。組織のしがらみなく、利用者を含めた「家族まるごと」の権利が擁護される社会が具体化されています。
ミッション(自身の役割)
壮大なビジョンを実現するために、「自分(自社)が具体的に何をすべきか」という行動指針です。松谷さんは、「公平な立場で、分野や地域を横断した支援を行い、社会を動かすソーシャルアクションにつなげる」ことを自らのミッションと定めています。
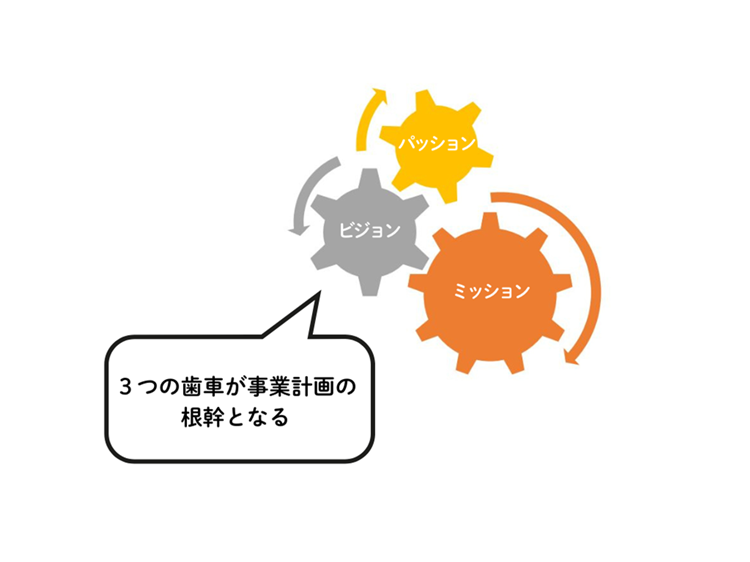
3.事務所や設備の準備――「形あるもの」と「無形のしくみ」
最後に、事業の「器」となる事務所や設備の準備です。
事務所形態(形あるもの)
松谷さんは「スピード感」と「公平性」を重視し、「個人事務所」を選択しました。
これは、法人化に伴う事務手続きや制約を避け、個人の専門職として柔軟に活動したいというビジョンに合致した選択です。
独立・開業を考える際は、自身のビジョンや活動内容に合わせて、法人格(NPO、株式会社等)が必要か、個人事業主で十分かを慎重に検討する必要があります。
ミッション(自身の役割)
壮大なビジョンを実現するために、「自分(自社)が具体的に何をすべきか」という行動指針です。松谷さんは、「公平な立場で、分野や地域を横断した支援を行い、社会を動かすソーシャルアクションにつなげる」ことを自らのミッションと定めています。
これらは個人事業主の脆弱性を補い、クライエントからの信頼を維持・向上させるために不可欠といえるでしょう。これらの準備に加え、松谷さんが最後に強調する「家族の理解と協力」という基盤があってこそ、独立・開業という挑戦が実りあるものになるといえるでしょう。
著者紹介
小川 幸裕(おがわ ゆきひろ)
弘前学院大学社会福祉学部 教授/社会福祉士。
独立・開業したソーシャルワーカーを対象とした調査に基づき、ソーシャルワーク実践の構造や要因を分析。研究活動の傍ら、地域の活動をとおして地域の社会福祉連携の推進に貢献し理論と実践の架け橋となる活動に取り組む。
横田 一也(よこた かずや)
株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ 代表/認定社会福祉士(地域社会・多文化分野)・介護福祉士・介護支援専門員・大阪府人権擁護士等。 障害者・高齢者福祉分野を中心に支援経験を重ね、2012年に独立。ソーシャルワーカーとして子どもから障がい者・高齢者まで幅広い支援活動を行う。成年後見人等の受任のほか、スクールソーシャルワーカーや大学等講師を務める。訪問ケア・人材育成事業で地域に根ざした活動を展開。
