独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.4 独立・開業の意義と心構え
2025/09/26
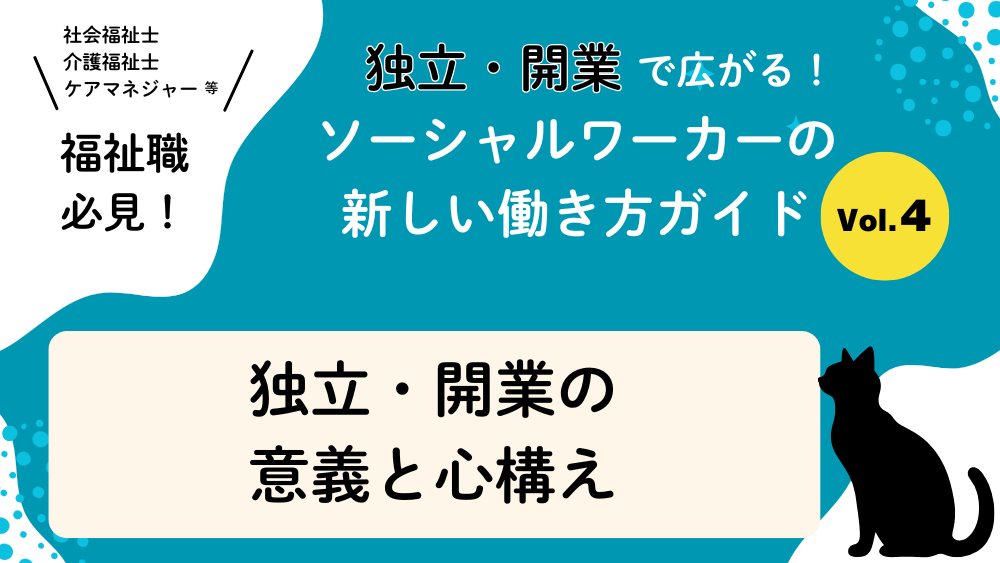
福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!
この連載は、介護や福祉の仕事に熱い想いをもち、これから資格取得を目指している方、あるいはすでに資格をもっていて、さらなるスキルアップを考えている方に向けてお届けします。
Vol.3でご紹介した、福祉現場の法人職員からソーシャルワーカーとして独立・開業の道を選んだ横田さんのケースから、独立・開業に必要な心構えや視点を整理します。
著者
小川 幸裕(弘前学院大学社会福祉学部教授)
松谷 恵子(まつたに社会福祉士事務所所長)
Vol.3でご紹介した社会福祉士事務所カラーサの横田さんのケースは、社会福祉専門職が独立・開業する際のリアルな軌跡と想いが込められていました。今回はその内容をもとに、
① なぜ独立・開業するのか
② 独立・開業のメリットとデメリット
③ 社会的課題解決としての事業
という3つの視点から、その意義と心構えを深掘りして解説します。
①なぜ独立・開業するのか? ―組織の限界と自己の可能性の追求
横田さんが独立・開業に至った原動力は、大きく2つに集約されます。1つは「組織の枠組みに対する限界意識」、もう1つは「自身のキャリアと可能性を広げたいという強い想い」です。
13年間の法人職員経験で感じた「自分の理想とする仕事を実現する難しさ」は、多くのソーシャルワーカーが一度は抱く葛藤かもしれません。組織には組織の理念やルールがあり、それが安定したサービスを提供する基盤である一方、個々の専門職の柔軟な発想や挑戦を制約してしまう側面もあります。
このようななか、横田さんは、「もっと自分の力を活かし、仕事の幅を広げ、キャリアを高めたい」という極めて前向きなエネルギーを核に、働きながら大学で社会福祉士の資格取得にむけ挑戦し、「独立・開業」という選択を実現していきます。
つまり、福祉分野における独立・開業は、現状からの逃避ではなく、「自分が理想とする支援を、自らの責任と裁量において実現したい」という、専門職としての成熟と自己実現への強い意志の表れであるといえるでしょう。
②独立・開業のメリット・デメリット ―「裁量」と「責任」は表裏一体
独立・開業の魅力と厳しさは、表裏一体の関係にあります。横田さんの言葉を借りれば、それは「自分の決断がすべて結果に反映される」という一点にあります。
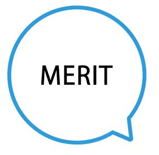
最大のメリットは、横田さんが語るように「自分自身の裁量を大きくもてる」ことです。支援内容やクライエントと向き合う時間、働き方までを自分でデザインできるため、専門職としての倫理観に基づいた丁寧な支援を追求できます。また、「働いた分だけ収入にもつながる」という点は、自身の専門性が正当に評価されるという強いやりがいを生み出します。これは、組織の給与体系のなかでは得難い感覚です。
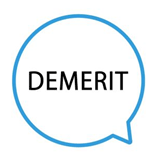
その一方で、自由な裁量には「経営者としての重い責任」が伴います。横田さんが「最初に直面した大きな壁」と語るように、優れた福祉専門職が、必ずしも優れた経営者であるとは限りません。「理念」という熱い想いと、「経営」という冷静な視点の両輪を回し続けなければ、事業は立ち行かなくなります。特に世帯主である横田さんにとって、「収入の安定」は避けて通れない課題でした。組織という庇護を離れ、たった1人で事業と生活の全責任を負う覚悟が求められます。
③社会的課題解決の「手段」としての事業 ―独立・開業のその先へ
横田さんのケースで最も本質的なのは、独立・開業を「社会的課題を解決するための手段」と捉えている点です。これは、独立・開業を「目的化」しないための極めて重要な視点です。
横田さんは、法人職員時代の現場経験から「制度の狭間で取り残されがちな人たち」「支援が届きにくい家庭」「地域からの孤立」といった具体的な社会的課題を目の当たりにしてきました。そして、その課題に対して、組織の枠組みでは届かない支援を、自らの事業を通して届けようとしています。
居宅介護支援、成年後見活動、人材育成、訪問ケア、スクールソーシャルワーカーといった事業展開は、一見多岐にわたるように見えますが、「現場で見える課題に応える」という一貫した目的意識でつながっています。
つまり、横田さんにとっての独立・開業とは、単に自由に働くことではなく、自らの専門性とネットワークを最大限に活かし、組織では対応しきれない地域社会の狭間を埋めていくための挑戦といえます。
横田さんのケースから、独立・開業が「自分がなぜこの仕事をしているのか」という根源的な問いと向き合い続ける営みであることがわかります。
これから独立・開業を目指す方は、「信念」「責任」「ネットワーク」「学び続ける姿勢」という彼の言葉を胸に、自らが解決したい社会的課題は何かを問い直すことから始めてみてはいかがでしょうか。
著者紹介
小川 幸裕(おがわ ゆきひろ)
弘前学院大学社会福祉学部 教授/社会福祉士。
独立・開業したソーシャルワーカーを対象とした調査に基づき、ソーシャルワーク実践の構造や要因を分析。研究活動の傍ら、地域の活動をとおして地域の社会福祉連携の推進に貢献し理論と実践の架け橋となる活動に取り組む。
松谷 恵子(まつたに けいこ)
まつたに社会福祉士事務所所長/認定社会福祉士(児童・家庭分野)・介護支援専門員。
高齢者の通所介護・グループホームの勤務を経て、2011年10月まつたに社会福祉士事務所開設。福祉全般の相談業務、第三者委員やオンブズマン、成年後見人等の受任、スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー、非常勤講師・研修講師等を行う。
