独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.3 【独立・開業を選んだ人①】横田 一也さん(社会福祉士事務所カラーサ)の場合
2025/09/19
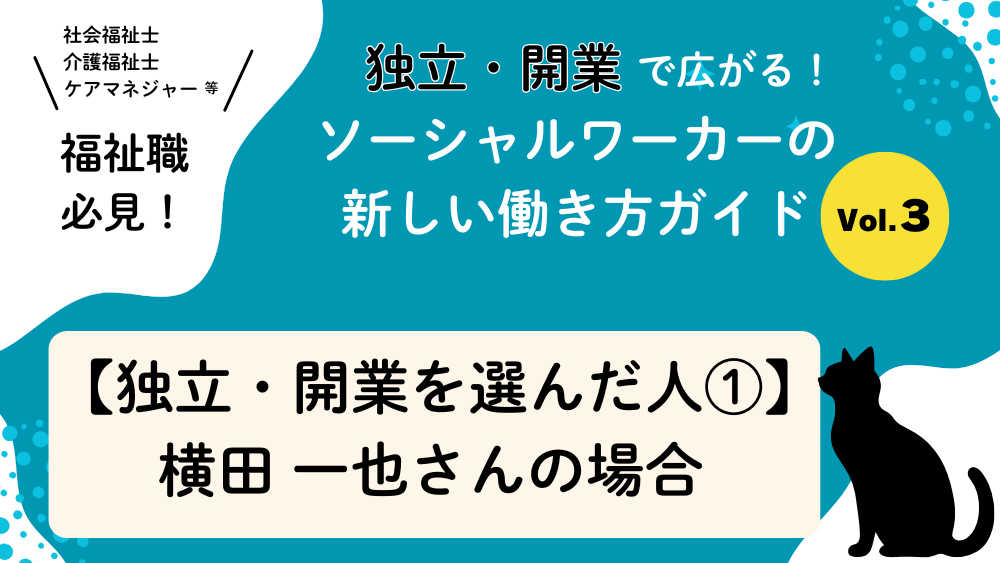
福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!
この連載は、介護や福祉の仕事に熱い想いをもち、これから資格取得を目指している方、あるいはすでに資格をもっていて、さらなるスキルアップを考えている方に向けてお届けします。
ここまではソーシャルワーカーの「独立・開業」について、その意味を整理しました。
今回は、福祉現場の職員からソーシャルワーカーとして独立・開業の道を選んだ横田さんへのQ&Aを通じて、独立・開業に必要な心構えや視点をお伝えします。
横田さんのプロフィール

株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ 代表/認定社会福祉士(地域社会・多文化分野)・介護福祉士・介護支援専門員・大阪府人権擁護士等。
障害者・高齢者福祉分野を中心に支援経験を重ね、2012年に独立。ソーシャルワーカーとして子どもから障がい者・高齢者まで幅広い支援活動を行う。成年後見人等の受任のほか、スクールソーシャルワーカーや大学等講師を務める。訪問ケア・人材育成事業で地域に根ざした活動を展開。
Q1 「独立・開業」の原動力となったものは?
20歳で介護福祉士を取得してから、障がい福祉や高齢者福祉の分野で13年間、法人職員として勤務しました。
ケアマネジャーの資格を取得後は、居宅介護支援事業所でケアマネジャーとしての経験も積みましたが、組織の枠内では、どうしても自分の理想とする支援が実現できないというもどかしさも感じていました。「このままでいいのだろうか」「もっと自分の力を活かしたい」という思いが強くなったことがきっかけで、独立・開業を考えるようになりました。
また、自分自身のキャリア形成において、長く仕事をしていくためにも、多くの選択肢をもてるように資格を取得して広げていきたい、という考えもありました。仕事の幅を広げ、さらにキャリアを高めたい、自分の想いを形にし、柔軟な発想で支援を届けたい――そんな気持ちが、独立・開業という選択肢へ私を導いていきました。
それらの想いが強くなり、働きながら大学に通い社会福祉士を取得しました。この挑戦が、「独立・開業」という選択肢へと私を後押ししました。
Q2 独立・開業までのプロセスは?
独立・開業を具体的に考えたとき、「自分ができること」から始めようと決めました。これまでの福祉実践経験と、ケアマネジャーとしての実績を活かし、法人を設立して居宅介護支援事業所を開設することからスタートしました。
また、社会福祉士の資格取得後にネットワークの広がりを求め職能団体に加入していた影響で、成年後見業務にも関心をもつようになり、独立・開業後は成年後見人としての活動も行いました。
それ以降、法人としては社会資源開発となる人材育成事業(さまざまな資格養成研修の運営)や訪問ケア事業(介護保険・障がい福祉制度の事業と自費ヘルパー派遣事業)に取り組み、自分自身では大学等の講師を務めるほか、スクールソーシャルワーカーとしての実践にも取り組みました。
Q3 独立・開業して良かったことは?
法人職員時代と比べ、仕事に対して自分自身の裁量をもてるようになったことは大きな変化です。福祉職としての倫理を大切にしながら、クライエントと丁寧に向き合える環境を自ら整えられるので、これまでの経験を活かす絶好の機会と感じます。
また、時間の使い方も自分でマネジメントできるため、働いた分だけ収入にもつながり、やりがいも強く感じています。自分の性格にも合っていたと、今では実感しています。
Q4 独立・開業して大変だったことは?
組織から離れたことで、独立性とともに責任の重さも感じました。なかでも、経営の視点が未熟だったことが、最初に直面した大きな壁でした。専門職としての経験はあっても、経営者としての視点や判断力はゼロからのスタート。
特に私は世帯主という立場でもあったため、収入の安定を確保することが重要課題でした。「理念」と「経営」という両輪のバランスをどう取るかが、今も課題であり、日々の学びでもあります。
Q5 独立・開業は、どんな人におすすめしたい?
自分の信念を持ち、それを形にしていきたい人にこそおすすめしたいです。組織のなかでのやりがいとはまた異なり、自分の決断がすべて結果に反映されるのが独立・開業の良さであり、厳しさでもあります。
福祉の現場で「もっとこうしたい」と感じた経験がある人は、独立・開業という選択肢によって、その思いを実現できる可能性が広がります。
Q6 独立・開業を考える際に押さえておいてほしいことは?
独立・開業の最大のメリットは、自分の裁量で支援を組み立てられることです。クライエント1人ひとりと丁寧に向き合える環境を、自分自身で整えることができるのは、大きな喜びです。時間の使い方を自分でコントロールでき、努力した分が収入や成果に直結する点もやりがいにつながります。
反面、当然ながら経営者としての責任も大きく、特に私のように家族を支える立場にとっては、安定した収入の確保が切実な課題でした。理念があっても、経営の視点がなければ継続できません。福祉専門職としてのスキルに加え、経営知識やネットワーク構築の重要性を実感しています。

そして何より、私にとっての独立・開業の挑戦は「社会的課題を解決するための手段」でもあります。制度の狭間で取り残されがちな人たち、支援が届きにくい家庭、地域からの孤立など、現場にいて見えてくる課題は多岐にわたります。そうした課題に対して、自らの専門性と行動力をもって応えていく――その手段として「独立・開業」があると考えています。組織に属することでは実現できなかった支援の形を、地域のなかで自分らしく展開する。その実践が、社会全体の福祉力を高める一助になると信じています。
独立・開業とは、単に「自由に働ける」ことではありません。それは、「自分がなぜこの仕事をしているのか」を見つめ直し、「どう社会と向き合っていくか」を考え続ける営みです。信念と責任をもち、孤立せず、ネットワークを保ち、学び続ける姿勢が、継続的な事業運営には欠かせません。もし今、「もっとこうしたい」と感じている人がいれば、その思いこそが、独立・開業への第一歩になるかもしれません。
