対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第9回 ホウレンソウの場におけるコーチング ~報告編~
2025/07/24
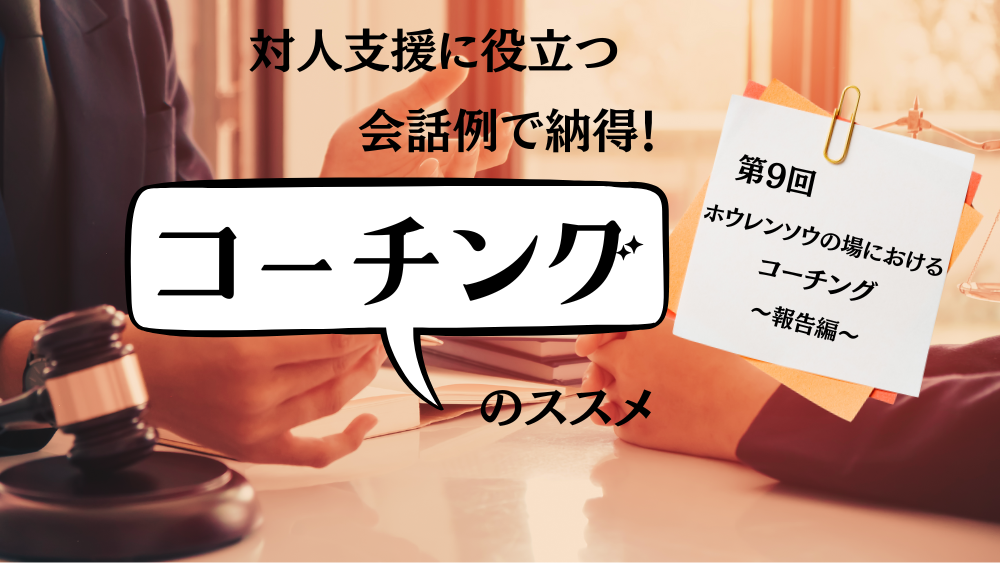
ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。
この記事の監修者
眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)
1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。
ホウレンソウは職場コミュニケ―ションの核
職場内でのチームづくりの基本となるのが活発なコミュニケーションですが、「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」の徹底はその核となるものです。ホウレンソウによる意思疎通がうまくいかないと、ロスタイムやストレス等でお互いの思い違いやわだかまりが発生し、仕事の生産性が低下するおそれがあります。
ホウレンソウの実態把握
まずは、所属する職場の実態を把握しましょう。下記の項目は、ホウレンソウが徹底されていない職場の典型的な特徴です。5つ以上該当するものがあれば要注意で、8つ以上あれば赤信号です。
□ 1上司(管理者)と部下の意思疎通がうまくいかない
□ 2 スタッフ間の横の意思疎通がうまくいかない
□ 3 仕事の効率が悪く、残業が多い
□ 4 トラブルや苦情が続出している
□ 5 事業所の業績が悪化している
□ 6 事業所全体に活力がない
□ 7 スタッフの仕事へのモチベーションが低い
□ 8 不平不満や陰口悪口が横行している
□ 9 スタッフが定着しない
ホウレンソウ強化のためのコーチング
ホウレンソウのスキルを強化するためには、最初に正しいホウレンソウを教え、その後の実践のなかでコーチングを通じて成果が出るまでフォローしていくことが必要です。
ホウレンソウの知識やノウハウが何もない人からは「問いかけて引き出す」ことはできません。最初にそれらの正しい情報を教えて相手にインプットしておけば、相手のなかに「答え」ができるのでコーチングが活きます。この段取りが成果の決め手です。
職場で正しいホウレンソウが徹底されると、意思疎通が活発になるだけでなく、お互いに認め合うようになります。仕事がスムーズに運び、ミスや事故がなくなり、仕事の効率が上がります。
ホウレンソウの“ホウ”適切な「報告」について
“報告”の定義…上司からの指示や命令に対して、部下が経過や結果を知らせること
報告を行うのは、部下から上司へ、もしくは後輩から先輩へという流れが一般的です。上司から部下へ行うのは報告ではなく連絡です。
“報告”の目的…現状を正確に認知してもらうこと
報告が重要な理由は、上司やリーダー等の責任者が部下の業務を正しい方向へ舵取りするために、現状をタイムリーかつ正確に知る必要があるためです。報告が遅いと決断が鈍りトラブルや失敗の原因になります。
“報告”の内容…今どのような状況か、過去から現在に至る経緯とその結果、次に向かうべき方向性、そして自分の考えや意志を伝えること
報告の内容によりますが、途中経過なら現状、最終段階なら結果、次にそこに至る経過を伝えます。今後の方向性の見込みや予測は相手に求められたときに私見として述べます。
“報告”のコツ…結論から理由の順番で話すこと
結論の事実を簡潔に話すことが大事です。時系列や数字等でその事実関係を伝えると相手にわかりやすく伝わります。
報告でありがちな失敗例
報告では、自分の考えや感想は伝えても構いませんが、冒頭で述べるのはNGです。報告の終盤で、相手に求められたときに答えるのが適切なタイミングです。
最初に伝えると相手は混乱します。その考えに至った理由や経過が相手にわからないからです。相手は仕事の「コト」が知りたいのに、報告者の「ヒト」が前面に出てきてしまうと、印象や評価もよくありません。そのために、話の途中に「結論は何?」と要求されてしまうわけです。
【報告のNG例】
|
ケアマネA : ご利用者のCさんは私を信頼していないようですし、相性も合いません。もう無理です。かかわりたく…… 管理者B : ちょっと待って。あなたは何が言いたいの? ケアマネA : えっ、昨日の苦情解決会議でCさんにもっと共感的に傾聴するように進言されたので…… 管理者B : 報告ならAさんの意見より先に苦情対応の結果から話してくれないと、よくわかりません。 ケアマネA : すみません |
NG例では、ケアマネAが報告の冒頭で自分の感想を述べてしまっています。これでは、報告を受けた人にはそもそも何の話なのかが伝わりません。
適切な報告に変えるコーチング
一方で、コーチングが活用できる管理者なら、「まとめて話しなさい」と威圧的な物の言い方はしません。事前にホウレンソウの基本を職場内で全員が学習していることが前提ですが、双方向のやりとりのなかで部下が適切な報告ができるように支援します。
【報告のNG例】
|
ケアマネA : ご利用者のCさんは私を信頼していないようですし、相性も合いません。もう無理です。かかわりたくありません。 管理者B : 何か穏やかな感じではないですね。Aさんは私にホウレンソウのなかの何をしようとしていますか?? ケアマネA : あっ、昨日の苦情解決会議で取り上げていただいたCさんの報告です。 管理者B : わかりました。それでしたら、報告のコツは何か覚えていますか? ケアマネA : そうですね、確か“結論から理由の順番で話すこと”ですよね。すっかり興奮して意識できていませんでした。 管理者B : AさんがCさんにかかわりたくないと思うようになった理由も含めて、会議後から今までの間に何があったのか教えてくれますか? |
OK例では、管理者BはケアマネAが報告の場面で先に感想を述べてしまっている状況に対しても、傾聴的な姿勢で接しながら、正しい報告の仕方へと導いています。コーチングを活用して、事前に学んだ正しい報告の仕方を引き出すことが、適切な報告を生み出すポイントです。
