対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第10回 ホウレンソウの場におけるコーチング ~連絡・相談編~
2025/08/07
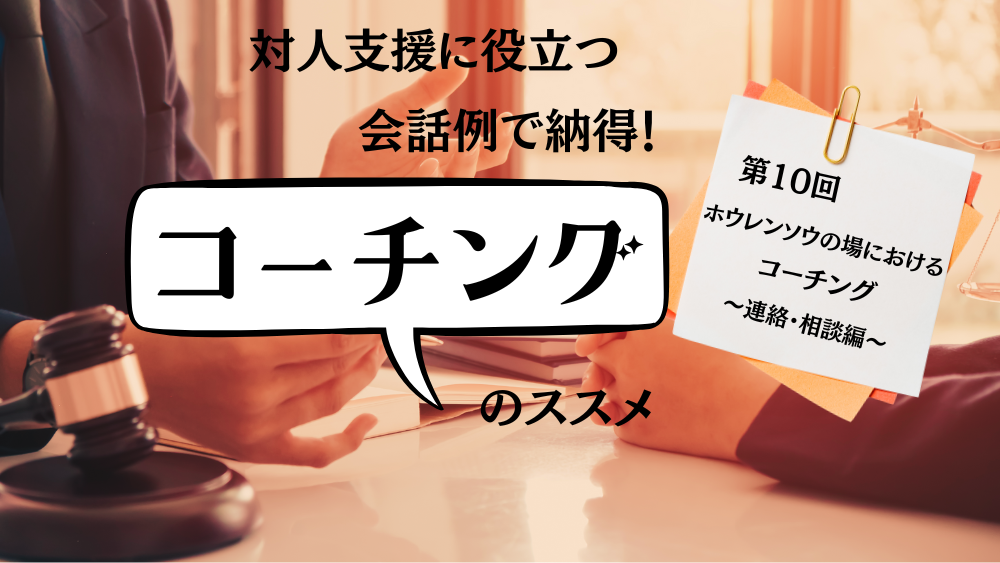
ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。
この記事の監修者
眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)
1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。
前回(第9回「ホウレンソウの場におけるコーチング~報告編~」)は、ホウレンソウの「報告」について、適切なポイントや正しい「報告」の仕方を学びました。今回はホウレンソウにおける「連絡」「相談」に焦点を当てて学んでいきましょう。
ホウレンソウの“レン”適切な「連絡」について
“連絡”の定義…簡単な情報を関係者に知らせること
上司や部下等の立場は関係なく、誰もが発信する側にもなり、受信する側にもなります。”連絡”の方法は対面のほか、電話やFAX、電子メールや回覧板などがあります。
“連絡”の目的…事実の周知
”連絡”とは組織内の意思疎通で、仕事における重要事項や変更点等の変化を共有することです。
“連絡”の内容…ありのままの事実を関係者に知らせること
”連絡”では、引継事項、スケジュール関連、トラブルなど、業務を遂行するうえで重要な情報を知らせます。
“連絡”のコツ…周知したい事実に自分の個人的見解や解釈、憶測を加えないこと
報告と同じで、”連絡”では結論から理由の順番で話し、事実を時系列で簡潔に伝えることが大事です。
連絡でありがちな失敗例
連絡でありがちな過ちは、事実に個人的解釈を加えてしまうことです。そうなると、話に尾ひれや背びれがついて内容が複雑化してしまいます。ひどいときには、まるで伝言ゲームのように発信者の情報が最後の人にはまったく異なった情報になることもあります。また、「あれ、これ、それ」の指示代名詞での表現が誤解を生むこともしばしばあるので要注意です。
【連絡のNG例】
|
ケアマネA : 人事評価シート提出日が今月末の30日から28日に変更になったって聞いた? ケアマネB : まだ聞いていなかったから、ありがとう。なぜ繰り上がったの? ケアマネA : きっと賞与支給日を早くするからじゃない? ケアマネB : ボーナスが早く出るのはうれしいね。 ケアマネA : 明日出勤するCさんにも伝えておいてね。 ~翌日~ ケアマネB : Cさん、賞与支給日が2日早くなるからシートも早く提出するようにお願いします。 |
NG例では、「賞与支給日が早まる」というケアマネA・Bの個人的解釈を、ケアマネCにあたかも決定事項かのように伝えています。これでは、誤った情報が周囲にどんどん広まっていく可能性があります。
適切な連絡に変えるコーチング
正確に周知するには文書が確実ですが、口頭で情報が回ってくることはよくあることです。個人的解釈を加えないことはもちろん、コーチングを活用することで情報が入れ替わることを防ぎ、次に連絡する人に正確な情報が届くように支援します。
【連絡のOK例】
|
ケアマネA : 人事評価シート提出日が今月末の30日から28日に変更になったって聞いた? ケアマネB : まだ聞いていなかったから、ありがとう。なぜ繰り上がったの? ケアマネA : いろいろな噂は飛び交っているけど、本当のところはわからないな。明日出勤するCさんにも提出日が変更した旨を正確に伝えておいてね 。 ケアマネB : わかった。 ケアマネA : Bさん、確認だけど、連絡の内容を今私に復唱してくれるかな? ケアマネB : いいよ。人事評価シート提出日が今月末の30日から28日に変更になりました。だよね? |
OK例では、情報に個人的解釈を加えず(事実をそのまま伝え)、コーチングで内容の正確性を確認するひと手間を加えています。そうすることで、他の人に正しい情報を届けることができます。
ホウレンソウの“ソウ”適切な「相談」について
“相談”の定義…判断に迷うときに、上司や先輩、同僚等に参考となる意見を聴き、アドバイスをもらうこと
経験が少ないと、自分がもつ判断材料だけでは容易に決断できないことがあります。足りない要素を補うために、”相談”によって経験や知識の豊富な人の意見を求めます。
“相談”の目的…決断しかねている状況において、判断材料を増やすこと
”相談”によって新しいアイデアや解決方法を見つけ疑問や問題を解決します。業務の効率化や労力の削減にも効果が期待できます。
“相談”の内容…まずは何に迷っているのか、何を決断するのか、正確な事実を相談相手に伝えること
どの選択肢を選ぶかについて今の自分の考えを述べることです。最終的に、相談後いつどのように決断するつもりか、その予定も伝えることでより役立つ助言が得られます。
“相談”のコツ…事前に相談内容と自分なりの考えをまとめておくこと
今までの経緯や必要な情報を忘れないように整理して、的確なアドバイスをもらえる備えをすることです。誤った情報や、不都合な事実について意図的に隠ぺいした情報を伝えてしまうと、役に立つアドバイスを受けるのは難しくなります。小さなミスでも隠し事は一切してはなりません。素直な姿勢で臨むことが基本です。
相談でありがちな失敗例
相談で誤りがちな認識が、問題解決を相談相手に全面的に委ねてしまうことです。問題を解決するのは当事者である自分自身です。解決策を自ら考えることなく、壁に直面したら自動的に上司や管理者の下に行き、指示・命令をもらうことは相談ではありません。本来は相談の前に問題を整理し、問題解決の選択肢をいくつか用意し、自分が考えるベストな選択肢を仮決めした状態で相談をするのが筋です。
【相談のNG例】
|
ケアマネA : Bさん、担当ケースのことで相談したいのですがよろしいですか? 管理者B : いいですよ。どうしましたか? ケアマネA : 担当利用者のCさんが主治医の診察に行かないと言って困っています。認定更新の際の意見書も書いてもらえないし、必要な薬を出してもらうこともままならない状況です。どうしたら受診してもらえるでしょうか。 管理者B : Cさんの家族や身寄りの方にお願いすることがまず大事ですね。主治医に往診してもらうことも解決方法の一つです。 |
NG例では、ケアマネAに考えさせることなく、すぐに管理者Bが解決策を提示しています。これでは、ケアマネAの考える力を奪いかねません。
適切な相談に変えるコーチング
人材育成を常に念頭においている管理者なら、相談されたからといって解決策を安易に答えません。部下の主体性が成長するビッグチャンスだからです。あくまでもこの問題を解決するのは部下で、管理者は問題解決の考え方やヒントを提示する立場にとどまります。コーチング手法を活用して、部下が適切な相談ができるように支援します。
【相談のOK例】
|
ケアマネA : Bさん、担当ケースのことで相談したいのですがよろしいですか? 管理者B : いいですよ。どうしましたか? ケアマネA : 担当利用者のCさんが主治医の診察に行かないと言って困っています。認定更新の際の意見書も書いてもらえないし、必要な薬を出してもらうこともままならない状況です。どうしたら受診してもらえるでしょうか。 管理者B : それは困りましたね。私が答える前にいくつか質問していいですか? ケアマネA : わかりました。 管理者B : Cさんはなぜ受診を拒むのでしょうか? ケアマネA : 元々Cさんは医者嫌いです(中略) 管理者B : この問題を解決するためにAさんが対処したことは何ですか? またほかにどのような解決方法を検討しましたか? |
OK例では、コーチングを活用してケアマネAが主体となって問題を解決できるよう支援しています。この方法であれば、ケアマネAも自ら考えて解決策を見出すことができるでしょう。
正しいホウレンソウの活用でチームの基盤を強化しよう
社会人の基礎として大切な「ホウレンソウ」ですが、意外と誤った方法で実践している方は多いのではないでしょうか。正しいホウレンソウを習得し、仲間に共有することはチーム内の連携をスムーズにし、基盤を強めることにつながります。また、コーチングを活用することは人材育成にも役立ちます。
