知ってるつもりの認知症ケア 第12回 動き出したときが絶好のタイミング?
2025/07/25
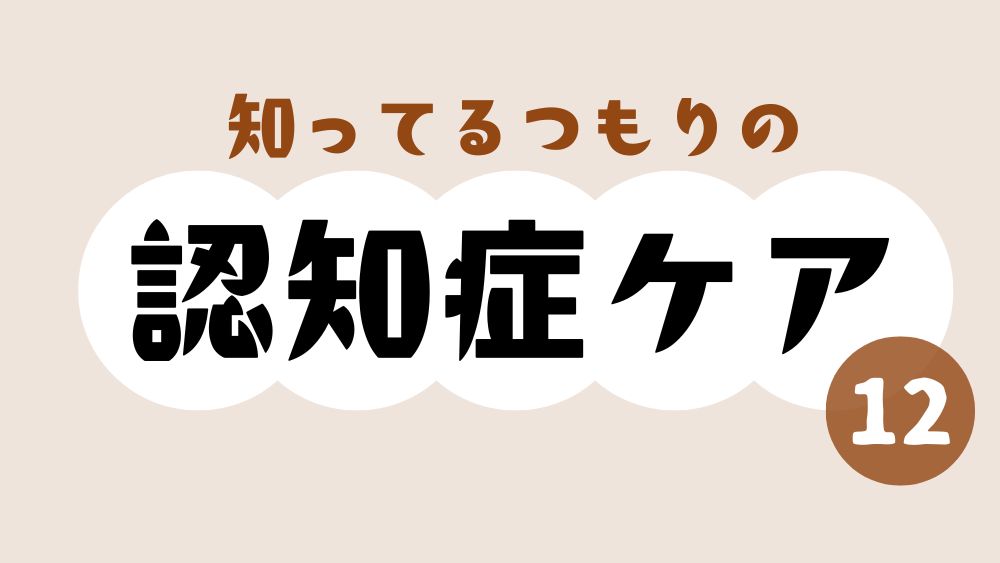
川畑智

認知症の人に接するときには「認知症の人の見ている世界」を正しく理解することが大切です。それによって適切で質の高いケアを提供でき、利用者は認知症になっても安心して生活することができます。
……とはいっても、さまざまな仕事をこなす日々の業務のなかでは、理想どおりのケアを行うことは一苦労です。
この連載では、認知症ケアの第一人者である理学療法士の川畑智さんのもとに、悩み多き介護職の方々が訪れ、ともに「現場のリアルな困りごとを理想に近づけるためのヒント」を模索していきます。
理想論ではなく、認知症ケアのリアルなつまずきにスポットを当ててみたいと思います。
川畑 : 今回も引き続き、認知症の人の徘徊について考えていきましょうか。
Dさん : よろしくお願いします!
川畑 : 前回、窓から外を見ていて外に出てしまった利用者さんのお話をされていたかと思います。施設は自由に出入りができる環境だったんですね?
Dさん : そうですね。ただ、現在はエレベーターにセンサーが設置されていて、ドアが開くと音が鳴って知らせるシステムになっています。
川畑 : なるほど。セキュリティの点からも、施錠をしている施設は多いと思います。出入りに暗証番号が必要であったり、開錠ボタンを押さないとドアが開かないようにしていたり。ただ、そのような環境になっていると、外に出たいという思いがある認知症の人はどうするかというと、開いている窓を探すんですね。
Dさん : どこかから出られるんじゃないかと探して、出ようとするんですね。
川畑 : そうなんです。自分の部屋の窓をはじめ、勝手口や1階フロアの窓など、開いているところを探していく。単なる一人歩きや迷い歩きのように見えますが、本人にとっては目的が確実にある。その目的が叶わないから、ずっと歩いてしまう。
Dさん : だからこそ、その背景を考えることが大事だ、ということでしたね。ただ、その背景がわかっても難しい場合はどうすればいいんでしょうか。
川畑 : ぜひ一緒に考えていきましょう。徘徊されている方に対して、まずはどんなふうに声かけしますか?
Dさん : んー、そうですね。とりあえず「どうしましたか?」「どこに行くんですか?」と声をかけます。
川畑 : ですね。私もそうするかなと思います。でも、実はこれって、本当に答えを知りたいわけではないってことはありませんか。本当は「お部屋はこっちですよ」なんて誘導したいのが本心で、ただ聞いていることも多いんじゃないでしょうか。
Dさん : まあ、それはそうかもしれません。
川畑 : 徘徊を止めたいとき、どうすればいいか。これは一つですが、お茶を出してみると意外に効果的なんですよ。ただ出すだけではなくて、「お茶を淹れたいんですけど、手伝ってもらえませんか?」と声をかけて、お茶を淹れてもらうとなおよいです。今の高齢者の世代であれば、特に女性の方にとっては、お茶を淹れることは普段からよくやっていたことです。徘徊があるのは、何かに興味関心があるというサインですから、そのベクトルをこちら側に向けるわけですね。
Dさん : なるほど! 止めようとするのとは逆の発想ですね。
川畑 : このときに「手伝ってください」と言って、「今は忙しいから」と断られてしまうかもしれません。だから「助けてください」と言うのがいいんですよ。
Dさん : 「助けてほしい」ということであれば、「今、するしかないか」という気持ちになりそうです。
川畑 : そうなんです。だからタイミングが重要ということですね。徘徊とは別のバージョンで考えてみると、わかりやすいかもしれません。よく利用者さんに、洗濯物をたたんでもらおうかという場合があると思います。どんなときにお願いしていますか?
Dさん : そうですね。座っていて、何もすることがなさそうだったら「洗濯物でもたたみましょう」と声かけする、みたいな。なので、いすに座っているときに頼むことが多いと思います。
川畑 : ですよね。今の話で言うと、これも実は、狙い目は動き始めたタイミングなんです。興味関心がどこかに向いた瞬間を見つけたら、そのベクトルを人助けのほうに向けてみる。「○○さん、あそこに洗濯物が山積みになっていて、もしよければ一緒にやってほしいんです。一人じゃできないので、助けてもらっていいですか?」なんて声をかければ、快くサポートしてくれると思います。徘徊をいったん休止してもらって、人助けの方向にもっていく。
Dさん : なるほど。でも、認知症のある人にお茶を淹れさせるのって、施設からしたら嫌がられそうですよね。熱湯を使うこともあるでしょうし……。
川畑 : もし施設側が「お湯なんて使わせるなんて危ない!」と言うのであれば、実際にポットを持ってきて、本当に危ないのかどうかを見てもらうといいと思います。実は危なくないんですよ。認知症があっても「お茶は熱い」くらいはわかっていますからね。
Dさん : それまでの生活でお茶を淹れることに慣れ親しんでいれば、なおのことですよね。
川畑 : ですね。ただ、段取りで苦戦することはあるでしょうね。たとえば、ポットの蓋を開けているときに、湯気が立っているお湯にお茶の葉をドバっと入れちゃう方もいます。ちょっと変わったやり方ですが、これはこれでちゃんとお茶はできます(笑)。後から洗えば済む話ですからね。
Dさん : たしかにそれくらいであれば命にかかわることでもないし、濃いお茶が飲めると考えれば、好きな人はいるかもしれないです。
川畑 : むしろいい経験にもなると思います。まとめると、徘徊を止めて人助けの方向に興味関心を向けてもらうことが第一の目的です。そして、第二の目的は、認知症の人の自立支援です。「お茶を淹れる」「洗濯物をたたむ」ということから社会とのつながりになる。それに、お茶を飲むとなんだかホッとしますからね。
Dさん : 私も仕事中、一息つきたくなったらお茶を飲みたくなります。利用者と一緒に飲んじゃおうかな(笑)。
川畑 : それはナイスアイデアです! まさにこれが3つ目の目的で、淹れたお茶を職員が一緒に飲むことで、よい効果を得るというものですね。
Dさん : あ! 本当に飲んじゃっていいんですね。
川畑 : そうなんですよ。業務中にイライラしてしまう職員ってどんな職場にもいると思うので、少し余裕があるときは、その人も呼んで一緒にお茶タイムにする。お茶の時間を業務の中に追加してもらうと、意外とうまいこといくと思います。
Dさん : 意識して「お茶の時間にしよう」としてみるのはありかもです。
川畑 : ですね。実はこれ、私のアイデアではなくて、実際にやっている施設があるんです。施設長が現場をぐるっと見渡して、イライラしてる職員を見つけたら、15分くらい現場の仕事から外れてもらう。そうすると気持ちをリセットできるんですよね。認知症の人がお茶を淹れて、それをイライラする職員さんと一緒に飲む。わずかな時間でもゆっくりできるし、関係性も生まれるし、そして一緒に会話をしているうちに「○○さんって、こんなことを覚えているんだ、あんなこともできるんだ」と新たな発見にもつながる。相乗効果が生まれてくるんです。
Dさん : なるほどなあ。お茶淹れ以外にも、いろいろとストックをつくっておけば、タイミングを見計らってお願いしてみるのもよさそうですね。
川畑 : ですね。そうすれば、「徘徊でやめさせようする」という発想も変わってくるでしょうね。そういえば、少し余談ですが、私がヨーロッパへ認知症ケアの視察に行った際、徘徊への対応が印象に残っています。私が視察したところでは、4時間までの徘徊は容認されていて、この時間内なら特に問題視されないそうなんです。もし4時間を超えた場合は、栄養補給のタイミングが遅れてしまったり、過度にエネルギーを消費してしまうなどの問題から、本人の体調に影響を与える可能性が高くなるので、休憩を挟むか中止を勧める、と。つまり考え方としては、歩くこと自体が悪いのではなく、歩いた後で体調が悪くなってしまうことに気を配っているわけですね。
Dさん : なるほど。考え方が明瞭でおもしろいですね。
川畑 : ですから徘徊の対策としては、位置情報を追跡できる機器を利用して安全を確保しつつ、自由に活動できる体制を整えておけばよい、ということになる。もしかすると、日本にも取り入れられていくんじゃないかなと思います。
Dさん : 環境が整っていれば、実現できそうな感じもします。すぐには難しいかもしれませんが、まずは私たちが認知症の人のことをどう捉えて、どう接するかが大事な気がします。
川畑 : まさにその通りだと思います。徘徊に困ったな、なんとか止めて解決しなくちゃ、という視点ではなくて、発想を変えてケアにあたってみてほしいと思います。
Dさん : わかりました。ありがとうございました!
川畑智さんのプロフィール
理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表
1979年宮崎県生。病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。ほかに脳活性化ツールとして、一般社団法人日本パズル協会の特別顧問に就任し、川畑式頭リハビリパズルとして木製パズルやペンシルパズルも販売。年間200回を超える講演活動のほか、メディアにも多数出演。著作に『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズなど。
