知ってるつもりの認知症ケア 第11回 徘徊にはそれぞれ事情がある?
2025/07/11
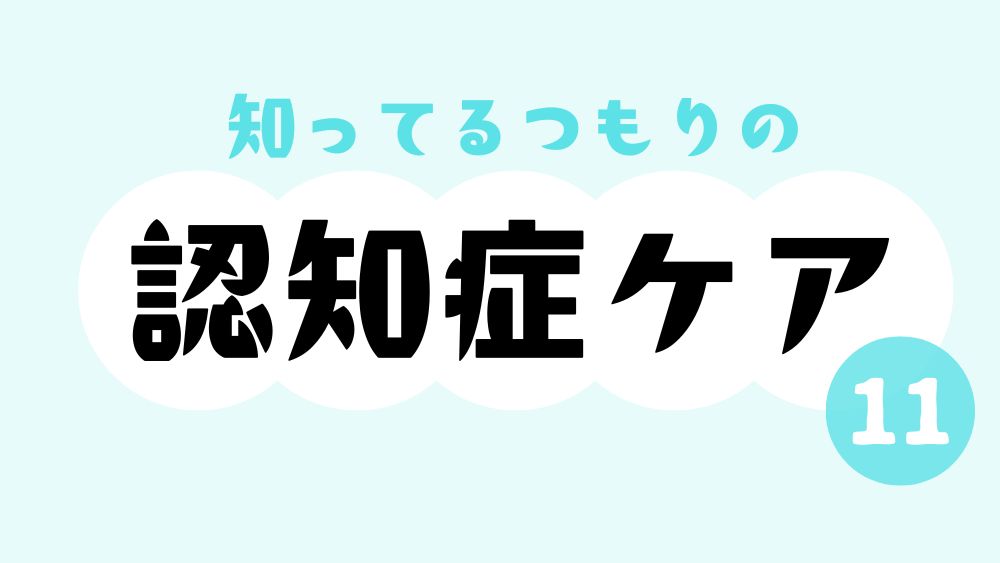
川畑智

認知症の人に接するときには「認知症の人の見ている世界」を正しく理解することが大切です。それによって適切で質の高いケアを提供でき、利用者は認知症になっても安心して生活することができます。
……とはいっても、さまざまな仕事をこなす日々の業務のなかでは、理想どおりのケアを行うことは一苦労です。
この連載では、認知症ケアの第一人者である理学療法士の川畑智さんのもとに、悩み多き介護職の方々が訪れ、ともに「現場のリアルな困りごとを理想に近づけるためのヒント」を模索していきます。
理想論ではなく、認知症ケアのリアルなつまずきにスポットを当ててみたいと思います。
Dさん : 川畑さん! 徘徊について相談がしたくてやってきました。
川畑 : よろしくお願いします。今回は徘徊ですね。これも認知症ケアでは、よく耳にするお悩みです。どんな方がいらっしゃったんでしょうか。
Dさん : はい、重度の認知症がある方なのですが、施設の外に出て、田んぼ道をあてもなく歩くんです。その行動を止めようとは思わないものの、なかなか引き返してもらうのが難しくて、やきもきしたことがありました。
川畑 : 付きっきりでいられるわけではないですもんね。すぐには気づかず、しばらくしてから「あれ、○○さんがいない!」と気づいたり、ときにそれが夜遅くだということもあるかもしれません。悲しいことに、私の経験だけでも徘徊で亡くなられたケースが3件あります。施設や病院、地域の中でもありました。ビルから転落したり、側溝に足を滑らせたり、高低差の感覚がうまくつかめなくて危険度が高まっているんですね。
Dさん : それはつらいですね……。だからこそ徘徊については心配が尽きないんです。
川畑 : 本当にそう思います。では、まずは徘徊がなぜ起こったのかを考えてみましょうか。徘徊があった利用者さんはどんな様子でしたか?
Dさん : えーと、2階の窓から外を見ながら「出たい」とおっしゃっていて、しばらくして玄関から本当に出てしまいました。どうやら外にいた人から「田んぼの手伝いをしてくれ」と言われたらしくって。それで本人は「行かなくちゃ」となったようでした。
川畑 : なるほど。外を見ていて誰かの声が聞こえてきた、と。実際に人がいたということですから、本当に声をかけられたかもしれませんね。
Dさん : でも、人はいましたが、その方は散歩されていただけなんですよね。
川畑 : なるほど。それだと幻聴の可能性もありそうですね。
Dさん : 実際に「手伝ってくれ」と言われることはなさそうですし、外に出たかったんだと思うんです。とはいえ否定するわけにもいかず……。
川畑 : 悩ましい問題です。幻聴というと、なんだか怖い感じもありますが、きちんと説明がつくことではあるんです。幻聴の根源にあるものは何か。徘徊の理由を考えるためにも、ちょっと推測してみましょう。
Dさん : 根源にあるもの、ですか。
川畑 : ええ。答えを言っちゃうと、幻聴の根源は「自分の声」なんです。わかりやすくいうと、自分が頭の中で思い浮かべている言葉といった感じでしょうか。これを「内言語」と言いますが、私たちが「お腹が空いたな」「トイレに行きたい」とわざわざ口に出さないですよね。心の中で思ったことは自分の思考のために使われて、そこで処理が終わるはずなんです。
Dさん : なるほど。でも、なぜ内言語がほかの人の言葉のように聞こえてしまうんでしょうか。
川畑 : いい質問ですね。内言語に対して、声として外に発せられるのが外言語ですが、認知症の人は内言語と外言語の処理がうまくいかない。つまり内言語が飛び火して、自分の言語野まで情報が側頭葉まで届いてしまい、実際に自分の外から聞こえたように感じるんです。
Dさん : 区別がつかなくなっているんですね。
川畑 : これが幻聴のしくみです。認知症があっても、視覚的な情報はしっかり受け取ることができますから、田んぼの近くにいる人のことが目に入ってきた。そこで、きっとあの人は「手伝ってほしい」と言っているな、と。そう思ったのは、きっと過去に田んぼの作業をした経験があるんだろうと思うんです。
Dさん : 心の声を推測することがヒントになるんですね。それがよくいわれるその人の「背景」というものでしょうか。
川畑 : まさに! 幻聴は「その人が思っていること」のサインですから、できることであれば、それを叶えてあげるために付き添ってあげることが非常に有効になります。
Dさん : なるほど。そう考えると、「外に出たい」ではなくて、誰かを助けなきゃと思ったのかな。
川畑 : そうかもしれません。そういった想像力を鍛えるためにも、私たちの目線で「どんなときに立ち上がるのか?」を考えてみることが大事です。よく「本人目線で考えましょう」「認知症の人がどんな思いをもっているか考えましょう」と言われると思いますが、その前のゼロ番目の練習として「私たちがどんなときに立ち上がっているか」を考えるのが意外と役に立ったりします。
Dさん : どんなときに……。トイレに行きたいときはもちろんですし、誰かが困っている様子を見たり、喉が乾いて飲み物を取りに行ったり、ボールペンのインクがなくなって新しいものを探しにいったり、なんかが思いつきました。
川畑 : いいですね。自分のことなら理由を考えられますよね。実はここに私たちと認知症の人たちとの共通項目がたくさんあるんです。意外に思われるかもしれませんが、認知症の人も自分のために立ち上がったり、歩いているわけではないかもしれない、ということです。先ほど「誰かが困っているとき」とおっしゃったように、「あの人が大変そうだから手伝おうと思って」と立ち上がる人もいるかもしれません。
Dさん : そうなると「徘徊」と一括りに呼ぶのはためらいますね。
川畑 : 認知症の人は意外と職員の様子を見ていて、まわりで職員の行き来が激しいと、「忙しいんだろうな」とわかります。職員の足音がバタバタと聞こえてくるようであれば、「何かあったのかな」「手伝わなきゃ」と思って立ち上がる人が多いんですよ。私が経験したことですが、あるとき認知症の利用者さんが転倒したケースがありました。職員が右往左往していたなか、当の本人は転倒したことを認識していないので、職員をつかまえて「火事でしょ、火事」と言っていました。こんなにも人が動き回っているんだから火事に違いないと思ったんですね。なので、私は「○○さん、火事です。でも、もう火は消えたから大丈夫ですよ」と言ったら安心してくれました。「火事じゃないです。○○さんが転倒されたんですよ」と言っても本当のことを話しても追加の説明が多くなったり、その話によって心配事が増えてしまっては仕方ないですからね。だから、相手の頭の中に描かれた物語に乗って、少し話を少し合わせるんです。
Dさん : 私でも自分の休憩時間になんだか慌ただしかったら、とりあえず立ち上がってしまう、なんてことはありそうです。これは本人の言葉を肯定して、対応したことがよかったというケースですね。
川畑 : ですね。認知症の人が立ち上がるのを少なくしたいときは、本人に何か活動をしてもらうといったプラスの発想だけではなくて、私たち自身がのんびり動いているように見せることも大事です。ゆったりとした時間が流れていると思ってもらえれば、本人もゆったりとした気持ちでいられると思います。
Dさん : なるほど。ここまでの話をまとめると、徘徊には理由があって、自分の欲求に従っていたり、誰かの声が聞こえたように感じたり、誰かを助けなきゃと思ったり、その理由はそれぞれということですね。そういえば、意識せずともできていたことってあるのかなと思えてきました。
川畑 : お、どんなことでしょう?
Dさん : 少し前のことですが、ふとしたときに歩き出す方がいて、どうやら看護室に向かっているみたいで。そこでわかったのが「看護師さんに湿布を貼ってもらいたい」ということでした。もともと発語の少ない方だったので、ジェスチャーで腕を動かして訴えることもあったり、別の場面ではお腹をポンポンして「トイレに行きたい」というサインを出したり、「部屋に戻って横になりたい」と意思表示することもわかったので、対応が考えられるようになりました。チーム全体で気持ちを理解できるようになってきています。
川畑 : いいですね。気づいて情報を共有しているのが素晴らしいですね。その人の目線でよく見て、先読みをする。この人が何をしようとしているのかなと考える時間がすごく大事です。解決する答えは一つじゃないですからね。先ほど「私たちがどんなときに立ち上がっているか」を考えるのが役立つとお話ししましたが、これを職員さん同士でやってみると、いくつもの例が出てくると思います。みなさんでアイデアを出し合って「この人だったらどんなことが起こり得るか?」「この人とこの人の共通な部分は何か?」というヒントを見つけてみましょう。「相手の背景を知る」ためにも、自分たちの背景を相手に当てはめる練習をしておくと、いざというときにも解決の糸口をつかみやすくなると思います。
Dさん : そうすると、声のかけ方も変わりそうですね。「どこに行くんですか?」ではなくて、「もしかしてトイレを探してますか?」「もしかしてティッシュペーパーが欲しいんじゃないですか?」とか。以前、食事がまだ終わってないのに動き出してしまう利用者がいたのですが、もしかしたら味噌汁みたいな味のあるものを飲みたくて探していたのかな、と考え、お味噌汁を入れるお椀にお茶を入れてあげたら飲んでくれて、立ち上がることもなくなったことがありましたね。
川畑 : 思いに寄り添いつつ、できる範囲で叶えてあげる。素晴らしいと思います。
Dさん : でも問題は、そうやって背景を理解してあげられることばかりじゃないというか……。「田んぼの手伝いをしたいのかな」と思ったとしても、何ができるのか。その思いはどう叶えてあげればいんでしょうか。
川畑 : それも難しいところですね。次回はそういった悩みについて考えてみましょうか。
Dさん : よろしくお願いします!
川畑智さんのプロフィール
理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表
1979年宮崎県生。病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。ほかに脳活性化ツールとして、一般社団法人日本パズル協会の特別顧問に就任し、川畑式頭リハビリパズルとして木製パズルやペンシルパズルも販売。年間200回を超える講演活動のほか、メディアにも多数出演。著作に『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズなど。
