知ってるつもりの認知症ケア 第13回 疲れやすくなるのはなぜ?
2025/10/14
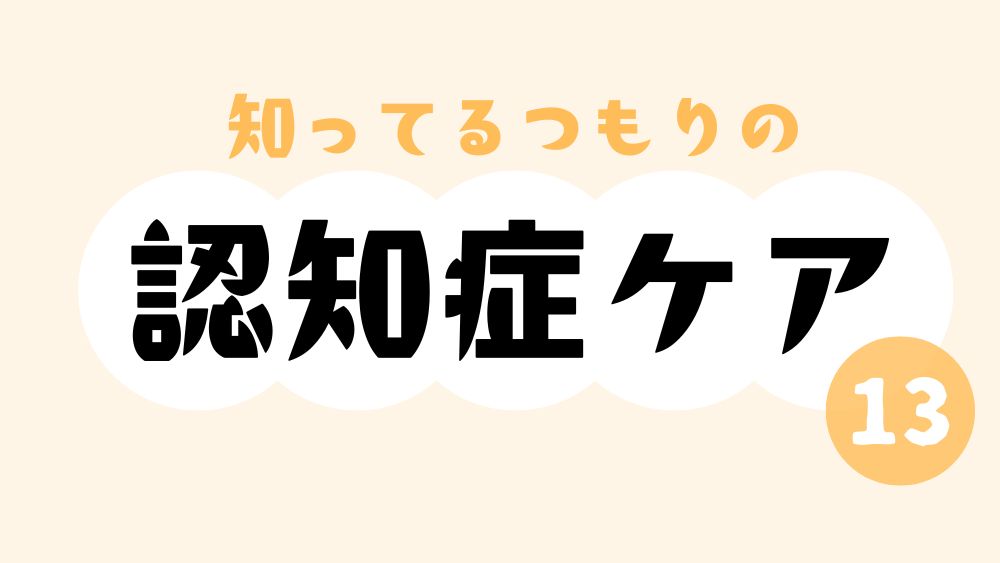
川畑智

認知症の人に接するときには「認知症の人の見ている世界」を正しく理解することが大切です。それによって適切で質の高いケアを提供でき、利用者は認知症になっても安心して生活することができます。
……とはいっても、さまざまな仕事をこなす日々の業務のなかでは、理想どおりのケアを行うことは一苦労です。
この連載では、認知症ケアの第一人者である理学療法士の川畑智さんのもとに、悩み多き介護職の方々が訪れ、ともに「現場のリアルな困りごとを理想に近づけるためのヒント」を模索していきます。
理想論ではなく、認知症ケアのリアルなつまずきにスポットを当ててみたいと思います。
川畑 : 今回は、リハビリやレクリエーションへの参加にどうも気が乗らない、という利用者さんについてもお悩みですね。「なかなか気持ちが乗ってくれない」という瞬間って、皆さんよく経験することかもしれません。
Eさん : そうなんです! 私が担当しているのは、車いすでフロア内を移動される利用者さんなのですが、本人も「リハビリを頑張りたい」と希望されていたのに、いざ始めると「疲れました」「ご飯が食べたい」「ここが痛い」って。いろいろ試行錯誤しても、どうにも順調に進まない、という感じです。
川畑 : うんうん。本人に意志があるにもかかわらず、なかなか集中できなくて実践することが難しい状況ですね。ケアする側としては「上手に説明ができなかったのかな」と反省してしまうかもしれませんね。
Eさん : まさにその通りです。「体操しませんか?」って誘っても、集中力が続かずで……。そのときの気分に合うように、何種類か選択肢を用意して提案をしてもみるのですが、どれも「んー……」という感じで、なかなか気乗りしてもらえない。
川畑 : こちらの提案に対して、なんだか言い訳をされたように聞こえちゃうことってありますよね。ここで注目してほしいのが、この「疲れた」という言葉なんです。この言葉を聞く機会って少なくないんじゃないかなと思います。実は、認知症の人がしばしば訴える言葉の一つが「疲れ」なんです。このことを「易疲労性」、つまり「疲れやすさ」があるということなんですね。
Eさん : 疲れやすさ、ですか。
川畑 : そうです。もし、ご自身が認知症だったら、レクリエーションやリハビリで何が一番疲れやすい要素になると思いますか?
Eさん : ええと……そうですね。何をするのかがわからないから、すごく不安で、いろいろ考えちゃって、それで脳が疲れちゃうのかな、と思いました。
川畑 : その通りです! 何をするかわからない、つまり今から何が起きるのかが認識できていない状態は、本人にとって大きな負担になります。たとえば、私たちは「玄関」が何をする場所なのか、「トイレ」が何をするためのスペースなのか、場所と行動がセットで頭に入っていますよね。
Eさん : なるほど。場所と目的が頭の中でセットになっている。
川畑 : そう。それは「人」に関しても同じです。私たちは脳の中で「この人(理学療法士などのスタッフ)と一緒のときはこのリハビリをするんだ」といったふうに、人や場所、そして行動の紐づきがちゃんと認識できている。でも、認知症の人にとっては、何が始まるのかわからないまま、さまざまな情報が飛び込んできて処理が追いつかず、不安と混乱で疲労につながるんです。
Eさん : 「疲れた」と言われると、単に運動不足だとか、やる気がないのかと思ってしまいがちでしたが、認知的な疲労が大きいんですね。
川畑 : 私たちは認知症でないゆえに、その方の気持ちに寄り添えなかったり、安易に「言い訳をされた」ように聞こえたりしてしまいますが、まずは疲れやすさ(易疲労性)を前提に考える必要があります。
Eさん : ありがとうございます。あと、認知症になっても感情は残る、とよく言われますよね。もしかしたら、以前にやったリハビリの印象が悪くて、「この人にこんな風にされた」と嫌なこととして思い出されて、拒否反応が出るのかも、と思ってしまうこともあるんです。
川畑 : 嫌な感情が残っていて、ますます足が遠のいてしまう。それも大事な視点ですね。たとえば入浴介助で「今からお風呂に行きますよ」と言われても、情報の処理が追い付かずに「お風呂って何? 何するの?」となるわけですね。それなのに、急にバンザイさせられて服を脱がされる。そして、着ているものが1枚しかないという状況になると、「あの人、私をどこかに連れて行こうとして。何をされるかわからなくて嫌だ」となっちゃいます。
Eさん : たしかに。
川畑 : でも、プラスの考え方でいけば、本人にとって良いことや楽しいことでは覚えていてくれている、ということですよね。あるグループホームの話なのですが、農作物なんかを作らなくなった土地(耕作放棄地)を借りて、利用者さんたちで畑仕事をしているんです。ショウガやジャガイモを植えて、定期的にバスで行くのですが、農作業をしてから2か月くらい経っても、ある利用者さんは「あのときのショウガの香り、よかったね」っておっしゃるんです。認知症が進行していても、感情は覚えている。「これをしていると楽しい」と心が揺さぶられると、ここがどういう場所なのかという記憶が残りやすくなるわけですね。
Eさん : やっぱり嬉しい記憶は残っているんですね。そうやって、いい循環に乗せられるといいなと思うんですけど、お風呂に入りたくなくて、「疲れた」「風邪をひいた」なんて言うんですね。引き下がっちゃうときも多いかもしれません。
川畑 : もちろん自己決定権は尊重すべきですから、無理強いはできません。でも、「お風呂に入る」ということが理解できていなければ、意思があるわけもないですね。では、感情に上手にはたらきかけるには、どうすればよいのか? 楽しいことならいいですが、なかなか悩みますよね。これを宿題にしておきますので、次回、考えてきましょう。
Eさん : わかりました! よろしくお願いします。
川畑智さんのプロフィール
理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表
1979年宮崎県生。病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。ほかに脳活性化ツールとして、一般社団法人日本パズル協会の特別顧問に就任し、川畑式頭リハビリパズルとして木製パズルやペンシルパズルも販売。年間200回を超える講演活動のほか、メディアにも多数出演。著作に『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズなど。
