対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第4回 新任者へのコーチング
2025/05/15
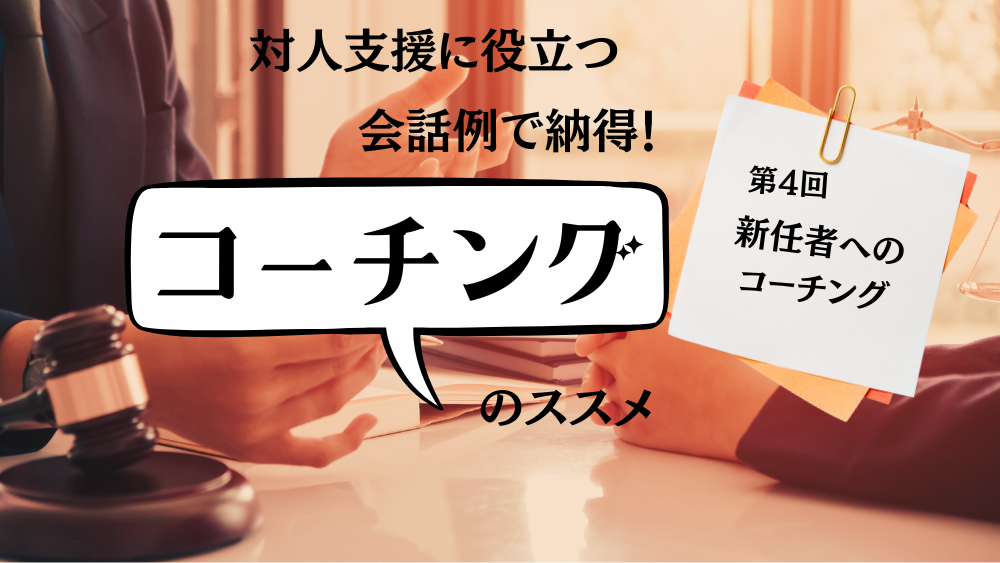
ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。
この記事の監修者
眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)
1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。
新任者にコーチングは有効か?
第1回から第3回までは、「コーチング」に関する基礎的な知識やスキルを身に付けるうえで大切なポイントを紹介してきました。今回からは、会話例を用いて、現場で実践できるコツを紹介します。
第1回「コーチングとは」では、新任者や異動後間もない人など、まだ必要な情報や目標を持ち合わせていない人に対しては、コーチングは不向きだと述べました。なぜなら、コーチングは相手に目標がなければうまく機能しないからです。ここで役立つのは「ティーチング」であり、「指導」や「指示」をすることで、相手に「問題解決」のために必要な情報をインプットする手法が有効であることを紹介しました。
とはいえ新任者にとって、コーチングがまったく有効ではないかというと、決してそうではありません。ティーチングを実施した後は、コーチングを積極的に活用することができます。
新任者に対するティーチング
ここで、新任者を対象として、ティーチングを行うときの会話例を紹介します。
新任者が入職して間もないころ、事務所のコピー機の前で何もできず立ちすくんでいました。
|
管理者:「何か困っているの?」 |
管理者は、ここでは新任者が「必要な情報を持っていない状況」だと判断し、「ティーチング」を活用しました。管理者は新任者に時間をかけてコピー機の使用方法を説明し、新任者にはノートにメモを取ってもらいました。無事に資料印刷と編集を終えた新任者は明るい表情で立ち去っていきました。
ところが1週間後、管理者は新任者が再びコピー機の前で立ちすくんでいる光景を目にしました。
|
管理者:「どうしたの? また何か困ったことでも起こった?」 |
ここで、コミュニケーション技術にティーチングのカードしかないと、再びティーチン
グが繰り返されます。場合によっては「前に教えただろ」「なぜ覚えられないんだ」など𠮟責の言葉が思わず口から出てくることがあるかもしれません。
そうなると、こちらのイライラ感や怒り、失望感が伝わり、相手のモチベーションを下げてしまいます。これでは自分で考えて行動する人材は育ちません。
新任者に対するコーチング
相手のなかに必要な情報がある場合は、コーチングを活用します。この場合は、コピーや編集の方法は1週間前にすでに教えています。
|
管理者:「まだ慣れてないから戸惑ってしまうよね。1週間前に機械の取り扱いやマニュアルの見方など教えたことは覚えてる?」 管理者:「そうそう、いい感じ。では、次にすることは何?」 |

新任者は管理者の質問にたどたどしく答えていきながら、覚書ノートに書いてある手順に従って作業を進めていきました。途中つまずく箇所もあり、「どうしたらいいですか?」と逆に質問されるシーンもありました。しかし、十分理解できていなかったところでも、「マニュアルのどこを調べればわかるかな?」などの質問を投げかけ、あくまでも新任者のアイデアや行動を引き出すことに努めました。これがつまり、コーチングです。
主体性を育てるコーチング
答えをすぐに教えれば問題は解決するかもしれません。しかし、それでは主体性の高い人材は育ちません。新任者は自分の力でやれたという達成感からか、その表情はとても明るくなっていました。一つの仕事に対する小さな自信を手に入れたようです。遠回りで面倒くさいと思われるかもしれませんが、コーチングは相手の主体的成長を待つコミュニケーションともいえます。
