道なき道をゆく! オルタナコンサルがめざす 強度行動障害の標準的支援 第13回 強度行動障害支援者養成研修の限界について考える② ――定着の壁
2025/08/20
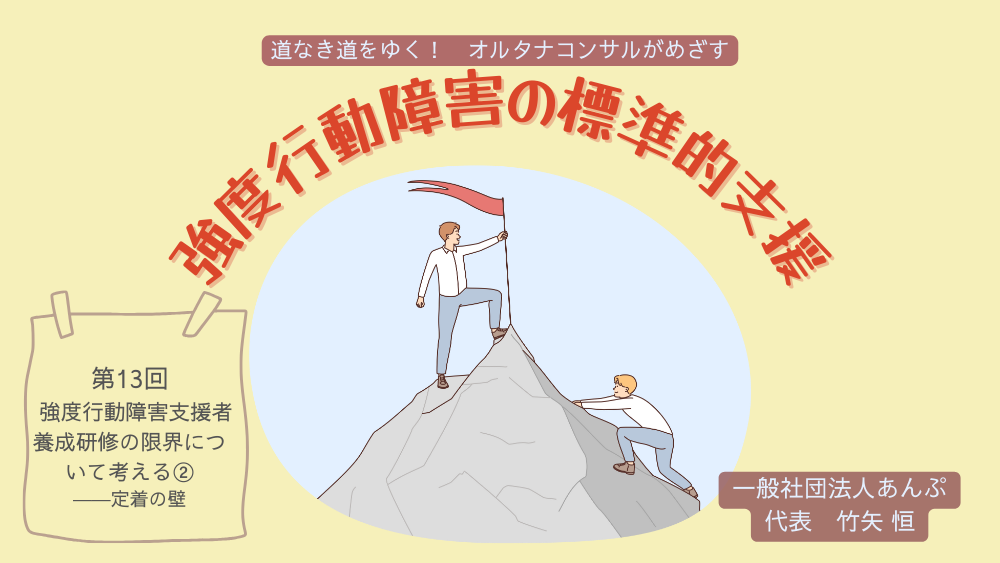
この記事を監修した人

竹矢 恒(たけや・わたる)
一般社団法人あんぷ 代表 社会福祉法人で長年、障害のある方(主に自閉スペクトラム症)の支援に従事。厚生労働省「強度行動障害支援者養成研修」のプログラム作成にも携わる。2024年3月に一般社団法人あんぷを設立し、支援に困っている事業所へのコンサルテーションや、強度行動障害・虐待防止などの研修を主な活動領域とする。強度行動障害のある人々を取り巻く業界に、新たな価値や仕事を創出するべく、新しい道を切り拓いている。
強度行動障害支援について、研修制度が整い、ここ数年間で支援の標準化や人材育成が大きく前進したことは間違いありません。しかし現場は、必ずしも制度設計通りには動いてくれません。「これで一安心!」と言いたいところですが、実際にはうまくいっている部分と、そうでもない部分が混在している気がします。
さて、今回は、前回の最後にふれた内容――「そうは問屋が卸さなかった」部分――を取り上げます。特に、研修で学んだ知識や技術が、日々の支援現場に根づかない、いわゆる「現場への定着」の課題について掘り下げて考えてみたいと思います。
国の報告でも明らかにされているように、研修修了者数は年々増えているにもかかわらず、その効果が現場で十分に発揮されていない現状があります。
この「定着の壁」は、なぜ生じているのでしょうか?
国の研修事業にかかわる私としては正直書きづらいテーマではありますが、あえて問題提起してみたいと思います。
現場への定着が課題という事実
厚生労働省の報告(令和5年度)によると、強度行動障害支援者養成研修の基礎研修修了者は14万3815人、実践研修修了者は7万7873人にのぼります(平成25年度から令和5年度までの累計)。一方、別の厚生労働省資料では「障害特性や支援手順などの知識は獲得できても、それが現場の支援実践に活かされにくい状況がある」と指摘されています。国が公式に「現場への定着が課題」としていることがわかります。
私は以前、障害者施設の管理者を務めていました。研修受講者が年々増えていく一方で、現場の支援が大きく変わったという実感はあまりもてていませんでした。研修を受けても、せっかく学んだ知識や技術は、日常の忙しさの奔流にのみ込まれ、学びが形になる前に風化してしまう……。そんな現実を何度も目の当たりにしました。国の研修事業にかかわらせていただいている身としては、その状況を非常に残念に、そして正直なところ寂しく感じると同時に、どこか申し訳ない気持ちも抱いていました。
制度設計上の背景と研修の限界
強度行動障害支援者養成研修の制度は、強度行動障害のある方の行動を障害特性と環境との相互作用から理解し、適切な支援を行える知識と技術を備えた職員を育成・配置することで、生活の質と支援の質を高めることを目的として創設されました。
しかし、多くの現場では、「配置要件を満たすための手段」として研修を受講するケースが少なくありません。平成27年度の報酬改定で、重度障害者支援加算Ⅱ(児童系は強度行動障害児支援加算Ⅱ)の算定要件として、基礎研修および実践研修修了者の配置が義務化されると、多くの事業所では加算算定や法令遵守を目的に受講者を確保する動きが強まりました。
これは制度の普及や受講者の裾野を広げるという意味で決して悪いことではありませんが、一方で、研修の本来の目的である「行動理解と適切な支援技術の習得」よりも、受講実績の確保が優先される傾向が生まれやすくなります。厚生労働省の研修実施状況調査や一部の自治体報告でも、受講動機に「加算算定要件の充足」を挙げる事業所が一定数存在することが確認されています。
さらにカリキュラムは、講義形式だけでなく演習や事例報告などの実践的な要素も多く盛り込まれており、まずは強度行動障害のある方の障害特性の理解を深め、そのうえで視覚的な手がかりやスケジュール提示、環境調整、コミュニケーション支援、チーム支援など、支援に必要な技術を多角的に学べる構成になっています。ただし、こうして習得した知識や技術を「この利用者の場合はどう応用するか」という個別具体的な判断にまで落とし込むには、現場の状況やチーム体制に合わせた追加の検討が不可欠です。
現状では、研修後に現場で伴走しながら定着を支援するフォローアップ体制は十分とはいえず、「学んだことをどう現場に適合させるか」は、受講者や事業所の自主的な取り組みに委ねられる場面も少なくありません。
何が学びを阻んでいるのか?
理由の一つに、福祉の現場の多くが常に人員不足との闘いを余儀なくされているのではないかと感じます。私が勤務していた事業所でも、ある職員が研修後に「環境調整をやってみたい」と提案してくれたことがありましたが、シフトや時間の制約が厳しく、実行に移すことができないまま終わってしまったことがありました。別の理由としては、現場での過密な勤務体制が想定されます。グループホームや入所施設などでは、夜勤明けでそのまま日勤や会議に入ることも少なくありません。
こうした慢性的な人員不足や過密な勤務体制は、研修で得た知識や技術を現場で試し、定着させる余力を奪っている気がします。言い換えれば、現場環境が学びを阻む一因になっているのかもしれません。
さらに「昔からのやり方」が根強く残っていて、新しい方法を提案しても、どこか変な協調圧力のような雰囲気に押し戻されてしまう場面を何度も見てきました。こうした空気は、私自身も若いころに経験したことがあり、そのときのもどかしさは今も記憶に残っています。
そうした職場では、研修で新たな光明を見出した職員が、それを現場で実践しようとしても、周囲の理解や協力が得られず孤立してしまい、学びが組織全体に広がらないことがあります。もしかしたら、そんな現場も少なからずあるのではないでしょうか。
私は勇者ではありません
強度行動障害のある方への支援では、利用者の課題となっている行動や状態が数週間や数か月の短期間で劇的に改善することもありますが、多くの場合はそうではなく、時間をかけて少しずつ変化していくものです。
もちろん、研修で学んだことがすべてではありませんが、私の経験でも、そこで得た特性への合理的配慮(たとえば感覚の過敏さに配慮した環境づくりや、見通しを持ちやすくするためのスケジュール提示など)を取り入れ、スモールステップでPDCAサイクルを回していくなかで、行動が一進一退を繰り返しながら、少しずつ改善していくことが多くありました。こうした変化も、改善への道のりではよく見られるものです。
ところが、せっかく変化の兆候があったとしても、少しの変化に「効果なし」とすぐに判断されることも少なくありません。研修内容はあくまで汎用的なもので、もっと深い障害特性の理解や行動の意味の分析など、深い検討を継続しなければ変化につながらないこともあります。そのギャップが、「研修通りにやってもうまくいかない」という誤解やあきらめにつながり、現場での活用意欲を削いでいるのかもしれません。
強度行動障害支援者養成研修は、課題となっている行動を一気に改善させる「一瞬で最強になれるチートアイテム」を配る場ではありませんし、講師を務める私も勇者ではありません。あいにく『ロトの剣』みたいな最強の剣も持っていなければ、『ベホマ』のような全回復呪文で誰かを一気に元気にすることもできません。残念ながら、この世界にはゲームの世界のような「課金すれば一気に解決!」という便利アイテムはないんです。もし本当に存在するのであれば、自分はきっと課金しまくっていると思います(笑)。
それでも、勇者ではない私たちにできるのは、現場の小さな変化の芽を大切に育て、根づくことを願いながら研修づくりに励むことくらいだと思うのです。
今回述べた背景からも、研修で得た知識や技術を「現場の当たり前」にすることは、決して簡単な道のりではありません。
次回は、その理由を、事業所に潜むさまざまな構造的課題という視点から紐解き、よりよい支援につながる視点を共有してみたいと思っています。
