道なき道をゆく! オルタナコンサルがめざす 強度行動障害の標準的支援 第12回 強度行動障害支援者養成研修の限界について考える①――はじまりと現在地点
2025/08/06
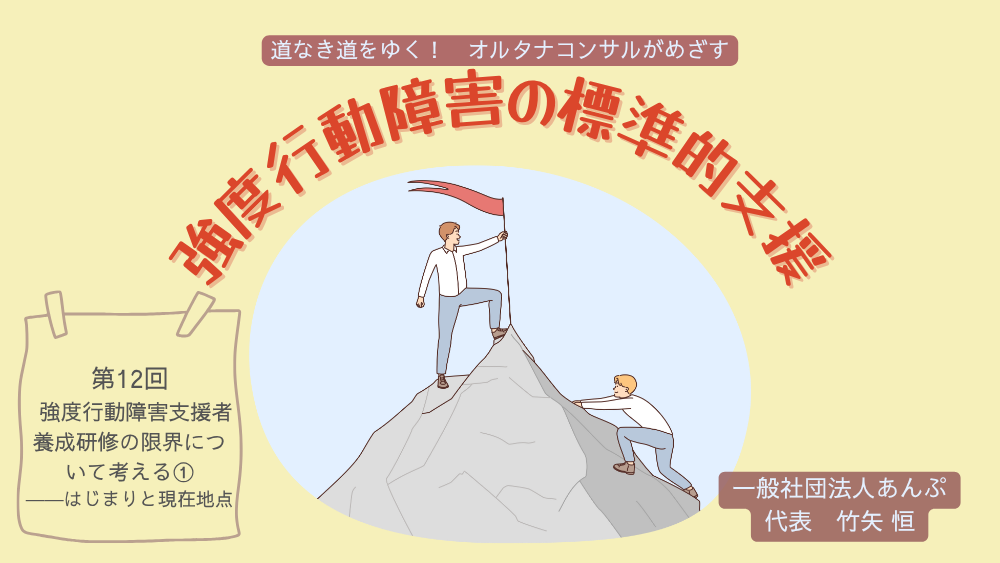
この記事を監修した人

竹矢 恒(たけや・わたる)
一般社団法人あんぷ 代表 社会福祉法人で長年、障害のある方(主に自閉スペクトラム症)の支援に従事。厚生労働省「強度行動障害支援者養成研修」のプログラム作成にも携わる。2024年3月に一般社団法人あんぷを設立し、支援に困っている事業所へのコンサルテーションや、強度行動障害・虐待防止などの研修を主な活動領域とする。強度行動障害のある人々を取り巻く業界に、新たな価値や仕事を創出するべく、新しい道を切り拓いている。
これまでの連載では、強度行動障害の状態にある方の行動の多くが、環境とのミスマッチや誤学習の積み重ねによって形成されていくこと、そしてその多くは児童期の段階で予防的な支援を講じることで軽減できる可能性があることをお伝えしてきました。
強度行動障害の状態にある方の行動を「困った行動」ではなく、「困っているサイン」として捉える視点、視覚的な手がかりやスケジュール提示といった環境設定の工夫が大切であること、そして児童期には子ども自身が理解し安心して行動できる環境づくりの重要性などにもふれてきました。こうした実践の積み重ねが、将来的な強度行動障害の予防につながるというお話でした。
適切な理解や支援が届かないまま成長してきた方々について
一方でさまざまな事情から、適切な支援や理解につながることが難しいまま成長し、大人になってから強度行動障害の状態に至るのも現実です。自閉スペクトラム症や知的障害を背景に、周囲とうまくコミュニケーションがとれず、環境とのミスマッチの中で困難を抱えながら必死に生活してきた人たちがいます。
こうした方々の行動は、表面的には「自傷」「他害」「破壊行為」などの激しさを伴うことがありますが、そうした行動の背景には、思いや困りごとが十分に理解されないまま、日々を必死に乗り越えてきた経験が積み重なっていることが少なくありません。ときには、「自分の意思が尊重されない」「一方的に制御される」といった理不尽な環境の中で、防衛的な行動として身についた側面も多いと想像します。
言い換えれば、「問題行動を学んだ」のではなく、困難な状況に適応しようとした結果として現れている行動であるともいえます。だからこそ私たち支援者には、その人の“今”だけを都合よく切り取るのではなく、これまでの人生の文脈に目を向ける想像力が求められるのだと思います。
属人的支援から、標準的支援への転換
こうした支援の必要性が社会的に強く意識されるようになった背景には、2013年に千葉県の知的障害者施設で発覚した「養育園事件」のような、深刻な虐待事例の存在があります。強度行動障害のある方が、適切な支援のないまま施設内で暴力や支配的な関係性にさらされたこの事件は、社会に大きな衝撃を与えました。
この事件を契機に、厚生労働省は行動障害に対する専門的な支援の必要性を明確にし、平成25年度に「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」を創設しました(実践研修は平成26年度に創設)。この研修は、強度行動障害の状態にある本人の障害特性と環境との相互作用から行動を理解し、標準化された支援技術を学ぶための仕組みとして位置づけられています。
研修は、目で見てわかる支援や環境調整、コミュニケーションの支援、チームでの連携など、支援に必要な要素を多角的に学べる構成になっています。個々の感覚や経験に頼る属人的な対応ではなく、共通の言語と理解に基づいた「標準的支援」を現場に根づかせることを目的としています。なぜなら、強度行動障害の状態にある方には、支援者個人の善意や勘に頼るのではなく、誰が支援にあたっても一定の質を担保できる、再現性ある支援が必要だからです。
虐待事件が起点
この研修制度には、支援の標準化や専門性の向上に加え、「虐待の未然防止」という観点もあります。行動の意味を読み解かず、理解や技術が不足したまま現場が疲弊していくと、やがてそれは不適切な対応や関係性の崩壊、そして虐待へとつながりかねません。
実際に制度創設の契機となった養育園事件も、支援の困難さと専門性の欠如が引き金となっていました。
「適切な支援が届かなかったとき、支援は人権侵害に転じうる」
この研修は、その痛ましい教訓に応える取り組みでもあるのです。
様々な制度の誕生と現場の変革
こうした支援の必要性が広く認識されはじめたのは、2010(平成22)年前後からです。厚生労働省は2011(平成23)年ごろより、強度行動障害のある人々の地域移行支援に関するモデル事業や調査研究を通じて、行動障害に関する理解の促進と専門的人材の育成の必要性を明らかにしてきました。
そして平成27年度の報酬改定において、障害福祉サービスの加算として「重度障害者支援加算Ⅱ」(児童系のサービスは強度行動障害児支援加算Ⅱ)が創設され、その算定要件として「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修および実践研修)を修了した職員の配置」が求められるようになりました。これは、制度として専門的な知識と技術をもつ支援者の養成を本格的に進める、重要な転換点となりました。
現在も各都道府県が主体となって研修を実施しており、行動の理解、環境調整、コミュニケーション支援、チーム支援など、支援に必要な視点を体系的に学ぶことが可能となっています。
地域連携体制の推進と新たな研修等の創設
近年は、さらに一歩進んだ取り組みとして、「中核的支援人材」や「広域的支援人材」の育成も始まっています。これは、単に一人の職員が研修を受講するという枠を超えて、事業所内や地域全体において強度行動障害支援の質を底上げし、支援文化を広げていく中核的な役割を担う人材を養成しようとする動きです。
中核的支援人材は事業所の中で継続的に学び合いや支援の工夫を促進する「推進役」として、また広域的支援人材は地域や複数事業所を横断して困難ケースに対応できる「支援のハブ」として位置づけられています。こうした人材育成の体系化は、困難な支援を現場任せにしない継続的な地域連携体制の確立に向けた重要なステップといえます。
支援者個人や一事業所の「がんばり」に頼らない支援体制へ
強度行動障害のある方の支援においては、個別のかかわり方や対応技術にとどまらず、「支援のあり方そのものを見直し、支援の土台を育てていく視点」も大切です。
今、現場に求められているのは、誰か一人の「がんばり」に依存する支援ではなく、組織や地域全体で支援を支える「文化」をつくっていくこと。そのための研修制度の充実や人材育成は、支援の質と持続可能性を高めるとともに、虐待の未然防止にもつながる、大きな社会的基盤として重要な役割を担っているのです。
……そうは問屋が卸さなかった
さて、ようやく研修制度が整備され、「これで一安心!」と言いたいところですが、実際にはうまくいっている部分と、そうでもない部分があるのが現状です。つまり、「研修ができたことで大きく前進した点」と、「研修だけでは解決しきれていない課題」が共存しているのです。
誤解のないよう、先に申し上げておきますが……、この強度行動障害支援者養成研修、本当にいい研修なんです。いや、私がちょっとだけ、企画や編集にかかわっているからって、“ひいき目”で言っているわけじゃありません(笑)。むしろ、まったくの初心者でも理解できるように、とても丁寧に、実践を想定して設計されたすばらしいプログラムなんです。これはもう素直に、「よくできてるなあ」と思っています。
とはいえ、じゃあ研修ができたからすべて解決! ……というほど現場は単純ではありません。
では、何が課題として残っているのか?
「研修ができてよかった!」だけでは終わらない、「研修だけではうまくいっていない」部分とは何か?
次回はこのテーマを掘り下げて、現場と制度の間にあるギャップについて、少しだけ問題提起してみたいと思います。
