道なき道をゆく! オルタナコンサルがめざす 強度行動障害の標準的支援 第11回 児童期の予防的支援の大切さ③――実践
2025/07/24
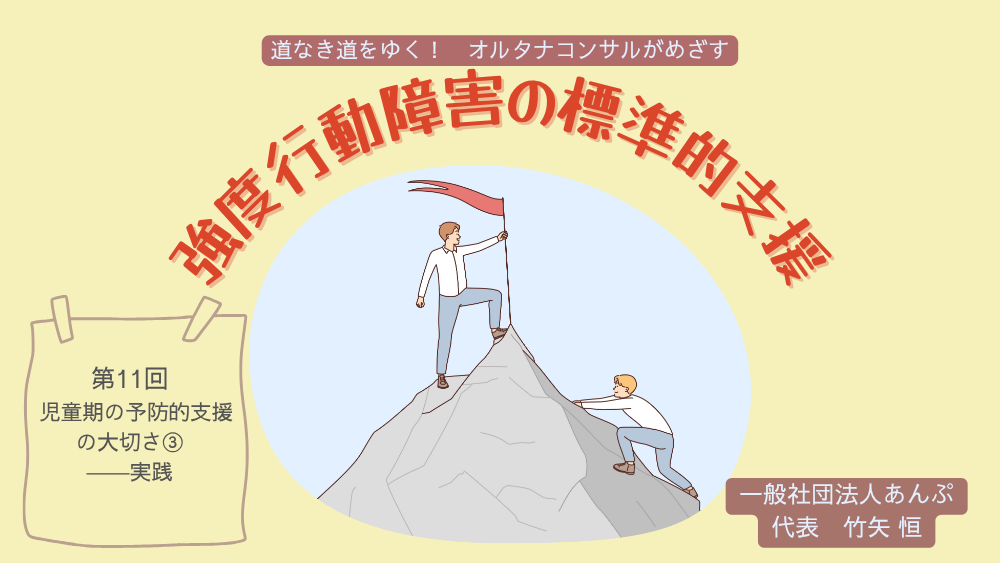
この記事を監修した人

竹矢 恒(たけや・わたる)
一般社団法人あんぷ 代表 社会福祉法人で長年、障害のある方(主に自閉スペクトラム症)の支援に従事。厚生労働省「強度行動障害支援者養成研修」のプログラム作成にも携わる。2024年3月に一般社団法人あんぷを設立し、支援に困っている事業所へのコンサルテーションや、強度行動障害・虐待防止などの研修を主な活動領域とする。強度行動障害のある人々を取り巻く業界に、新たな価値や仕事を創出するべく、新しい道を切り拓いている。
前回の連載では、児童期の支援のあり方をA君の事例を通して振り返りながら、強度行動障害の状態にある方が示す行動の多くが“学習されたものである”という視点、そしてその“誤学習”をいかに防いでいくかという「予防的支援」の重要性についてお伝えしました。
今回は、その予防的支援を日々の実践の中でどう具体化していけるのか、いわば“ミクロな支援”としての工夫や視点について考えていきたいと思います。
これからお話しする支援の話は、「特別な方法」ではありません。しかし、児童期の早い段階から、小さな支援を積み重ね、取り組むことが、その後の成長や生活の安定につながる、大きな意味をもつものだと考えています。
見通しを持てる環境づくり――視覚的支援の活用
自閉スペクトラム症のある子どもたちの多くは、話し言葉の理解が得意ではありません。そのため、口頭での説明だけでは、内容を十分に理解することが難しい場合があります。特に、抽象的な表現や長い文章は、混乱や不安を引き起こす原因となりやすいと言われています。
また、自閉スペクトラム症のある子どもたちは、「先の予測」を立てることも苦手とする傾向があります。そのため、「今から何をするのか」「どこへ行くのか」「いつ終わるのか」といった見通しが持てない状況では、不安や混乱が生じやすく、時には強い抵抗やパニックといった行動として現れることもあります。
“言葉を理解する”という行為は、空中に浮かぶ言葉の断片を一つひとつ拾い上げ、頭の中で文章として組み立てていくような作業にたとえることができます。また、予定を把握するというのは、実際にカレンダーが目の前になくても、頭の中にカレンダーを思い描き、そこから先の見通しを立てるような認知的な処理を必要とします。
こうした認知特性をふまえると、「視覚的支援」は、もっとも効果的でわかりやすい方法のひとつです。言葉だけで伝えようとするのではなく、スケジュールボードや絵カード、タイムタイマーなどの視覚的なツールを活用して、活動の順序や時間の見通しを“見える化”することで、不安を軽減し、安心して生活できる環境を整えることができます。
たとえば、「おやつの時間のあとにお散歩に行くよ」と口頭で伝える代わりに、【おやつ】→【おさんぽ】という絵カードを並べて見せるだけでも、本人にとっては理解しやすくなるかもしれません。また、「あと5分で終わりだよ」と言葉で伝えるよりも、タイムタイマーを使って、“残り時間は赤いエリア”として視覚的に示すほうが、時間の感覚がよりつかみやすくなることもあります。
ここで大事なのは、視覚的支援は「子どもを動かすための道具」ではない、ということです。私たちが忘れてはいけないのは、「本人が状況を理解して、安心して動けるようにするための手がかり」だということ。支援者の意図を伝えるためだけに使うのではなく、子どもが“自分でわかる”ことを支えるツールとして使っていきたいですね。
……とは言いつつ、私自身も時々忘れてしまうことがあります。だからこそ、自戒の意味も込めて、ここにあらためて書き添えました。
自分で行動できる「仕組み」を整える――構造化された環境づくり
「何を、どこで、どのようにすればよいのか」が明確にされている環境は、自閉スペクトラム症のある子どもたちにとって大きな安心につながります。
たとえば、作業机に着いたときに「どの課題から始めればよいか」「終わったらどうすればよいか」が一目でわかるように視覚的に示されていることで、支援者の声かけがなくても、本人が自分のペースで作業を進め、完了することが可能になります。
これは単に作業効率を上げるための工夫ではなく、「自分でできた!」という達成感を通じて、自己肯定感や主体性を育むことにつながる、重要な経験となるのだと思います。
小さな選択肢の積み重ね――自己決定を育てる
「今日は何をしたい?」と尋ねられても、選ぶこと自体が難しいと感じる子は少なくありません。そうした場合には、「リンゴとバナナ、どっちがいい?」といった具体的な選択肢を提示することが有効です。
こうした日常の中での小さな選択の積み重ねが、「自分で決める」「自分の気持ちを表現する」という力をゆっくりと育んでいきます。自己決定の経験は、本人主体の支援へと移行していくための基盤であり、本当の意味でのコミュニケーションの根幹をなす部分だと思います。ですので、強度行動障害の予防という意味でもとても大切な視点です。
感覚特性への配慮 ――刺激を整える支援
音や光、におい、肌触りなど、日常にあふれるさまざまな感覚刺激が、自閉スペクトラム症のある子どもたちにとっては強いストレスとなることがあります。そうした場合には、ノイズキャンセリング機能のついたイヤーマフや、肌触りのやさしい衣類、照明を落とすなどの感覚に対する配慮が有効です。
これらの工夫は、困った行動が起きたときの「対処」ではなく、そもそも行動が不安定にならないようにするための正に「予防的支援」です。そして、こうした支援の一つひとつの積み重ねは、その子どもにとっての「安心できる関わり方」として蓄積され、将来関わる支援者にとっても、重要な手がかりとなる支援ツールになっていきます。
成功体験を丁寧に積み重ねる ――肯定的なかかわりの力
自閉スペクトラム症のある子どもたちは、周囲とのコミュニケーションのすれ違いや環境への適応の難しさから、日常の中で失敗体験を積み重ねやすい傾向があります。「わからない……」「できない……」「叱られる……」といった経験が繰り返されることで、子どもは自分に自信を持てなくなってしまいます。
だからこそ、私たち支援者が意識的に「できた」という経験を支え、丁寧に積み重ねていくことが重要です。子どもが何かをうまくできたとき、「できたね!」「がんばったね!」といった肯定する温かい言葉をかける――それだけでも、子どもにとっては安心と自信につながります。
どんなに小さなことでも、「自分でできた」と感じられる経験は、その子の中に確かな成功体験として積み重なっていくのだと思います。本当に大切なのは、「できないことを減らす」ことではなく、「できたことを増やす」視点をもつことです。
日々の中にある小さな“できた”を丁寧に拾い上げ、子どもとともに喜ぶことは、自己肯定感を育てるうえで大切な土台となります。そして、私たち支援者がめざすべきは、子どもが「自分はできる!」「きっと大丈夫!」と前向きに感じられる力を育てていくことです。
前向きな人って、やっぱり強いですよね。困難に直面しても、折れずに進んでいけるその力は、きっと人生を支える大きなエネルギーになるのだと思います。
5年後、10年後の本人や支援者にとっての意味
どれも決して難しい支援ではありません。しかし、「今この場を落ち着かせる」ことに終始してしまう支援者の混乱の中で、子どもの将来を見据えた支援の機会を逸してしまうことがあります。
それゆえに、私たちは常に「この支援は5年後、10年後も本人にとって意味のあるものだろうか?」と問い続けながら、日々のかかわりを見直していく必要があるのだと思います。
強度行動障害の予防とは、「特別な支援技術」ではなく、「当たり前の環境を、当たり前に整えること」から始まります。私は、様々な方との出会いを通じて、そのことを深く学び、この仕事に対して前向きになれました。
次回は、強度行動障害支援者養成研修について、考えを整理してお伝えしたいと思います。
