知ってるつもりの認知症ケア 第14回 「強み」を知るには、どうすればいい?
2025/11/21
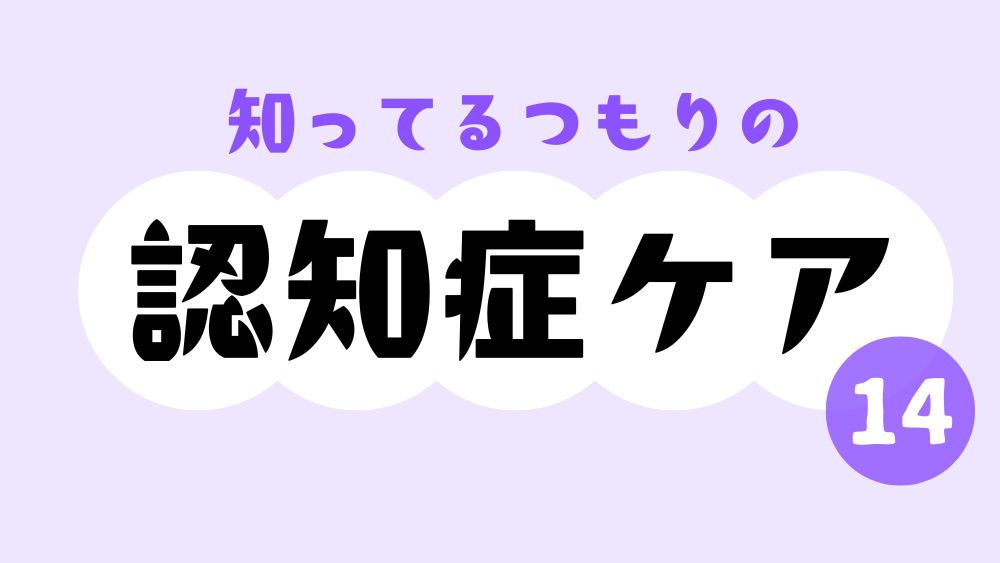
川畑智

認知症の人に接するときには「認知症の人の見ている世界」を正しく理解することが大切です。それによって適切で質の高いケアを提供でき、利用者は認知症になっても安心して生活することができます。
……とはいっても、さまざまな仕事をこなす日々の業務のなかでは、理想どおりのケアを行うことは一苦労です。
この連載では、認知症ケアの第一人者である理学療法士の川畑智さんのもとに、悩み多き介護職の方々が訪れ、ともに「現場のリアルな困りごとを理想に近づけるためのヒント」を模索していきます。
理想論ではなく、認知症ケアのリアルなつまずきにスポットを当ててみたいと思います。
Eさん : 前回は、認知症の症状として「疲れやすさ」があるというお話でしたね。だからこそプラスの感情にはたらきかけるにはどうすればよいか、ということでした。
川畑 : はい。以前、伝わりやすいコミュニケーションのコツをいろいろお話しましたが、その応用といえるかもしれません。「いざリハビリだ」という段階になってからではなくて、前倒ししながら声かけをしておくわけです。たとえば部屋に移動するまでに好きな曲を流しておいたり、「あら、今日は肌つやがいいですね」「顔の表情が明るいですね」みたいに褒め言葉をいくつも準備しておけば、「ここにいても気分が悪くない」「自分の居場所として受け入れられる」となってくる。そうすれば、声かけをしたときに「じゃあ、行こうかしら」と何の気なしに応えてくれるようになるんです。
Eさん : 誘導そのものが悪いのではなくて、前段階でのかかわりが影響を与えているということですね。かかわり方しだいで拒否のように見えたり、疲れやすくなってしまったり、何をしたらいいのかわからない様子が見られるようになってしまう。
川畑 : あとは、身振り手振りは「言葉よりも少しだけ早く出すこと」が大事です。まずは表情が大事で、そこにうまく言葉が機能すれば、ちゃんと集中もしてくれるし、疲労も少なく、楽しい気持ちで行動に移ることができます。ただ、言葉での指示は多ければ多いほどいいわけじゃない。言葉数が多いと、逆にわからなくなる。意外にも、優しい性格の方が陥りがちなミスですね。「こうしてああして……」と言ってわからない様子で、翌日もまた「ああしてこうして……」と繰り返して失敗してしまうケースですね。もちろんスピードも大事です。レクリエーションでやるゲームの手順について「まずはこちらの席の方から順々に一人ボールを二つ投げていただきまして……」と言っている間に「私は何をしたらいいの?」とわからなくなり、考えているうちに疲れ切ってしまう。
Eさん : もうわからないですね(笑)。早く話さないことを心がけるのが大事ですね。聴覚情報の処理が難しくなるんでしたよね。
川畑 : アルツハイマー型認知症の場合は特にそうですね。有名な長谷川式認知症スケール(HDS-R)では、「桜・猫・電車を覚えてください。後から聞きますからね」と耳から得た情報をすぐに取り出せるかどうかの即時記憶のチェックと、少し時間が経ってからの記憶(近似記憶)のチェックがあります。視覚的な記憶のチェックもあって、物品をしばらく眺めてもらった後で「さあ、何でしたか」と尋ねる。こういったテストは認知症を疑うためのものですが、点数だけに注目してはいけません。認知症の研究をするのであれば別ですが、ケアをする私たちにとって大事なのは、一つひとつの項目なんですね。つまり、単に認知症の疑いを測るためではなくて、その項目ごとに「私たちがケアで活かせる部分はどこか」を知ることなんです。
Eさん : 「この人は聴覚性の記憶はどうだろうか」「そもそも視覚性の記憶は残りやすいのかな」ということを見る。「活かせる部分はどこか」というプラスの視点で見ることが大事なんですね。
川畑 : そうですね。ただ、日頃から利用者さんと接している皆さんは、おのずと「できることは何かな?」というプラスの考え方ができているんじゃないかなと思うんです。ふだんの業務のなかで、どんなアプローチをしているか思い出してみてもらえますか?
Eさん : えーと、ある利用者さんは、同じ動作を真似してもらっています。その方は以前、書道をしたときに書き方がわからなくて涙ぐんでしまって。筆と墨汁を手にして、どうしたらいいのか手順がわからない。そこで「こういうふうに書くと書けますよ。1、2、3…でこう書きましょうか」というふうに見せると、「ああ、わかった」と思い出してくれました。あるいは、箸とスプーンの区別がつかなくなって、ご飯の食べ方がわからない方がいます。2膳分ご飯を準備して、「こういうふうにご飯を食べましょう」とやってみせながら真似してもらうと、食べてくれましたね。
川畑 : 必要がある方を見極めて、スタッフが対応できるための食事を追加で準備しておくわけですね。素敵なアプローチですね。
Eさん : それでもわからない場合には、たくさん説明してもわからないかなと思うので、簡単に「はい、これスプーンです。持ってください」と言って食べてもらいます。単語で促しながら繰り返して、少しわかったかなという表情になったら、「お願いします」と言って、また様子を見る。そんな感じですね。
川畑 : いいですね。利用者さんの様子や状態に応じてかかわりを工夫しているのがわかりますね。少し認知症の症状について、おさらいしてみましょうか。運動機能に問題がないのに、日常的な動作が困難になることを……?
Eさん : 「失行」でしょうか。
川畑 : そうです! では、自分で食べることができるのに、「左手にお茶碗を持って、右手のお箸は親指と人差し指と中指でこうやって使いながら食べるんですよ」なんて言葉で指示されると、どうもうまくいかない。立ち上がるときに「まず左足で出してから、ここの手すりがありますんで、これ握っていただいて、手の力でよいしょって持ち上げて……」なんて説明を受けたら、うまくいかない。
Eさん : たしか「観念運動失行」ですよね。
川畑 : そう。この失行が何かを言われて考えた結果として起こっている。つまり、観念を入った結果、運動ができなくなる失行。というわけです。むしろ、さりげなく誰かが「誰々さん、あっち行くよ」と言ったときに、すっと立ち上がれる。情報を引き出そうと理屈で考えるとうまくいかない。
Eさん : 本能だと行動できてしまうことがある。
川畑 : よく似た「観念失行」は個々の動作ができるのに、一連の行為の順番や、道具の使用方法などがわからなくなる症状ですね。よく例に出されるのが、ズボンを履こうとするものの、どうしていいかわからなくて着替えられない、というやつです。
Eさん : でも真似することはできる。先ほどの利用者さんの場合は「観念失行」だったわけですね。
川畑 : そうなりますね。こうやって認知症の知識があれば、ケアに活かしていくことができる。そして大事なのは症状そのものの特徴を知ることで、何が苦手で何が得意なのかがわかること。そうなれば、本人の強みにアプローチをしてみましょう、という先回りのケアを実践することができるんですよ。
Eさん : ケアに対する見え方が少しクリアになってきた気がします。ありがとうございます!
川畑智さんのプロフィール
理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表
1979年宮崎県生。病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。ほかに脳活性化ツールとして、一般社団法人日本パズル協会の特別顧問に就任し、川畑式頭リハビリパズルとして木製パズルやペンシルパズルも販売。年間200回を超える講演活動のほか、メディアにも多数出演。著作に『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズなど。
