対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第17回 相手のモチベーションを高めたいときのコーチング~傾聴~
2025/11/13
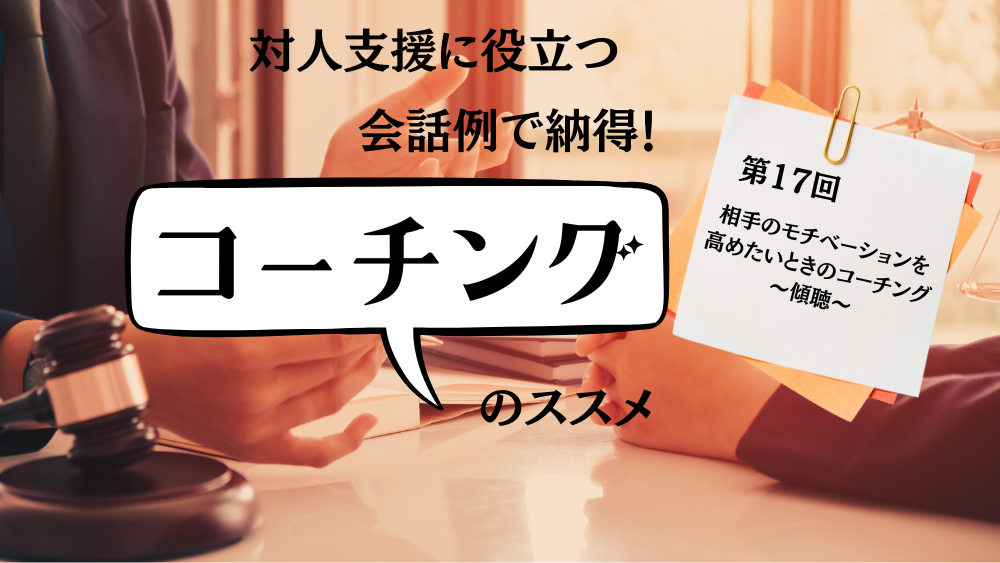
ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。
この記事の監修者

眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)
1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。
意欲を向上させるコミュニケーションの鍵は「傾聴」にあり
対人支援の現場において、相手のモチベーション(動機、意欲、やる気)を高めることは、成長や成功を引き出すための最初のアプローチです。モチベーションの度合いは、視線が上を向く、表情が明るくなる、笑顔が増える、前向きな言葉が多くなる、おどおどしなくなる、行動スピードが速くなる、集中しているといった具体的な様子からうかがい知ることができます。
なかでも「集中」は最も意欲の高い状態で、やる気の正体ともいわれます。たとえば、静寂を感じながら物事に没入し「テンション高めの平常心」を保っている状態です。何か行動を起こすときや困難に臨むときに全集中できれば、私たちは最大限の成果を手にすることができるでしょう。
モチベーションを上げる方法
モチベーションを上げる方法として、外発的な動機づけ(お金などの報酬や、褒める・称賛するなど)がよく知られていますが、その効果は一時的になりがちです。
一方、コーチングを活用して内発的に動機づけできると、継続的なモチベーションの向上につなげることができます。そのための主要なコーチングスキルは、以下の4つがあります。
①傾聴(アクティブリスニング)
②承認(アクノリッジメント)
③相手にとって魅力あるビジョン
④完了感のあるコミュニケーション
今回はこのうち、最も基礎となる「傾聴」について深く掘り下げていきます。
傾聴(アクティブリスニング)
1.「耳」ではなく「脳」で聴くアクティブリスニング
コーチングにおける「傾聴(アクティブリスニング)」は、単に耳で「聞く」(あるいは「聞こえる」)というレベルのものではありません。
傾聴とは、相手が何を伝えようとしているのか、その言葉に込められた感情や気持ち、言葉の周辺にある本当の思いや意味は何なのかを「脳」で聴き分け、正しく理解することを指します。まさに、「聴きに行き、聴き分ける」ことがアクティブリスニングなのです。
真摯に話を聴く態度を示すことは、相手に「自分を尊重してくれている」「話を聴いてもらって認めてもらえた」と感じさせ、その結果として意欲を自然と高めます。また、傾聴が行われることで、相手は自分の考えや気持ちを自由に話すことができるようになります。
コーチングの傾聴では、「いやいや」「それは違う」「そうではなくて」などと途中で口を挟まずに、最初から終わりまですべて漏らさずに聴くことが求められます。
2. 傾聴がもたらす「オートクライン」の力
傾聴のもつもう一つの重要な意義は、「オートクライン」を相手に起こさせることです。オートクラインとは、自分で話した言葉が、自分自身に作用する現象です。
話を最後まで真摯に聴いてくれる、心理的安全性の高い対話の場においては、実は最も話を聴いているのは話し手自身なのです。こうした環境の中では、話し手自身の中から、新しい気づきや問題解決のアイデアが泉のように湧き出てきます。
さらに、モチベーションが高まってくると、いつの間にかあきらめていた「希望」や「夢」を熱く語り始めるかもしれません。オートクラインは、相手の主体性ややる気を引き出し、「問題解決の主役はあくまでも自分自身である」という自覚に導いてくれるのです。
会話例で深堀り!傾聴でモチベーションを上げる方法
【NG例】
傾聴力が不足している上司の対話事例を見てみましょう。
ある上司は、普段から部下に関心をもち、部下のいつもとは違う様子を察知しています。上司自ら部下に歩み寄り声をかけていますが、対話を進めるうちに、部下の心は次第に上司から離れていく様子がうかがえます。
上司:どうしたの? ちょっと元気がないね
部下:いえ、そんなことはありません
上司:何かあったの?
部下:別に何もありません
上司:何もなかったら元気出しなさいよ
部下:ごめんなさい
上司:仕事が終わったら、最近できたカフェにでも一緒に行く?
部下:ごめんなさい、疲れていますから
上司:なぜ疲れているの?
部下:いろいろありまして
上司:いろいろって何があったの?
部下:いいんです、別に
上司:別にって、疲れているのはね、あなただけじゃないのよ
部下:ごめんなさい
上司:何か言ってみて、しっかり聞いてあげるから
部下:特別ありません、失礼します
上司:あらあら、とにかく元気出してね
このように言葉の表面だけを追う対話では、部下の心の奥にある真の思いや気持ちを傾聴できていません。これでは、部下のモチベーションが上がるどころか、下がる一方になってしまいます。
【OK例】
次に、傾聴力の高い上司の対話事例を見てみましょう。
この上司も、部下に強い関心を持っている点は変わりありません。しかし、違いは、部下が言葉として明確に述べていない真のメッセージを、上司がしっかりと聴き取っている点にあります。
上司:どうしたの? ちょっと元気がないね
部下:いえ、そんなことはありません
上司:何かあったの?
部下:別に何もありません
上司:あんまり言いたくないようね
部下:……ええ
上司:なんとなく最近のあなたの様子が気になってね
部下:ありがとうございます
上司:もし私でよければ話を聞かせてくれたらありがたいなぁ
部下:……ええ……まあ
上司:話しづらそうね、ここだけの話にするよ
部下:部長には言いにくいのですが……本当は私、仕事辞めたいんです
上司:仕事を辞めたいの?
部下:面白くないんです
上司:面白くないのね……
部下:やりがいがそんなに感じられないんです
上司:そうなの……やりがいが感じられないって、どういうこと?
ここでは、部下が「別に何もありません」と返答した際、上司は「あんまり言いたくないようね」と、部下の本当の思いを汲み取って伝えています。「……ええ……まあ」という煮え切らない言動に対しては、上司は「話しづらそうね、ここだけの話にするよ」とその思いや気持ちを察して優しく伝えています。
このように、部下の内面的な状態を正確に反映したメッセージを伝えることで、傾聴されていることを実感した部下は心を開く決心をし、自ら「仕事を辞めたい」という思いを伝え始めています。部下は「この上司なら自分の状態をきっと理解してもらえる」と判断したのです。
傾聴力の違いは、部下のモチベーションに反映し、さらにはその進退にまで影響を与えるのです。
頼りがいのある上司になるためには、耳ではなく脳で聴き、相手の心の中の真のメッセージを聴き分ける「傾聴」のスキルが不可欠です
