第17回こども家庭審議会基本政策部会
2025/10/15
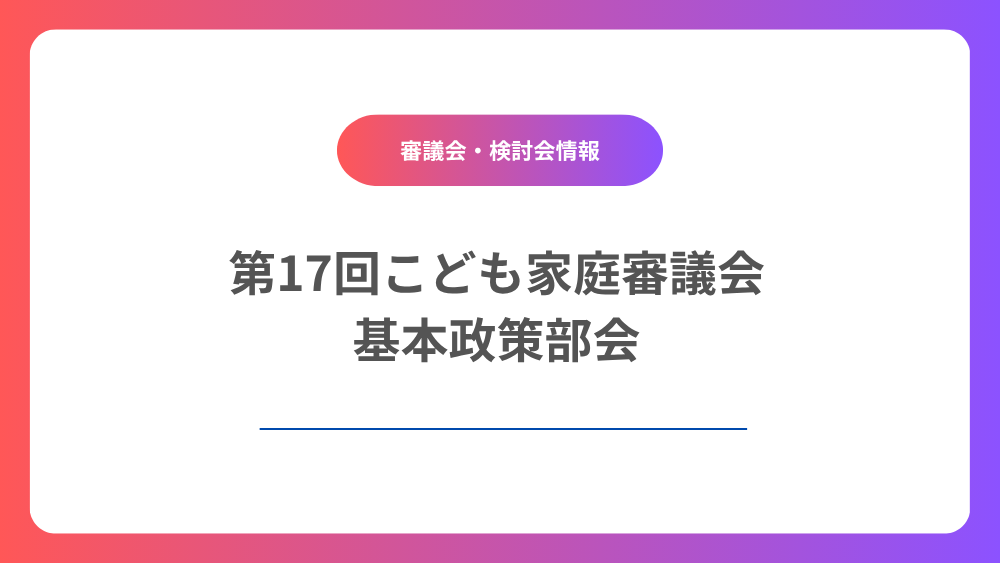
第17回こども家庭審議会基本政策部会について紹介します。
2025年9月22日に第17回「こども家庭審議会基本政策部会」が開催されました。
こども家庭審議会基本政策部会について
こども家庭審議会基本政策部会は、こども家庭審議会令に基づき令和5年4月に設置された部会です。
第16回こども家庭審議会基本政策部会については、
こちらの記事
をご覧ください。
第2期基本政策部会が始動
2025年9月22日に 第17回こども家庭審議会基本政策部会 が開催されました。今回は委員改選後初めての会合となり、こども施策の動きや基本政策部会の今後の進め方について、報告と意見交換が行われました。
1.こども施策の動向
事務局より、直近のこども施策の動向として、以下の3点が報告されました。
・
こどもまんなか実行計画2025
の策定
2025年6月6日に閣議決定された本計画は、こども施策を網羅し、政府一丸となって推進するためのものです。今後は毎年改定を行い、継続的に施策の点検と見直しを図る方針が示されました。
・
児童福祉法等の一部を改正する法律
の成立
保育人材の確保や虐待対応の強化を目的とした改正法が成立しました。保育士・保育所支援センターの法定化や、保育所等の職員による虐待の通報義務化などが盛り込まれています。
・
自殺対策基本法の一部を改正する法律
の成立
過去最多となった小中高生の自殺者数(令和6年:529人)など深刻な状況を受け、改正が行われました。こどもに係る自殺対策の体制整備や、デジタル技術を活用した施策、自殺未遂者や遺族への支援強化などが定められています。
2.今後の進め方とこども政策の全体像
部会は今後、来年6月ごろを目安に、こども施策の検証・評価や次期実行計画(2026)の策定に向けた議論を進めていくことが確認されました。
また、事務局からは「
こども政策の全体像
」が示され、個人の希望実現を支援し結果として少子化傾向の反転を目指す「少子化対策」と、今を生きるこどもたちの幸福を実現する「こども・子育て施策」が相互に関連し合っており、両輪で推進していく必要があるとの考えが共有されました。
3.主な意見
意見交換では、各委員から多様な視点での意見が出されました。
・複数の委員から、こどもの「ウェルビーイング(幸福)」の重要性が強調されました。特に、学年が上がるにつれて幸福度が低下する傾向があり、思春期世代が安心できる「居場所」を学校内外に複数確保することが急務であるとの指摘や、個人だけで完結するものではなく、こどもを取り巻く親、教師、地域社会といった「場」全体のウェルビーイングが循環することで、こどもの幸福につながるとの意見も出されました。若者委員からは、地方では中高生の居場所が絶対的に不足している現状や、予約制で利用しづらいといった運営面での課題が提起されました。
・少子化対策について、「こどもを増やす」ことだけを目的とするのではなく、「生まれてきて幸せだと思える社会」をつくることが結果として少子化対策につながるという意見が出されました。若者の賃金上昇や保育サービスの拡充、男性の労働時間短縮などを組み合わせることで、人々の出産希望をかなえ、希望出生率に近づけることが可能であるとの定量的試算も紹介され、多くの委員が、少子化対策とこども・子育て施策を切り離さず、一体的に議論していくことの重要性を共有しました。
・こどもの権利が侵害された際に救済するための独立した第三者機関(権利擁護機関)の設置について、国レベルでの議論を本格化させるべきだとの意見が出されました。また、自治体がこどもの意見を聞こうとしても、教育委員会や学校現場との連携が壁となるケースがあるなど、意見反映を実質的なものにするための課題も指摘されました。
・ヤングケアラーの経験を持つ委員から、支援制度や相談窓口などの情報が必要な当事者に届いていないという課題が提起されました。また、子育て当事者の委員からも、こども家庭庁の様々な取り組みが国民に十分に伝わっていないとの指摘があり、政策のコミュニケーション設計の重要性が改めて確認されました。
まとめ
第2期の初回となった今回の部会では、新体制のもと、ウェルビーイング、居場所づくり、少子化対策、権利擁護など、こども政策の根幹をなすテーマについて多角的な議論が行われました。
今後、これらの論点をさらに深め、「こどもまんなか実行計画2026」の策定に反映させていく予定です。
