第16回こども家庭審議会基本政策部会
2025/04/23
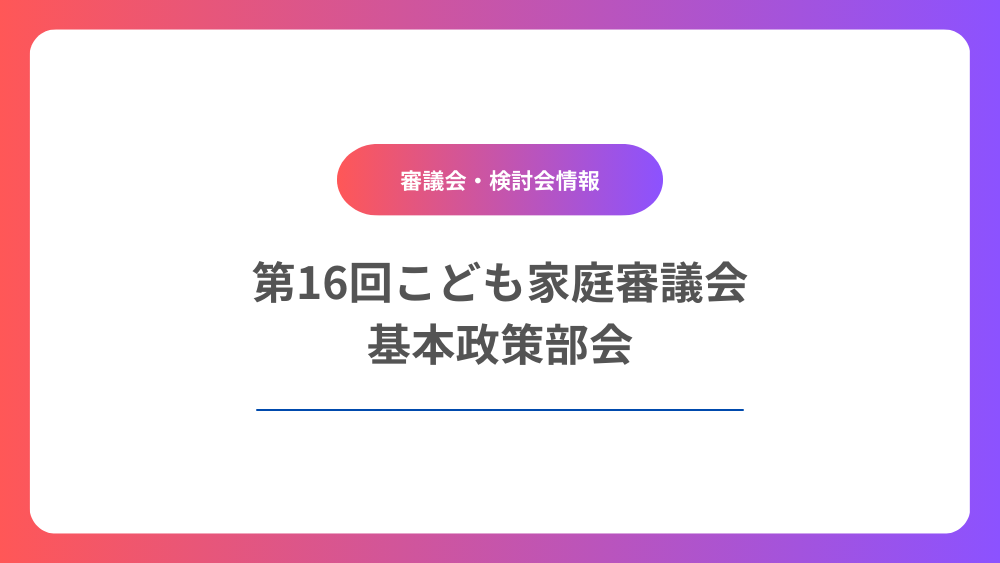
第16回こども家庭審議会基本政策部会について紹介します
こども家庭審議会基本政策部会について
こども家庭審議会基本政策部会は、こども家庭審議会令に基づき令和5年4月に設置された部会です。
委員は、20代、30代、子育て当事者などが全体の3割以上を占めています。こども基本法の基本理念おいて、こども・若者の意見反映や社会参画を進めていくことが求められており、こうした取組みを実践している審議会の1つとなっています。
今日に至るまで、こども大綱の策定に向けた素案検討なども行っており、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する調査、審議を行っています。
第16回 こども家庭審議会基本政策部会
令和7年3月27日第16回こども家庭審議会基本政策部会が開催され、次の3点の議題が審議されました。
1.こども・若者参画及び意見反映専門委員会とりまとめ文書について
こども家庭審議会基本政策部会の下に、こども・若者参画及び意見反映専門委員会を設置されており、専門委員より報告が行われました。
この専門委員会では、審議会等におけるこども・若者の登用を審議しており、「こども・若者が現時点において当事者となりうる事項について議論を行う会議」においては、候補者の検討段階において、こども・若者の積極的な登用を検討すべきであることが報告されました。
委員としての任命が難しい場合でも、こども・若者のみで構成される下部組織やワーキンググループの設置や、こども・若者からのヒアリング等の開催を検討することで、こども・若者参画推進につながるのではないか、などが意見としてあげられました。この基本的な考え方は、各府省庁、地方自治体においても、広く進めていくことが重要であるとされています。
この報告に、委員からは賛同する意見のほかに、選定前の情報共有や準備のサポートの必要性、事務局や経験者からの情報提供の重要性が指摘されました。
2.こども・若者によるこども政策の検証・評価について
2月8日に「こども若者★いけんぷらす」の仕組みを活用し、こども政策のPDCAサイクルにおける検証・評価(C)の段階にこども・若者の意見を反映させる試みが実施されました。
評価対象事業として、「地域の障害児支援体制強化事業」と「地域少子化対策重点推進事業」の2つが選ばれました。
1つ目の「地域の障害児支援体制強化事業」では、「病院に行って話を聞くだけではなくて、学校内でもっと相談に乗ったり話を聞いてくれることが普通にあるといいのに」といった意見や、「障害があるからという理由で批判されたり差別されることがないように、そういった考え方を変えていけばいいのではないか」という意見が出ました。実行計画においては、障害者のインクルーションの推進が強調されました。
2つ目の「地域少子化対策重点推進事業」では、「ライフデザイン等のセミナーに効果を感じている人が少ないのではないか」といった意見や、「特に自治体ではなかなかやれない部分は民間事業者と共同で取り組んだほうがいいのではないか」という意見が出ました。実行計画においては、セミナーだけでなく多様なコンテンツ開発や民間企業との連携、官民連携型の結婚支援などが盛り込まれました。
この取り組みに対して、多くの委員から賛同の意見があげられましたが、「こども若者★いけんぷらす」の登録者数が少ない実状も指摘され、母数をいかに広げていくかという点も意見としてあげられました。
3.こどもまんなか実行計画 2025 の策定に向けて
「こどもまんなか実行計画 2025」の素案が示されました。章立てはこども大綱の章立てを踏襲し、ライフステージを通した重要事項やライフステージ別の重要事項、こども施策を推進するための必要な事項などが盛り込まれています。各分科会や部会からは多岐にわたる意見や示唆が出されており、これらを踏まえて実行計画 2025 の素案を修正していく方針が示されました。
また、こども家庭庁の予算事業について、EBPMシートを作成し、アウトプット(事業の実施状況)とアウトカム(事業の成果)を整理したものが示されました。
委員からは「こどもまんなか実行計画2025」について、計画の構成や重点事項の明確化、こどもの権利擁護の推進、少子化・自殺対策の強化の重要性が指摘されました。EBPMに関しては、長期的な視点や自治体への情報提供、EBPMの評価が未達の場合の改善策やPDCAサイクルのCA(Check-Action)の部分がどこで示されるか、等の質問や意見、要望が出されました。
まとめ
第16回こども家庭審議会基本政策部会では、「こども・若者参画及び意見反映」、「こども政策の検証・評価」、そして「こどもまんなか実行計画2025の策定」を中心に議論が行われました。
審議会の資料等は
こども家庭庁のホームページ
よりご確認ください。
