【vol.14】放っておいてください | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2025/10/10

韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
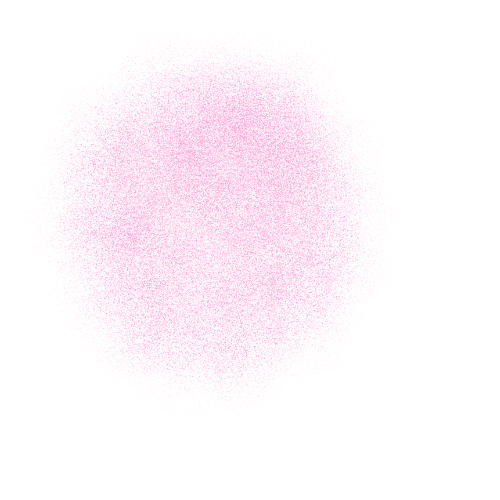 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
ほとんどの時間を一人で過ごすゼウスが座る場所は、丸いサイドテーブルの横にあるひじ掛け椅子だ。彼の姿は、無造作に脱ぎ捨てたコートが椅子のシルエットに沿って垂れ下がっているようにも見える。そこに在るものと同化した、静物のようだ。もしかすると、動かさずその場に休ませておくことも、一種の配慮だったのかもしれない。しかし、ずっと放っておくわけにはいかない。
一日中昼寝をすると活力が失われるため、ミューズとゼウスたちが過ごす部屋へ案内する。ここではリハビリ体操や単語ゲームなどのプログラムを行うのだが、ゼウスは腕も足も動かせないほど疲れているように見えた。ただ、一人にしてほしいという思いが伝わってくる。
デイケアセンターのエレベーターから歩行器に頼りながら現れる彼。一歩一歩を踏みしめるたび、脚の関節から一斉に悲鳴が聞こえるようだ。危うく、そして慎重だ。歩行器を握った腕を半歩前に出した後、手に力を込めると、ピノキオの足のように硬直した足が引きずられる。誰も代わりに動くことはできず、自身の力で移動しなければならない。ようやくサイドテーブルのある定位置にたどり着くと、彼は待っていたようにどさりと体を預ける。
そんな彼のもとに、今日は介護士と看護助手、社会福祉士が順番に訪れた。ゼウスがデイケアへの通所をやめると言ったらしい――夫がセンターにいる間、看病から少し息をつくことができていた妻は、再び身体の不自由な夫の世話に追われることになる。妻自身も高齢で、支えが必要な年齢なのだ。
サイドテーブルに集まったデイケアの関係者が一人また一人席を立つと、ゼウスは再び椅子と一体となった静物へと戻っていく。
実は、私はゼウスの声に心地よさを感じていた。「私は……」と話すたびに、〈アラビアのロレンス〉でファイサル王子を演じたアレック・ギネスを思い出す。ゆっくりと穏やかな低音には、人を安心させる力がある。今日もその声に寄り添おうと、近づいた。
「帽子のバッジは何ですか?」と尋ねると、彼はサイドテーブルに置かれた帽子を手に取って見せてくれた。
「これは朝鮮戦争参戦勇士で、これは花郎武功勲章だ」
「まあ、バッジ一つで人生が伝わってきますね」
私が感嘆すると、独特の低音でゆっくりと語った。
「俺は52年に入隊した」
私は大きくうなずく。
「国家への功労が認められてな。共匪討伐作戦で功績を立てた。その後50年、登山用品の商売を営んだ。長男は日本の銀行に派遣されたが、2年で癌で死んだんだ」
前に聞いたときも胸が痛んだが、再び胸が締め付けられ、ゼウスの手を強く握った。ゼウスの荒くごつごつした手は、実に温かかった。
「嫁と孫がいたんだが、孫は俺が大学まで学費を出したんだ」
「お嫁さんとお孫さんはよく会いに来ますか?」
さりげなく子供たちの安否を尋ねる私。
「それが問題なんだ。心が歪んでしまったのか。最近聞く話では……」
私はもう聞かなかった。聞こえなかった。ただ目の前のゼウスを見つめる。50年間登山用品を商い、子に先立たれた父親の心情を推し量るしかない。
「そうでしたか。でもどうか悲しまないでください。生活が楽になれば、きっと頻繁に訪ねて来ますよ。孫も子育てで忙しいでしょうから」
ゼウスの温かい手を握りながら。ゼウスの大きく丸い目がサイドテーブルの横の壁を見つめている。数分後、ふと我に返ったように私に尋ねる。
「火曜日と水曜日だけ来るんですよね?」
「はい」と答えると、
「それじゃあ、仕事をしてください。」
ゼウスの声には深い趣があった。劇的ですらある。逝った子と疎遠な孫の話をしていた彼が、今は目の前の私を気遣っている。
「こうしてお話しすることが私の仕事です。お年寄りからはたくさん学べます。母にもっと優しくしよう、美味しいものもたくさん作ろうってね」
私のアレック・ギネス、ファイザル王子は目を閉じて微笑んだ。そろそろ休みたいという合図だ。静かに席を立った。
あとで福祉士から聞いた話では、次男がみかんの箱を抱えてデイケアを訪れたという。「父をよろしくお願いします」と。息子に代わり、みかんは私たちの口の中で弾け、甘い午後を作ってくれた。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
