【vol.15】みんなを同じように扱わないで | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2025/10/28

韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
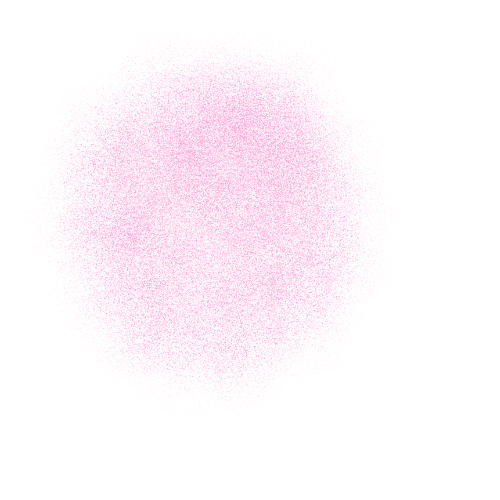 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
デイケアセンターに、重症の認知症を患うミューズが新しく来た。短期記憶が消えていくため、昨日会った顔も見知らぬ人になる。ドアが開くたびに外に出ようとし、一度外へ出ればひたすら一直線に進むだけだから、家に帰る道を見失ってしまうという。そんなミューズとペアを組み、私は一日をともに過ごした。
ソファの後ろにはミューズとゼウスの名札がある。空席には、新入りのミューズの名札も貼ってあった。
「あら、私の名前があるわ」
「はい、あなたはこちらへお招きされているんですよ」
しばらく自分の席に座ってから、彼女はバッグを手に立ち上がった。
「行かなくちゃ」
私の故郷は平壌(ピョンヤン)です。父がイデオロギーを批判する本を書いたために、朝鮮戦争のときに逃げてきました。父はなぜ私に「ソーシャルワーク」を専攻させたのでしょう。私は梨花女子大学を卒業しました。母は罵りました。「クソッタレ、ガキどもめ」と。私は心の中で「お母さんが嫌い、お母さんが嫌い」と思っていました。あるとき、姉たちが母に尋ねました。「なぜ私たちを罵るのか」と。すると母は、それが教育だと思っていた、と言いました。私には二人の姉がいましたが、二人ともアメリカに行ってしまいました。私はここに残りました。私が家を守らなければ、母と父を私が支えなければならない、そう思ったからです。
突然、我に返ったように再び起き上がり、ミューズは家に帰ると言う。彼女の腕に置いていた手にそっと力を込めながら、私は言った。
「あら、お昼ご飯を食べたあと、お化粧を直されなかったんですね。口紅がすっかり落ちてしまっていますよ」
「そう?」
私も立ち上がった。
ミューズはバッグから口紅を探す。私のを貸そうかと聞こうとしたとき、彼女のバッグから口紅が出てきた。鏡のある場所へミューズを案内する。彼女が化粧を直す間、私は少し待った。
口紅をきれいに塗り直したミューズは笑いながら、そろそろ家に帰らなきゃ、と言う。腕を組んだまま、私は言った。
「みんな亡くなってしまって、とても寂しかったでしょうね。お姉さんも二人ともいなくなって」
うなずいていたミューズが、突然、思い出したように口を開く。
「よちよち歩きの子ね。道を歩いていて小さい子がいると、可愛くてつい見とれてしまうの。これは私の経験から言っているのよ」
彼女の言葉に同意して、私はうなずいた。
一日中、ミューズと会話しているうちに、私は彼女の人生に、彼女の価値観に、次第に同化していく自分を感じていた。母親を憎み、父を失った喪失感に苦しむ娘になってしまう。
そのとき、定期的な認知テストの書類を持った同僚が近づき、ミューズに質問するために座るよう促した。その口調はどこか事務的に感じられた。こんなときは私が席を譲るべきなのに、うっかりその瞬間を逃してしまい、私はミューズと一体となったまま席に着いていた。ミューズにとっては、見知らぬ人からの質問を受けることになってしまったのだ。
ミューズが拒否の身振りを見せる。彼女以外の患者のケアも担う同僚は、時間に追われている気持ちだったのだろう。ミューズの意思に気づかない。ようやく認知テストが終わると、ミューズは私の方を見て一言言った。
「けしからん!」
「不快だわ!」
「上品に振る舞っていたのに、突然そういう下品な言葉が出るのよ。ふふっ」
まるでスローガンを叫ぶように力強く言うと、彼女はとてもさっぱりした笑顔を見せた。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
