死をことほぐ社会へ向けて 第19回
2025/10/07
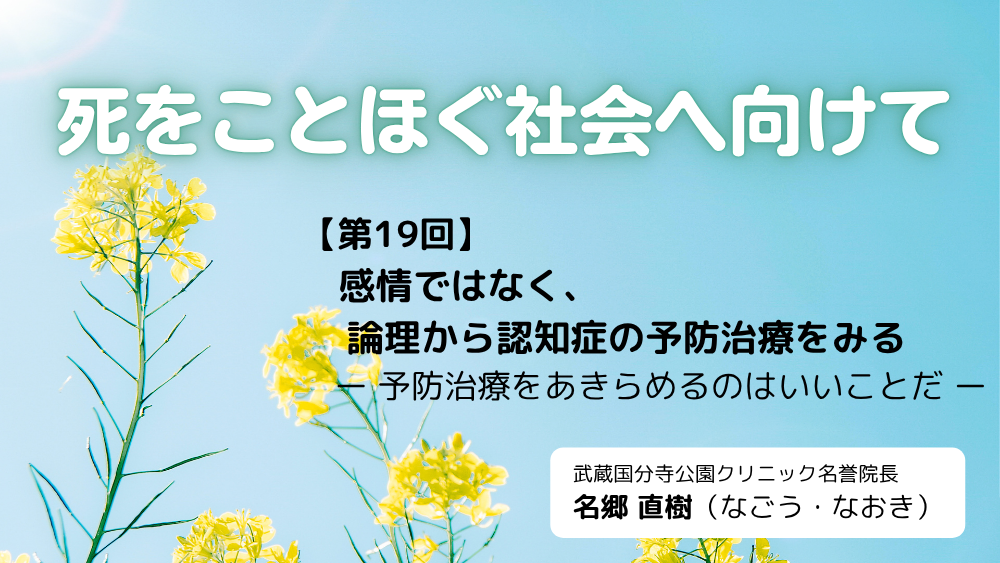
感情ではなく、論理から認知症の予防治療をみる……予防治療をあきらめるのはいいことだ
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
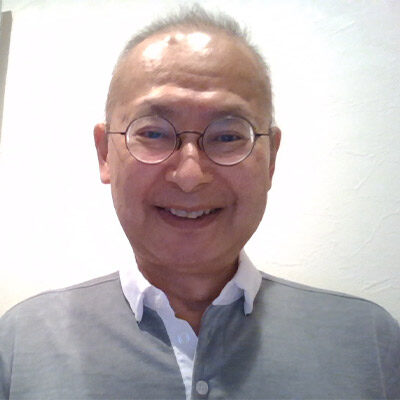
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
一部の治療可能な認知症では、下るどころか「上り坂の支援」としての医療が重要であるが、それ以外の認知症では、「下り坂の支援」が中心になる。しかし、「下り坂の支援」の困難さは、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、脳血管性認知症のいずれの場合も、予防でできることは発症を先送りすることだけ、治療についても進行を遅らせるという効果しかない点にある。つまり、認知症にならないようにするとか、認知症になってもなおるということをあきらめられないと困難だ。ここではまずあきらめるなんてことができるかという感情を抑えて、論理的に考えてみる。
予防治療の6つの可能性と合理的判断
予防治療をするかしないかという状況では、以下の6つの可能性がある。
①予防治療をして改善する
②予防治療をして、しない場合と比べて悪化のスピードが遅くなる
③予防治療をして、しない場合と同様悪化する
④予防治療をせずに改善する
⑤予防治療をせずに悪化のスピードが遅くなる
⑥予防治療をせずに悪化する
最悪はどれだろうか。「③予防治療をして、しない場合と同様悪化する」というのを多くの人が最悪と考えるのではないだろうか。さらに次に避けたいと言えば、「②予防治療をして、しない場合と比べて悪化のスピードが遅くなる」ではないだろうか。さらに「①予防治療をして改善する」という選択肢は可能性が小さく、現実的な対応としてそもそも選択肢に入らないと考えたほうがいい状況である。そうだとすればその①から③の3つを避けるためには、「予防治療をしない」という選択は、論理的には合理的な判断に思える。
ただ感情がそれを許さない。「何かよくなる方法があるはずだ」と。さらに、その感情につけ込み、「これで認知症が予防できる!」「これで認知症の症状がみるみるよくなる!」など、多くのデマとしか言いようのない情報が垂れ流される。それらの治療法は、まず避けたほうがよい。しかし、その中には、現時点で有効性が示されていないだけで、今後有効性が示される可能性があり、必ずしもデマとは言えないものがあるのも事実だ。とは言え、有効性が示される可能性がある予防治療であっても、副作用が不明とか、保険診療で受けられないために診療コストが大幅に高くなるとかの問題があり、そもそも効果がはっきりしない状況では、治療を受けるのは大きな賭けという側面もある。実際には、賭けに勝つ確率はかなり低い。それもまた上の6つの可能性で考えれば、「改善する」という明確な研究がない以上、先の進行を遅らせる効果しかない治療の場合と同様、論理的に考えれば保険診療以外の治療は避けたほうが賢明という結論に達する。予防法も同様である。コストはかからないものが多いが、そうだとしても同様に先の6つの可能性で考えれば、予防しないというのは論理的には最も受け入れやすいのではないだろうか。感情とは別に、論理的に考えれば、その感情も多少はコントロールできるかもしれない。
あきらめの先にある支援の転換―本人から周囲へ
しかし、あきらめるだけではどうしようもない。あきらめたうえでどんな「下り坂の支援」を提供するか、それが問題である。しかし認知症の本人は、「病気じゃない」「何も困っていない」などと言うことが多い。困っているのは本人ではなく、周囲の人たち、特に家族である。支援を提供する立場で言えば、支援の対象は、認知症の本人だけでなく、周囲の人たち、多くは家族である。本人の病気自体の改善をあきらめる一方、本人の症状をよくするという「上り坂の支援」をあきらめ、周囲の人たちの困難に対する支援を提供するというのが重要である。変わるのは本人ではなく、支援する側である。そうした意識の転換がとても重要だ。本人はそのままで、周囲が変わることにより、支援を考えていく。それがまた本人の症状も軽くしていくことにもつながる。
軽症のうちは、まず本人が好きなこと、やりたいことが続けられるような「下り坂の支援」が重要だ。本人がやりたくなくて、周囲が大事だと思うことを支援してもうまくいかない。ただその部分について多くの著作もあり、ここでは取り上げない。ここで取り上げたいのは、やりたいこともいずれはできなくなるのだが、そこからの支援である。つまり「下り坂の支援」の本番は、やりたいこともできなくなるところから始まるのである。
