死をことほぐ社会へ向けて 第18回
2025/10/06
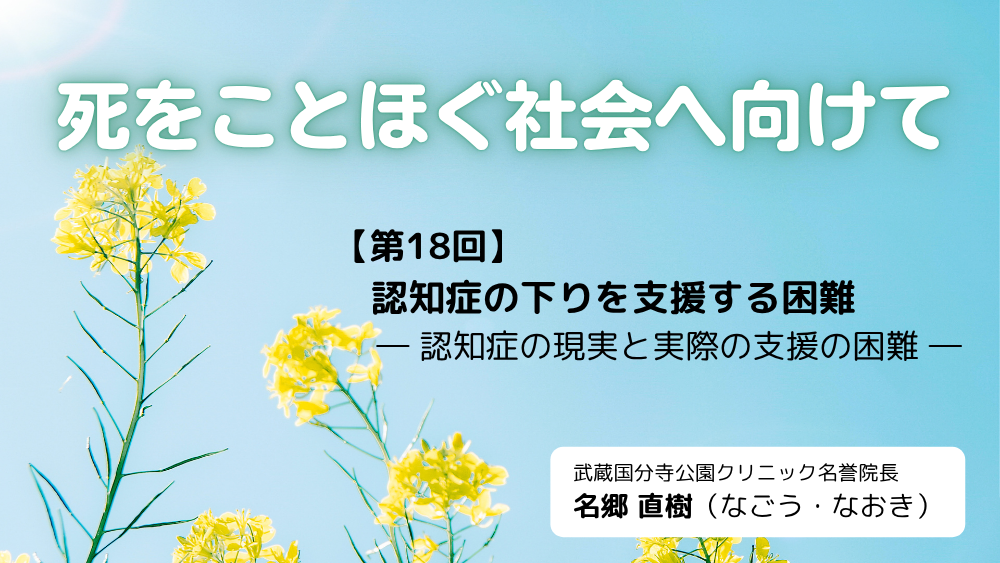
認知症の下りを支援する困難 ―認知症の現実と実際の支援の困難
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
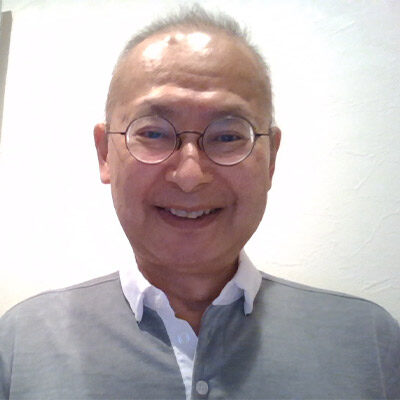
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
長寿になれば認知症は避けがたい。多くの予防法は、長生きを同時にもたらし、かえって認知症リスクの増加につながるかもしれない。認知症の経過は長く、10年以上にわたる場合も少なくない。現状では進行を止めたり、改善したりという明確な治療法はない。どうすれば認知症にならないですむか、どうしたら認知症が改善するかを考えても、今のところ明確な解決方法はない。予防できるとか、治るとかいう情報はほとんどでたらめと言っていい。ある時点で予防できるということに過ぎないが、人生はある時点では止まらず、死ぬまで続く。そこで今重要なことは何か。まず認知症の下る実際について知ることだ。その現実をまず整理しておこう。
認知症の有病率と寿命の関係
まず認知症の年齢ごとの有病率であるが、80歳から84歳では21.8%、85歳から89歳で41.4%と倍増し、90歳から94歳では61%、95歳以上では79.5%という報告がある。1)つまり、長生きすればするほど認知症になる確率は上がる。90歳を超えれば半分以上の人が認知症だ。95歳を超えて生きると認知症でない人が20%、認知症の人が80%と、長生きすればボケるのが普通というようなことである。
さらに認知症になった後の経過についても見てみる。診断後の寿命には幅があり、数年から数十年にわたる。十年後の生存率を見ると、アルツハイマー型で18.9%、レビー小体型では2.2%、脳血管性で13.2%との報告がある。2)もっとも多いアルツハイマー型で言えば、10年以上の介護を必要とする人が20%近くいるという結果である。さらに今後薬物治療が普及すれば、その期間はかえって長くなることが予想される
進行過程で生じる生活上の問題と周辺症状
認知症の進行の過程で起こる具体的な問題としては、病初期には物忘れに伴うものが多い。その後、場所や日時に関する見当識障害が問題になり、買い物や掃除にも困難が生じるようになる。お金の管理が怪しくなり、さらにはテレビのリモコン操作ができない、料理ができない、公共の交通機関が利用できないなど、生活に大きく影響する問題が生じてくる。その先には、着替えができない、嚥下が困難になり介助がないと食事ができない、トイレで排泄できない、介助なしに外出できない、お風呂に一人で入れないという基本的な生活レベルの維持が困難になってくる。そうした基本的な生活上の問題に加えて、抑うつや不安、暴力など攻撃的な行動、不潔行為、幻覚・妄想、徘徊、失踪など多様な症状、行動が出現する。
単に下るというだけでなく、「こんなはずではなかった」、「こんな人ではなかった」、「とても一緒に住めない」とか、支援どころではないというのが多くの本人や家族の反応だろう。「下り坂の支援と言われても…」というのが現実だ。さらには、それが長生きすれば避けがたく、予防や治療に頼るのも困難という状況のなか、いったいどうすればいいのか。本人も家族も追いつめられることが多い。
相談・医療・介護の入り口と現実的な難しさ
そこで実際に行える「下り坂の支援」とは何か、ということであるが、まず本人や家族にとっては、第三者に相談するということだろう。まず医療機関で評価を受けるのは、治療可能な認知症を除外する意味では重要である。ただ「下り坂の支援」に関しては、あまり頼りにならないかもしれない。ここはやはり介護・ケアの出番である。具体的には地域包括支援センターに行く、患者家族の会に出てみる、というのがいいかもしれない。しかし、多くの認知症患者は病院を受診したがらない。とりあえず困っている家族だけで相談というのが現実的だが、軽症の認知症では、それが悪化のきっかけになったり、さらにその後の病院受診や介護施設相談の拒否につながったり、かえって対応を困難にするリスクもある。
また経過中の本人の不安や介護負担で言えば、軽症である時期の方が本人の不安が強く、運動機能や言語活動が保たれている時期の方が、攻撃的な行動や徘徊、迷子などの問題が起きやすく、介護負担が大きい傾向にある。それにもかかわらず、介護報酬は低い。重症化して車いすやベッド上の生活が中心になれば、むしろ介護負担は軽減する場合も多い。ただ生活面での支援は必須となる。現実の「下りの支援」は困難を極める。その困難にどう対処するか、認知症の話題がまだ続く。
