死をことほぐ社会へ向けて 第17回
2025/09/19

老いと認知症 ―認知症の予防や治療効果とその現実
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
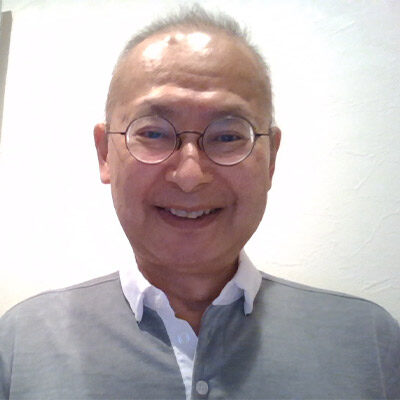
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
引き続き「下り坂の支援」について考えたい。ここまでは「老いる」という全体に対して「下る支援」を取り上げてきたが、今回はその「老いる」中での認知症について取り上げたい。
メディア情報と過大評価の問題
世の中では、「この食事で認知症が予防できる」「社会とのつながりが認知症を予防する」「新薬で進行を遅らせることができる」など、認知症に対する予防法や治療法がすでにあるかのように、テレビやネットなどで流され続けている。
しかし、そうした情報には間違っているものが含まれていたり、たとえ間違っていなくても効果を過大に評価したりしているものが大部分だ。認知症は現状では“下る”しかない。予防法といっても、認知症にならないというわけではなく、単に先送りにすぎない。長生きは認知症の最大のリスクである。つまり、長生きをしないことが、認知症にとって最も明確な予防法である。しかし、それでは多くの高齢者は認知症になる前に死んだほうがよい、さらには認知症になったら死ぬべきであるという差別社会をもたらす可能性が高い。予防や治療を云云する以前に、予防や治療ができなくても、認知症の人ができるだけ快適に暮らせる社会をどう作っていくかが重要である。それは予防法、治療法が確立しても、その重要性には変わりがない。認知症患者が快適に暮らせる社会は、認知症がない人にとっても住みやすい社会だろう。
認知症の予防・治療情報への懐疑と前提
その前提を明らかにしたうえで、認知症の予防、治療に関する研究結果を検討してみる。まず、予防について実際に行われた研究結果を見てみよう。日本で行われた運動、脳トレ、栄養指導、動脈硬化リスクコントロールを組み合わせた予防介入の効果を検討したランダム化比較試験では、予防が有効という結果ではあるが1)、その効果は小さく、受験でなじみの深い偏差値で言えば、認知機能の変化で2点弱の差に過ぎない。予防に取り組まないと偏差値50のまま変化しないが、予防に取り組めば50から52へわずかながら改善する程度の効果である。この2点の変化に周囲で気が付く人はほとんどいないだろう。受験の話で例えれば、偏差値50の大学に落ちて、52の大学に合格するというのは決して珍しいことではない。こう言えば、この差がどういうものかわかりやすいだろう。これは単に統計学的な差に過ぎず、現実の効果としてははっきりしないといったほうがよいと思われる。その統計学的な効果も1年半という期間を限った場合の話で、10年後の効果となるとはっきりしない。予防法の多くは認知症を先送りするだけでなく、脳卒中や心臓病を先送りする効果もあることが多く、結局長生きをして、かえって認知症リスクが増すということになるかもしれない。
さらに治療についていえば、進行を止めたり、改善したりという効果がある治療法は今のところなさそうだ。レケンピという何百万円もする高価な治療が保険適用になったが、この薬も進行を止めたり、改善したりする効果はない。進行を遅らせる効果が示されたということであるが、それはあくまで統計学的な話であって、治療を受けた人と受けない人を比較しても、目で見てわかるような効果が認められる人は少ない2)。実際の患者で効果があるとは言えず、脳出血や脳浮腫という重大な副作用が起こることが示されただけというのが、研究結果の妥当な解釈である。
進行を止めたり、改善させたりという明確な予防法、治療法がない認知症については、「上る支援」は将来可能になるとしても、今の時点では困難で、「下る支援」こそが重要ではないだろうか。その「下る支援」を提供するには、認知症の下りの現実を把握し、下りの現実を踏まえた支援を考える必要がある。
