死をことほぐ社会へ向けて 第16回
2025/09/05

「下り坂途中の急坂」にどう対応するか……「ヨボヨボコロリ」で終わるのは
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
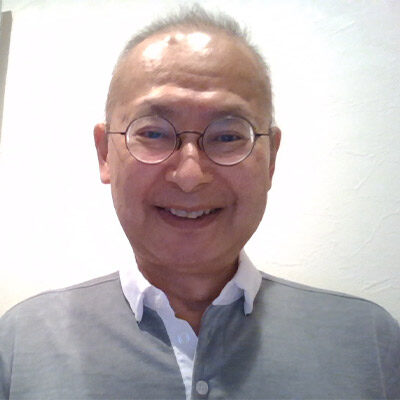
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
「ヨボヨボコロリ」という終末期の形
「下り坂」にもいろいろな局面がある。加齢に伴うなだらかな下り坂が基盤にあるが、それだけではない。その途中で、肺炎や尿路感染などの感染症になったり、心不全が悪化したり、認知症によるせん妄状態などで問題行動を起こしたり、あるいは新たに心筋梗塞や脳卒中になったり、がんが見つかったり、健康上の問題が起こる。老衰と言っても、ただなだらかに衰えるだけということはまれで、上記のような出来事で急激な悪化をきたすことがしばしばだ。「下り坂途中の急坂」である。
ここで急坂を転げ落ちるように亡くなってしまうというのは、高齢者の最期では決して珍しくない。ピンピンコロリに対して、私はこれを「ヨボヨボコロリ」と呼んでいる。高齢で下り坂になり、動けなくなりつつあったり、認知症が進みつつあったりする中で、「コロリ」と急に亡くなる状況である。世の中の多くの人がピンピンコロリで逝けたらいいよねと言うが、この「ヨボヨボコロリ」についてはどうだろうか。
ピンピンコロリが良いというのは、苦しむ時間が短いとか、元気なままで衰える時間がないとかいうのが理由だろう。そう考えると「ヨボヨボコロリ」も、これ以上衰える時間を過ごすことなく、苦しむ時間も短く逝けるという点でピンピンコロリと似たような状態である。しかし、「ヨボヨボコロリ」が私の造語であるように、それを望むという人にあまり出会ったことはない。逆にそうした状況でどうするか、人生会議(ACP)※で話し合いましょうというのが世の流れだ。話し合いなんかしなくても、普段からピンピンコロリがいいって言っていた人であれば「ヨボヨボコロリ」でいいのではないかという話にはならない。
このピンピンコロリを望む世の中と、それと似た「ヨボヨボコロリ」がまるで話題にならないことのギャップは何か。ピンピンコロリはまだ死が遠く、現実の問題としては取り扱われない中で話されることが多いのに対し、「ヨボヨボコロリ」は、すでに死が現実に近いところでの話というのが大きな違いかもしれない。実際に死が近づいてみると、やはりそれを遠ざけたいというのが多くの人の反応なのではないか。たとえば、現実に目の前で突然倒れた人がいる場面では、誰もがここでピンピンコロリがいいとは思わず、救急車を呼んでしまうように、どこまでも死を遠ざけたいという気持ちはごく自然でありふれたもので、ピンピンコロリは単に頭の中のイメージに過ぎないのかもしれない。現実にはピンピンコロリを望む人などいないということではないだろうか。
「ヨボヨボコロリ」と医療・ACPの課題
実はピンピンコロリを望む人は意外に少ない。むしろ「ヨボヨボコロリ」の方を望む人のほうが多いのかもしれない。「ヨボヨボコロリ」を望んでいないわけでなく、それを阻むものが現場にあるのではないか。
この「ヨボヨボコロリ」の現場で、まず問題になるのは、病院に搬送するかどうか、そうでなくてもできるだけの医療を提供するかどうかということだ。さらにその決断は急激に悪化した本人よりも周囲にゆだねられることが多い。人生会議(ACP)などで事前にどうするかを決めておいて、それに基づけばいいと言われるかもしれないが、こんな状況を想定して本人が病院は嫌だと言っていたわけではないと周囲が反応する。本人も苦しいので、病院は嫌だと言ったけど、こんなに苦しいのでは病院に搬送してほしいと、気持ちが変わることもある。
ここでの医療の役割は、診断して治療して回復を目指すだけでなく、その場の苦痛を軽減する緩和医療の役割も大きい。さらに苦痛の軽減という点では、医療機関においても、診断・治療より、介護・ケアが優先されてもいい。そうは言うものの、急坂の変化が起きて医療機関へ委ねるところで、病院に行くからにはまず診断・治療、緩和や介護・ケアは二の次という現状がある。もちろん後者は病院の主な役割ではないので、緩和、介護・ケアを優先というなら在宅で、あるいはホスピスでというのは病院側の対応として妥当なところではある。ただ、搬送を希望する本人とその周辺からすれば、そう割り切れず、在宅やホスピスの方がいいかもしれないとの考えも捨てきれないところで病院への搬送が決断されるのが現実だ。
この問題は人生会議(ACP)とも深く関わっている。「ヨボヨボコロリ」について、いましばらく考え続けたい。人生会議(ACP)を今後取り扱うところで、改めて論じたい。皆さんも、しばし考えてみてください。
※人生会議(ACP)
これからどのように生活して、どのような医療や介護を受けて最期を迎えたいか、自分自身の希望について、前もって家族や回りの人などと話し合って決めておくこと。アドバンス・ケア・プランニング(ACP)ともいいます。
