死をことほぐ社会へ向けて 第15回
2025/08/22
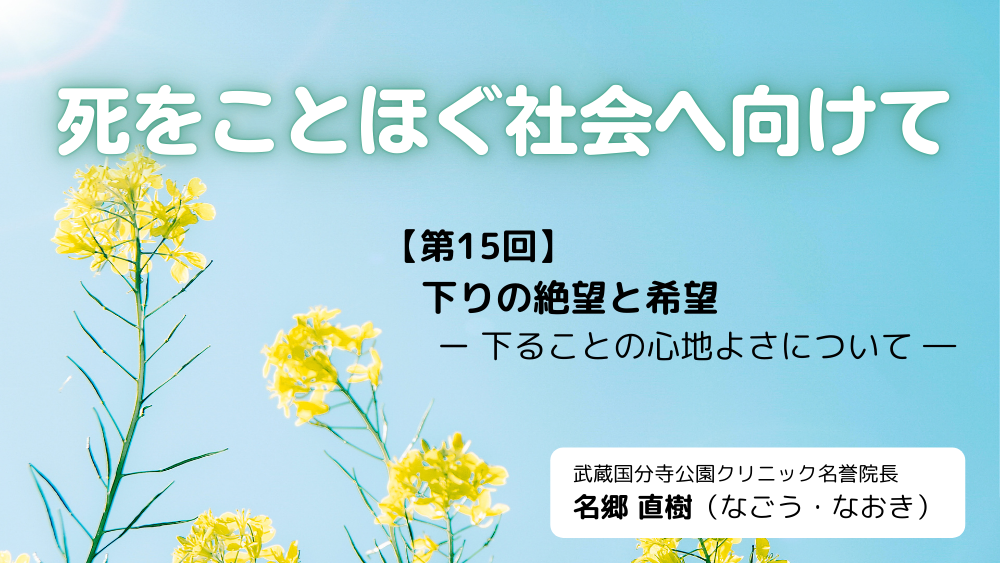
下りの絶望と希望……下ることの心地よさについて
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
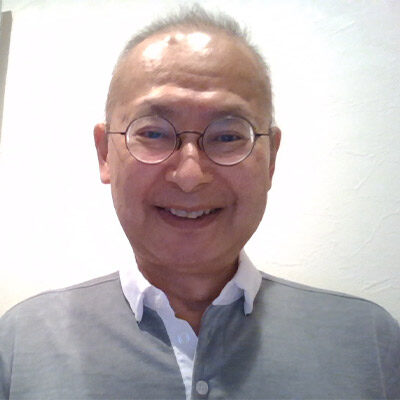
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
社会の価値観と下り坂のとらえ方
「下り坂を支援する」と言っても、何のことを言っているのかわかりにくい。下らないようにする支援、もう一度上るための支援がまず思い浮かぶ。そうではなく、下っていくことそのものに対して何かをすることを、支援と受け取ることはむずかしい。
ともすれば、早く死ぬための支援と受け取られ、見捨てられたように感じるかもしれない。さらには下り方向の支援そのものに受け入れがたい面がある。人の手を借りて生きていくくらいなら死んだ方がましとか、そこまでではなくても、迷惑をかける後ろめたさとか、支援を提供する側も、支援を受ける側も、「下り坂の支援」を考えるのはなかなか困難だ。そもそも、「下り」という言葉はネガティブな響きをもっている。
この背景には、上ること、がんばることに価値を置く社会がある。それは高齢者に対しても同様だ。テレビでも、元気で活動的な高齢者をほめたたえる場面をよく目にする。そんな高齢者に「元気の秘訣はなんですか」などと質問する。そこにはどんな回答をしても笑いがあったりして、ほとんど役に立たないような秘訣も好意的に受け止められる。反対に、だんだん歩けなくなってきたという高齢者に尋ねるときには、どうしたらよくなるかという話ばかりで、歩けなくなる中でどうするかということが話題にされることはほとんどない。むしろ高齢者に対してこそ、上ること、がんばることを求める世の中だ。
回復や改善を目指す情報があふれるのとは反対に、体は動かなくなるばかりだし、物忘れが進むのも避けがたい。世の中にあふれる情報と現実の体のギャップは広がるばかりで、「下り坂の支援」はますます理解されがたい。
しかし、よく考えてみてほしい。上るのは大変で苦しいことも多い。それに対して、下るのはがんばらなくても下っていけるし、その場の苦しさはかえって少ない。それにも関わらず、社会は高齢者にも上ることを勧める。いったいなぜか?
「上に登る」と「下に落ちる」。前者には希望があり、後者には絶望がある。そう考えやすい。もちろん、がんばることが将来の希望につながり、がんばらないことで将来に絶望をもたらすかもしれない。しかし今という視点に立てば、現実はむしろ逆だと言える。上るのは苦しく、下るのは楽だ。さらに将来の問題という点でも、最終的にはどんなにがんばっても死は避けられない。がんばった先に満足できる希望の死があるとも言えるが、がんばらず下る先にも、もうがんばらなくてよいという希望の死はある。下ることで現在の楽な状態を達成し、その先にも希望を抱くことができる。そんな生き方、死に方がある。
のんびりと下っていく生き方
ここで少し話題を変えて、休日をどうとらえるか考えてみたい。毎日しっかり働けるように休むのか、週末しっかり休めるように働くのか。あるいは、死ぬまで働けるようにがんばるか、年を取ったら働かず休むためにがんばるのか。私自身はといえば、働くためには休日が必要と思って長く働いてきたような気がする。しかし還暦を過ぎて、これまでがんばって働いてきたのは、これから十分休むためだったというのが今の正直な気持ちだ。
この「休む」は、「下る」ということの大きな要素ではないか。重力に従って降りて行けばいいわけで、物理学が示す通り「仕事」をする必要はない。さらに言えば、「老いる」とは、「仕事」をしなくても「下る」という「休む」生き方ができるということではないか。
上った後の下りをのんびり休みながら生きる。さらにどれだけ休みながら生きても、目的地には必ず到達できることがわかっている。死亡率が100%ということは、必ず死という行き先に達することができるということだ。これはがんばって仕事をしなければならない上りに比べて、ずいぶん気楽なものではないだろうか。この下ることの心地よさが、現代では失われている。ただその下りが、老いとともに転びやすくなって、転がる石のようではちょっと苦しい。そうならないように、赤ちゃんが世話をしてもらうのと同じく、誰もが介護・ケアを受けることができる社会が必要である。それは社会に対して、迷惑やうしろめたいことではない。生まれて、生き、死ぬという人の一生そのものである。
