【vol.12】一番いい薬は人だ | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2025/08/27
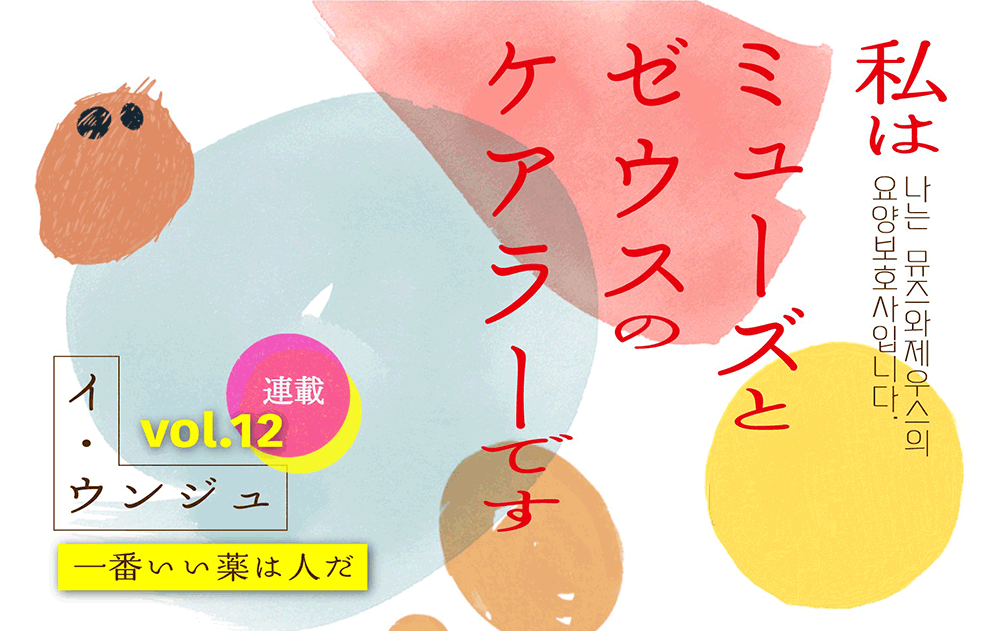
韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
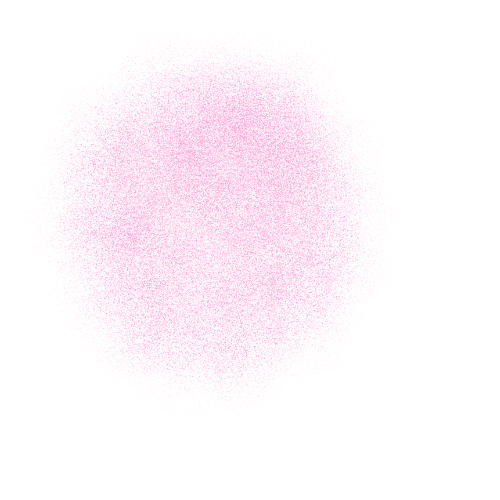 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
叔母の私と、祖母の手で育った甥は寂しがり屋だった。結婚できると期待して子供を産んだが、愛は去り一人で子供を育てなければならない状況になると、甥は彷徨い始めた。
私は認めざるを得なかった。非正規の仕事に就く甥一人の力で子供を育てるのは無理だということを。そして、決めなければならなかった。弟の子供たちの世話をしたように、甥の子供を安定した環境のなかで、愛をもって世話しなければならないということを。こうして孫との生活が始まった。
孫が肺炎を患い入院している間、10月に入ってすでに3回欠勤することになった私は、センターと相談して、土曜日も勤務することにした。
一人で子供を育てながら職場生活を送る際、子供が病気になるとどうすればいいのか。子供が入院でもしたら、生活全体が揺れてしまう。いや、子供に限らず家族の誰かが病気になれば、私たちの人生は、予測できない「非常警戒態勢」に突入することになる。キャリアが断絶した女性のためのプログラム「ビューティーライフ」の一環として始まったデイケア実習は、特別な事情なしに3回以上欠勤してはならない。
台風が来るというのに都市は雨に濡れた。
今日私が着ているエプロンは23歳から使っているせいか、もう体の一部に感じられる。エプロンをつければ私は何でもできる。エプロンは私の盾であり、人生を生きるための道具であり、絵の具を使う時は作業服になり、水に濡れた手を拭く時は古くなって柔らかい広々としたタオルの代用にもなる。このエプロンさえあれば私は怖くなく、おしゃれをしなくてもよくなり、市内のどこを歩いても格好がつく。
雨が降っているので、デイケアセンターの朝は忙しそうに見えない。
今日は坪庭には、7人のミューズとゼウスが集まった。できればミューズとゼウスの手を握って、膝を合わせて挨拶したい。普段目を閉じているゼウスのそばに近づき、洗礼名を呼ぶと微笑む。つい、指が1、2、3と、鍵盤を打つように膝の上で嬉しそうに動く。私と同じマンションに住むミューズとも挨拶し、息子が大邱(テグ)の職場に通っていると言うミューズとも挨拶を交わす。
土曜日だけボランティアに来るという青年とも目礼をする。ミューズたちの視線は青年から離れない。彼が部屋の主人公である。ゴッホの《ジャガイモを食べる人々》では、貧しい夕食の食卓に集まって座った家族の中で、背中をこちらに向けて座った中央の少女が希望であり、星のようであったが、ミューズたちにとってこの青年の存在は、成人になった孫のように心強い。
私に与えられた最初の任務は、軽い体操だった。初めてレクリエーションの進行を任せてくれた療養保護士の先生は、福祉士として勤務した時に、日本で見学した老人ホームが印象的だったという。エプロンからミニ鉛筆と手帳を取り出し、忘れないようにメモしておく。
「印象的だったのは、お年寄りの方の体の管理がしっかりしていて、太っている方が多くなかったんです。それはすなわち療養保護士がケアする時、肉体的な負担が少ないという意味もあります。そして、プログラムにそれほど縛られていません。個人の時間が多いということでしょうか。私たちのように大人数でプログラムを進めるというより、小さなグループに分かれて行うのが特徴です。講師の方も2、3人ずつグループについて、進行するので集中できますね。時間も10分から15分くらいと、長くありません。30分は超えません。排便や排尿といったトイレの問題もありますから」
隣国の老人ホームの長所を聞かせてくれた療養保護士が、ミューズとゼウスのそばに椅子を持ってきてくれた。
少し緊張するが、健康体操の時間にメモしておいた内容に一度、目を通してから始める。
「気功体操をするように手を一度合わせていただけますか?」
ミューズとゼウスのしわの寄った手が胸の前で合わさる。
「私が日本で留学していた時でした。貧しい家の娘にとって、家から送ってもらった生活費ではとても足りず、皿洗いのアルバイトを10時間働き、2時間しか勉強できなかった時代がありました。そんな留学時代、夜中に目が覚めて散歩に出かけたら、広い公園で日本のおばあちゃん、おじいちゃんたちが集まって体操をしているのを見つけました。夜明けの霧が立ち込めた森の中で、手をこうやって合わせるだけでも、体の悪い運気が出て、いい気が入ってきているという気がして、本当に不思議だった記憶があります」
ここまでは、大丈夫だったみたいだ。私は、何をするにしても最初の切り出しの一言が重要だと思う。ラジオDJがジングルを背景に番組を始める時や、仕事を終えて帰宅して家族と交わす最初の対話のような。
「今日一緒に手の体操をして、一番よくできた方には賞品があります」
エプロンのポケットから孫のおやつに買っておいた飴を取り出す。家から孫の飴を賞品に持ってきたと言うので、ボランティアに来た青年まで皆ケラケラと笑う。
「それでは、手を合わせて一度こすってみましょうか」
手をこすりながら私は話し続ける。
「年を取ると血行が悪くなるじゃないですか? こうやってこすると、体が温かくなる気がしませんか? 次は拍手を10回してみましょう。1、2、3。さて、これからは温かくなった手で自分の体を撫でてあげます」セルフ・リーダーシップ講師のチョン・ビキのメンタル瞑想で学んだことを応用する。
「頭をこのように撫でてください。 頭を撫でてあげながら、『〇〇さん、あなたは体が痛くて疲れているでしょ?』と、自分の体と会話をしてください。そして、このように言ってください。『これまで子供たちに勉強を教え、お金を稼いで、働いてきて本当にお疲れ様でした。あなたは素晴らしい』」
「次は、自分の頬を撫でてください。『今日は足も痛いし、腰も痛い、痛くないところはないけど、こうやって頬を撫でていると気分がいいんだな』。そして、自分の肩も抱きしめてください。肩を撫でながら、お腹も撫で、足も撫でる。最後に、足を撫でながらこう言います。『いつも子供の心配で大変だった。絶えないお金の心配も健康の心配もすべて外に出しなさい。心が疲れて痛かったでしょう? その疲れや痛みはすべて外に出しなさい』」
「これから最後に拍手を10回しますが、拍手をした後、誰が一番よくできていたのか指で指してください」
拍手をした後、各々の指が四方を指す中、本日のゲストである青年に飴を一つ渡すと、ミューズとゼウスはもちろん、飴を受け取った青年も何かに表彰されたかのように喜んでいた。
このようにして、短かったが私には長かったレクリエーションの進行が終わった。
昼食まであと20分ほど残っていたが、その残り時間に、奉仕しにきた青年は一人用ソファほどの大きなボールでレクリエーションを進行する。ミューズとゼウスのボール転がしの時間だ。ほとんど座って生活する方々には良いと思った。
居間の真ん中に大きなボールがころころ転がっていくと、おとなしいミューズが足を上げずに足首でポンと叩いてくれる。青年が居間の真ん中に置かれたボールを軽く転がすと、健康なミューズが再び青年の前までボールを蹴り、ボールは青年からゼウスへ、ゼウスからミューズへと、公平に軽快に、居間を転げ回る。
今日、私たちが転がすこのボールは、ミューズとゼウスが子供たちの心配や、健康への心配で曲がった背中を伸ばし、共通の遊びに積極的に参加することで、互いに共感し合える暖かい空気を作ってくれたのだった。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
