【vol.11】「キレイ」と言ってくれてありがとう! | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2025/08/19

韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
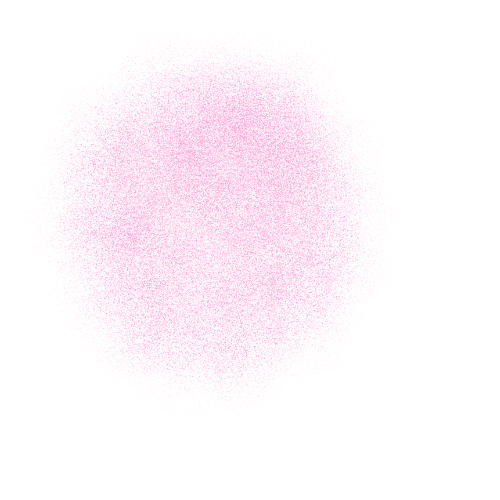 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
1.
一般的に正しいとされていることが、実は虐げる行為であることに気づいた。彼女はロックがかかった車椅子を無理に動かして、扇風機を倒したり壁にぶつかったりしている。はたまた、エアコンが作動している部屋のドアを閉じてしまう。一瞬もじっとしていられないミューズがうろつき回ることもある。排泄の介助やおやつの準備を手伝うケアラーは、ミューズとゼウスが危険にさらされないように見守りながら、仕事をしている。普通の人でもロックされた車椅子を押すのは難しいのに、老人の腕にはどれほど痛みが伴うのか。扇風機に指が挟まれたら大変だと思って、車椅子をロックして動かないように押さえていた私に、先輩ケアラーは言った。
「移動を妨げることも虐待とみなされますよ。自由に移動してもらい、保護することが私たちの仕事なんです」
時々天井に向かって叫んだり怒りしているミューズを指さし、もう一つのアドバイスをしてくれた。
「独り言を話している時は、放っておくのが一番です。長年の蓄積した感情を全て表現しなければならないから」
「この仕事は高齢者のケアが目的なので、単に軽く来てボランティアをするのとは違います。私たちも心が痛むものです。しかし、感情のコントロールも業務の一部です」
私は運よく才能のあるケアラーの先輩に出会った。親切で感受性が豊かであり、配慮の心を持ち、正確で適切に業務を行う姿を、いつも感心しながら見守っていた。忙しい業務の中、実習生である私にも気を配ってくれている。
レクリエーションの時間、ミューズとゼウスの皆さんを中央ホールへ案内する。一人で移動できるミューズが途中止まっていた。少し疲れているようだったので、私はミューズの車椅子を押してあげた。しかし、実はこれも良い方法ではないそうだ。リハビリが可能な方は、自分自身の力で食べたり、着替えたり、行動できるように支援することが優先されるべきだと聞いた。したがって、同情に近い配慮は実際には必要ないのである。
それでも私の行動が嬉しかったのか、ミューズが「ありがとう、他のケアラーたちは車椅子を押してくれないの。私は3人の子供がいて、全員大学院を卒業したの。食べることも着ることも知らないまま、全部子供の勉強に費やした」と自分の話を聞かせてくれる。
次に、一日中車椅子を押して徘徊する別のミューズが、レクリエーションテーブルに座れるよう手伝う。実習中、できるだけ多くのミューズと接するよう努めていたが、なぜかこのミューズにはなかなか近づけなかった。固く閉じた唇、美しい容姿、そしてこれまでの生活が容易ではなかったことを暗示する無表情な顔に刻まれた眉毛のタトゥーが、私を少し怖がらせた。そんなミューズが私に近づいてきて、先に話しかけてきた。最初は言葉の意味がはっきりしなかったが、何度も聞くと、次のような言葉だった。
「スイカを食べなさい」
先ほどケアラーたちのミーティングテーブルにスイカの皿がおいてあったからだ。
ああ、私はミューズの目線に合わせて座る。そして、彼女の頬を両手で包み込む。
「どうしてこんなにキレイですか? 目も美しく、鼻も美しく、口も美しい。全てが美しいです」
すると、しばらく私の顔を見つめた後、
「キレイと言ってくれてありがとう!」と答えてから、車椅子を押して去っていった。
2.
午後には、新しく入所されたミューズが家族と共に来られた。事務所で長い相談が行われている間、別のケアラーはミューズの手を握りながら、「ここが金さんのこれからの部屋ですよ。こちらはトイレ、そしてテレビもあります」と案内をしている。ミューズが生活する動線に沿って、繰り返し説明している間、ケアラーたちも新しく来られたミューズのための準備を開始している。ベッドの頭側に名前と注意事項を記入し、排泄活動が規則的かどうか、おむつが必要かどうかについてもチャートを見ながら相談する。
年齢は58歳、元デザイナー。強いストレス。何らかのショックで記憶喪失。
ついに保護者と別れる時間が迫ってきた。福祉士たちの忙しさを見ると、ミューズへのサービスを提供するために今後準備すべき点が多くあるようだ。
結局、実習生である私に、新しく入ってきたミューズを守るよう指示が下される。他のミューズ同様、この方にも極端な“徘徊”の傾向がある。めまいがするほど、吐き気を催すほど、ぐるぐると廊下とホールを徘徊するのを、手を握ってついて回る。数十周目だ。
私は手を握りながら歩く間、ミューズとは思えないほど若い「ボブカット」の彼女を観察する。限りなく澄んだ目をしている。整った口元、粗い仕事はしてこなかったような柔らかい手。そんな彼女が、女子学生のように私の手を握り、たどたどしく歩いている。歩きながらつぶやく。
「ああ、うんざりだ」
私は「うんざりだ」と言う人が、こんな優しい口調で話すのを初めて見た。彼女には似合わない言葉が次々と出る。「気が狂いそう」と繰り返す。独り言を言う彼女の手を握り、壁に掛かったマティスの絵を指さす。
「マティスの絵を見てください。人々が踊っているように見えませんか?」
私はもう歩きたくなかった。足も痛く、のども渇いていた。年配の方もおそらく同じだろう。鼻に掛かった角型の眼鏡を直しながら、彼女も私と共に絵に一瞬目を向けた後、また歩き始める。私の手を強く握り、今では私の腕に彼女の腕が掛かり、私を頼りながら歩いている。私は再びゴッホの絵の前へ引き寄せ、試みる。同じだ。今回は美しい模様の肘掛けがある木製のベンチを手のひらで叩き、注意を喚起する。
「ここで少し休んでから行きましょう」彼女も一緒に座る。ぼんやりと窓の外を眺めながらため息をつく。お金の話もする。
何かが彼女の記憶を短期間で消し去ってしまったのだろう。こんなに健康そうに見えるのに、こんな風に記憶が消えたまま、10年、20年、30年を生きなければならないとしたら、どうすればいいのだろう。私はまた泣いてしまう。流れる涙を止められない。彼女がぼんやりと私を見つめ、一言言う。
「泣かないで」
ああ、私はあなたのために今、泣いているのです。あなたの夜と昼のために。それでも今、私を慰めてくれるのですか。
私は呪文をかけたい。彼女の傷が軽くなり、やがて笑ってここを出るように。私は精神ショック療法を使いたい。彼女が自分の世界から抜け出し、再び人生を抱きしめるように。しかし、私はそれをできないことも知っている。もしかしたら、その涙は彼女のためでも、私の無力さのためでもなく、暑さで疲れて出た涙だったのかもしれない。
通りかかったケアラー先生が、私たちのベンチに座る。私の様子を心配そうに眺めながら、自分の話を語り始める。
「私はもう泣く涙もありません。両親は皆亡くなり、夫もあの世へ行ってしまいました。」
そして用事があるため急いで通り過ぎる別のケアラーを指さし、「あの人も夫が亡くなって一人で暮らしています。」と語る。
そうだった。初日、ナザレのイエスに似た裸のミューズを見て泣いていた私に「ああ、この方も何か事情があるのだろう」と言ったのだ。
ついに、家に帰る時間になった。ケアラーの崔先生に新しく来たミューズの手を渡す。崔先生もお年寄りと一回りして戻ってくる。私に近づくと、嬉しそうに微笑みながら手を差し伸べるミューズ。
「もうわかったようです。新しくやってきたのなら、ここが自分の家だと思って新しい生活を始めるんだということを」
家に戻る私を見送る崔先生とミューズに対して、私は何度も振り返って挨拶をする。
暗い廊下を抜け出すと、明るい光が差し込むホールに立っている二人のシルエットが、光の中に吸い込まれていくようだ。
やはり実習が終わった後、ボランティア活動を申し込んで、ミューズを再び訪ねに来るべきだと感じた。ミューズの安否が心配だ。夜中じゅう歩き回るミューズの足が心配で、午後中ずっと握っていた柔らかい手が恋しくなる。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
