住まいの支援‐考え方と取組み 居住支援って何? 第11回 住まい支援のネットワーク
2025/08/05
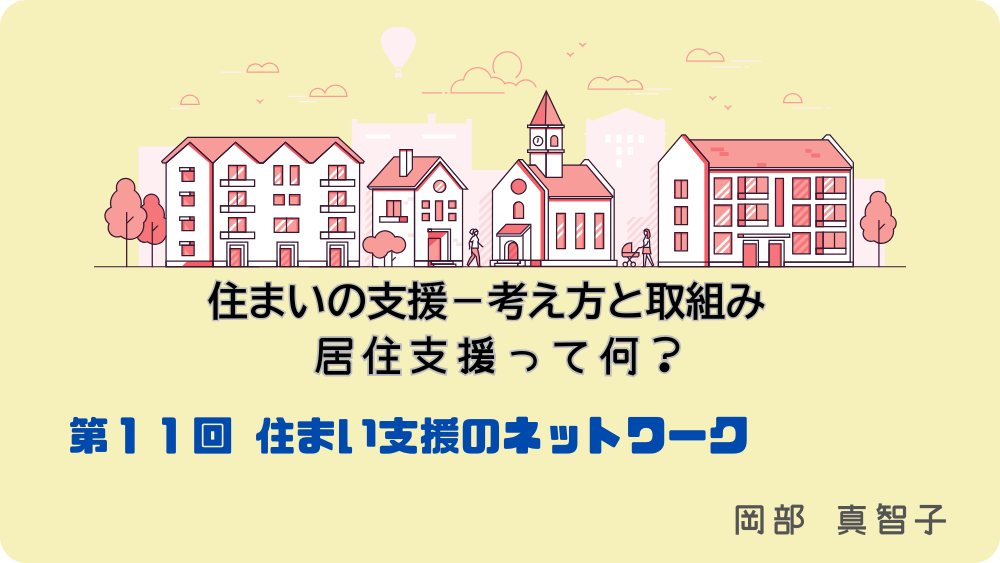
著者岡部 真智子(おかべ・まちこ) 地域で安定的な居住継続を支える研究を続けている一方で、社会福祉専門職養成に関する研究にも力を入れている。 連載にあたって人が生活を営む場となる住まいは、安全・快適で安心できる環境であることが求められます。 住まいは、食べる、寝る、くつろぐ、身をまもるための拠点となることはもちろん、住所があることは、福祉サービスや行政サービスを利用する際の絶対条件となります。 |
現在、住まい支援の担い手がつながるネットワークは各地でつくられ、住宅確保要配慮者への支援を支える基盤となっています。
住まい支援のネットワークとは
住まい支援は、福祉の専門職と不動産会社が連携するだけでなく、さまざまな人の関わりの下で行われます。それは、住まい支援(居住支援)には、住まいを確保する支援だけでなく、「住み続け」のための支援、住まいから退去するための支援など、さまざまな段階があるためです。
住まい支援に関わるさまざまな人や専門職が地域の中でつながる、つまりネットワークを築くことで、住まい支援を円滑に進めることができます。
住まい支援ネットワークの構成メンバー
不動産事業者、福祉専門職
地域で住まい支援のネットワークを構築する際、参加するメンバーとしてまず挙がるのが、不動産事業者と福祉専門職です。
住まいを確保する時点において、物件を貸してくれる不動産事業者の存在は重要ですし、本人に伴走しながら物件探しを行ったり契約を支援したりする福祉専門職の存在は欠かせません。福祉専門職の役割を、居住支援法人が担う場合もあります。
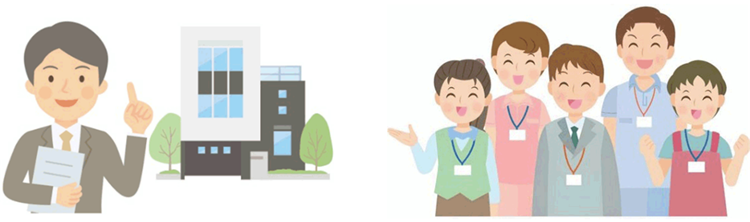
医療・福祉サービス、消防・警察
住まい確保の後、安定して住み続けるためには、本人の生活を支える医療や福祉サービス事業者の存在も大切です。あわせて、制度に基づかない支援者や支援団体(例えば、見守りをしてくれる近隣住民や食糧支援を行うフードバンク)などがあれば、生活を支えるネットワークを重層的なものにすることができます。
また、家の中で倒れているのを発見した時には、消防や警察に連絡することもあります。消防と警察にはどのような役割の違いがあるでしょうか。住まい支援を行う人同士が普段からつながり、その役割を知っていることで、緊急時の対応も速やかに行うことができます。

特殊清掃事業者、死後事務の担い手
住人が家の中で亡くなり、それがしばらく発見されなかった(いわゆる孤立死が生じた)時には、特殊清掃事業者が入ることがあります。
住まい支援を行う人が賃貸住宅で特殊清掃が行われる場合の費用や清掃内容についてあらかじめ知っておくことは、生前に見守りを行うことの大切さを認識することにもつながります。
身寄りのない方が亡くなった場合、その後の対応を行う人にはどこに連絡をすればよいのか、葬儀はどうするのかなど検討の必要が生じます。もちろん、身寄りのない人自身が、自らが亡くなった時のことを考えどこかに相談しておきたいという場合もあります。こうした内容の助言を得られるのが死後事務を行う事業者や葬儀会社です。
人はいつか必ず最期を迎えますから、その時のことを考えて事前に情報を得ておくのも大切なことです。

弁護士、司法書士
持ち家を手放す時や相続が発生する時、あるいは賃貸住宅入居中に家賃滞納が続いた時には、弁護士や司法書士の力を必要とすることもあるでしょう。
住まい支援を行う人たちが、弁護士や司法書士らと顔が見える関係を築いておくことで、法的な問題が生じた時、あるいは生じるおそれのある時に相談がしやすくなります。

ネットワークメンバーのつながり方
住宅確保要配慮者の支援を行うにあたり、すべてのメンバーがネットワークの構成員として積極的に関与する必要はありません。住宅確保要配慮者の状況に合わせて関わるメンバーは変わりますし、また関わりの濃淡や時期も異なります。
大切なのは、住まいの支援に関与する人たちが、互いに地域の中で顔見知りの状態で、互いが何をしているのか、どのような専門性を有しているのかを知り、何かあった時には相談できる関係にあるということです。
また、それぞれが使う専門用語や大事にする価値観に違いがあるため、違いを知っておくことや、わからないことを気軽に聞ける関係を築くことが大切になります。
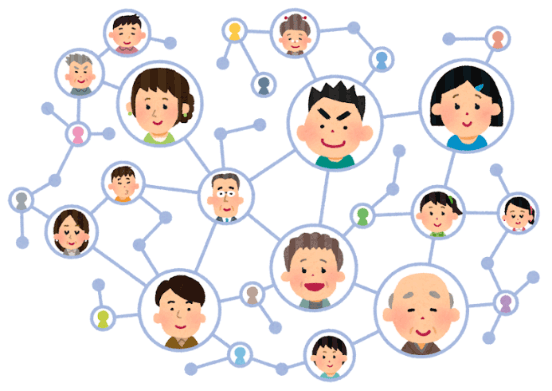
人口4万人ほどのある市では、居住支援の勉強会を進めるにあたり、住まい支援に関わっている多くの専門職・団体に参加を呼びかけました。
勉強会の参加者には、不動産会社、司法書士、特殊清掃業者、居住支援法人や福祉サービス関係者、葬儀会社、(一般の)清掃業者、行政の福祉部局、住宅部局の担当職員、警察官、消防署員が含まれていました。
普段から接点があり、すでに顔見知りの人もいましたが、多くは初めて会う状態でした。互いに自己紹介をして、それぞれの仕事内容について質問をすることで、住まい支援においてそれぞれの役割が見えてきました。また、他の人の仕事内容を知ることで、困ったときにどこに連絡をすればよいのか、必ずしも自分だけで対処しなくてもすむことを知ることができました。
人の異動もあるため、このように互いを知ることができる機会は、1年に一回程度あることが望ましいでしょう。回を重ねる中で、単なる顔見知りの関係から一緒に住まい支援を担う仲間としての意識が醸成されます。また、つながることで「自分の仕事が進めやすくなる」と感じると、会に参加する意義が理解でき、ネットワークをさらに強く・太くしていくことも可能になります。

公民協働の住まい支援のネットワーク ― 居住支援協議会
住まい支援に関わるネットワークは、現在、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下、居住支援協議会)という形で都道府県単位、市町村単位で設立が進められています。
居住支援協議会は、住宅セーフティネット法に位置づけられ、2024(令和6)年の法改正ではその設置が地方公共団体の努力義務となりました。
2025(令和7)年3月31日時点、すべての都道府県に居住支援協議会が置かれ、市区町村では155協議会が設立されています。お住まいの地域に居住支援協議会があるかどうかは、
国土交通省のホームページ
に掲載されていますので、こちらをご覧ください。
おわりに
地域には、すでに住まい支援に関わる多くの担い手がいますが、それぞれが個別に活動をしているのが現状です。担い手同士をつなぎ、そのつながりを地域レベルに広げ、それぞれが担っている役割を互いに理解し活用していくことで、住まい支援のネットワークが地域でつくられていきます。
では、このようなネットワークは、誰がどのようにつくっていくものでしょうか。それについては、次の回(最終回)でお伝えしたいと思います。
