【vol.9】一晩中砂漠を歩いたのだ | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2025/07/16

韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
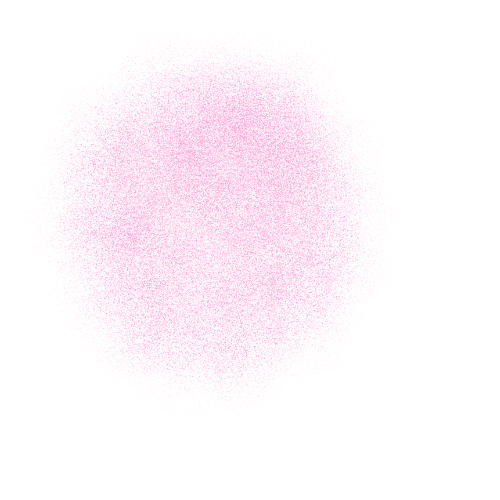 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
同僚と私は、前立腺癌で死線をさまようゼウスが目を覚ますと、心配そうに見下ろしていた。次の日も次の日も、褥瘡のあるゼウスの速い脈拍と痰の絡む音に、同僚と私は神経をとがらせ続けた。
消化機能に障害を持つゼウスは、抗がん剤やパーキンソン関連の薬、痰に効く薬が、多すぎるほど服用していた。耐性ができているため、高齢者はほとんどが薬を強めに処方されるという。経鼻経管食を注入する場合には、必ず事前に消化の有無を確認するため、ホースを通して注射器で胃液を検査する。ゼウスには1回の経管投与しかしていない。
――業務日誌に書く。「消化が悪いので昼は経管投与をせず、水と薬だけ投与した。夕方にもまだ昼に投与した薬が残っていたので、経管はもちろん薬も投与せずに、2時間に1回チェックして、夕食を与えることにした」という内容である。
最後のおむつを替える間、夢中で寝ていたゼウスが目を開けて一言投げる。
「きれいだ、したい」
私は自分の耳を疑う。「聞き間違えだろう」と、夜勤明けの同僚に業務伝達をした後、ゼウスのベッドサイドで同僚と私は彼の消化機能障害を心配し、今夜脈拍が速くなって緊急事態が起きないことを願う。そんな私たちの心配に応えるかのように、ゼウスはかろうじて目を開けてこう言う。
「恋愛しよう、したい」
私の聞き間違えではないんだなと苦笑いする。同僚が叱る。普段なら私もかっと怒ったはずなのに笑いが出る。
ベッドの片隅に腰掛けて、ゼウスと目を合わせる。
「おじいさん、もうすぐ死ぬかと思って心配したのに生き返ったんですね。死ぬから薬も食べないし、経管食も食べないって言ってたのに」
ゼウスは100万ドルの笑顔を見せる。
「おじいさん、おばあさんはいつ亡くなりましたか?」 私が聞く。
「つい最近だ」
「えっ、つい最近なのにそんなことを言うんですか?」私がまた尋ねる。
ゼウスがまた笑う。 少し恥ずかしそうにさえ見える。
ハハハ。憎くないし、怒らない。むしろよかったという気持ちだ。こんな気持ちになるのが不思議なだけだ。
ゼウスは今夜も砂漠の遭難者のように、生と死を行き来するだろう。蜃気楼が見え、幻聴が聞こえ、汗に濡れて寒さに震えるだろう。
水を一口も自分で飲むことができず、少し前までは絶望して死にたがっていたゼウスの笑顔を後にして、五種競技を終えたばかりのような私は、春風に吹かれながら二つの停留場を歩いてバスに乗る。
ゼウスのほっそりした頬が、笑いでさらに深くへこんで、病色が濃く見えた。そんなゼウスが自分の欲望を言葉で表現できた瞬間、先に逝ってしまった妻に少し申し訳なさそうになった瞬間があったからこそ、今夜、ゼウスは砂漠の真ん中で自分を待っている家族の元へ歩み出すのができるだろうと私は信じている。
息子に、娘に、父がまだ生きているから君たちは孤児ではないと、君たちの顔を見るために一晩中砂漠を歩いたのだと。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
