【vol.8】世の中に娘を嫌う母親はいないでしょう | 私はミューズとゼウスのケアラーです
2025/07/01

韓国の介護現場で働く作家が送るケア文学
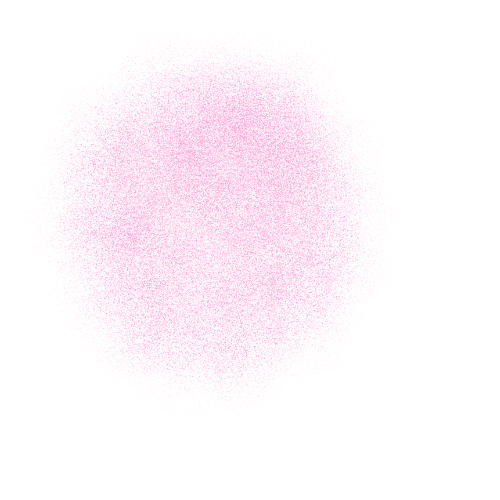 激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
激しいスピードで高齢化が進む隣国で、 ケアの最前線に立つ作家による、初の日本語エッセイ連載スタート!! 昼は介護の仕事をして夜は文章を書く、作家イ・ウンジュの連載が始まります。日本の介護福祉士にあたる、「療養保護士」という韓国の介護の国家資格を持つイ・ウンジュさんは、自身もケアの現場に立ちながら、ケアに関する文章を韓国語で発表する数少ない作家です。
-
そんなイ・ウンジュさんは韓国で、ケアについてのエッセイ三部作(『私は神々の療養保護士です』『こんなに泣いて疲れたでしょう』『東京因縁』)を出版して話題を集め、2023年には母親の在宅療養保護の経験を盛り込んだ『ケアの温度』を刊行しました。ケア三部作の『私は神々の療養保護士です』では、療養保護士として歩んだ療養院での日々から訪問介護に至るまでの道のりについて、『ケアの温度』では、誰かをケアする時の適切な距離感・温度感とレジリエンスについて、やさしい筆致で綴っています。この連載では、イさんの目に映った韓国の介護現場から、「ミューズとゼウス」のためのケアについて考えます。
老人ホームで娘を待ちながら一晩中歩き回る「スプラウト(新芽)のミューズ」がいる。歩き疲れるとベッドにしばらく座り、そしてまた起き上がって歩き出す。娘が自分を待っているという。
ミューズの片方の手を握り、痩せた肩をくるっと回し、ベッドの方向を示した後、私もヨガマットを敷いて横になる。
寝転んでじっとお互いを見つめ合う。 また立ち上がろうとする「スプラウトのミューズ」に声をかける。彼女が好きそうな話題はなんだろう。
「私は、ママがお父さんに似ているって可愛がらないので、どっかから拾われたのかと思ったわ。ママが、実は継母なのかと思った」
「いいえ、そんなお母さんはいないわよ。無愛想だからそう言うだけ」
家に置いてきた娘の心配ばかりしていた「スプラウトのミューズ」の確信に満ちた言葉に、眠気が一気に吹き飛ばされた。
「私はまだ娘とチューしてるわよ」
「スプラウトのミューズ」が誇らしげに私を見て、言う。
「そうなんですね。あんなに可愛い娘を家に置いてきて、娘のことばかり心配していたんですね。世界中の娘が聞きたい良いことを言ってくれて、本当にありがとうございます。この世に娘を嫌うお母さんはいませんよ。ただ無愛想なだけです」
「そんなことしちゃいけないのに、子供みたいにこっそり行かなきゃいけないのに」
娘は自分を追いかけようとする「スプラウトのミューズ」を振り切ってエレベーターに乗り込んだ。私は思わずつぶやいた。
12歳年上の同僚と私は、梨に袋をかぶせるように、ゼウスのそこにかぶせるおむつ袋を作る作業をしながら、その様子を眺めていた。
「私は娘に頼んでおいたんだ。1週間に1回はお母さんに会いに来て、服を着替えたり、爪を整えたりしてね、って」
「私はお母さんにそうしてあげられなかったわ、忙しくて。今ならちゃんとやってあげられるのに、あのときは知らなかったから、後悔している。今でもママが恋しいよ」
おむつ袋を作りながら、同僚と私は、おしゃべりをするのが日課になっていた。
「私は働く母の代わりに、祖母が育ててくれたんです。祖母は、認知症で3年間苦しんでから亡くなりました。3年間、イモ(*母の妹)が祖母の世話をしました。イモは私に、あなたも祖母が育ててくれたし、祖母の娘と同じだから、週に1回は祖母の世話をしろと言われ、日曜日は私が祖母の世話をする当番でした。車椅子で散歩をしたり、お粥を食べさせたり。祖母が亡くなられて、しばらくは一緒に死にたくなるくらい祖母のことが恋しくてたまりませんでした。だから、おばあちゃんたちにたくさん会えるケアラーになったのかもしれません」
「そうなの?」
同僚の先生は、おむつ袋を作っていた手を止め、私の目を見つめた。
「Jさん、辞めたら私は寂しくなるわよ。」
12歳年上の同僚の瞳からの真摯な眼差しに、私は少し照れた。
私の美しい同僚は鈍感で、あれこれと他人を評価することもなく、やるべきことを黙々とこなすだけで、周囲を陽気な空気にすることができる。きわめて素直で魅力的な女性である。私は、彼女からゼウスとミューズにするすべてのケアを学んだ。彼女は暇さえあれば、おむつ替えの際の腰を痛めないノウハウや、お尻についた便をどのようにきれいに取り除き、血行を良くするかを教えてくれた。おむつを交換する彼女の手つきは、ピアノの鍵盤を弾く奏者の手のように熟練していて、リズムがあり、何よりも正確だった。
私は、彼女と一緒に仕事をするのがとても楽しくて、腰の痛みさえ忘れることが多かった。私たちは時間があるたびに、少しずつ自分の話をすることができた。
無表情で、自分の感情をうまく表現しない彼女から「ママが恋しかった」という言葉を聞くとは思わなかったが、ゼウスとミューズの世話をしていた様子を思い出すと、彼女もママを悼みながら仕事をしていたのだろうと思った。
母が病気になったとき、自分は忙しくてできなかったケアを、知らなかったからできなかったケアを、彼女は悔しがっていた。介護士になって母にこうしてあげられる、ああしてあげられたということに気づいたときの、「母が恋しくなった」という言葉も手帳に書いておかなければならない。
最後の勤務を終えて、私は12年年上の同僚であり、ある意味では、この数ヶ月間私の羅針盤となった、人生の師匠である彼女と別れるのがとても残念だった。
そんな気持ちが通じたのだろうか。夜勤を終えて、最後の朝食を食べようとしていると、彼女が家から持ってきたおかずを並べ出す。
「トドックイ(蔓人蔘焼き)だよ、食べてみて。私が手で全部剥いて、味付けしたんだよ、一緒に食べよう」
朝食を済ませ、元気よく老人ホームのドアを開け、未知の世界への冒険に出かける覚悟を固めた私は、心の揺らぎがした。こんなに大切な気分にさせてくれる仲間と別れるのがとても寂しかった。
家から持ってきたごはん茶碗1つ、お箸、スプーン1組を荷物に入れて、挨拶をして出て行くと、彼女はエレベーターが7階に止まるまで、そばにいてくれた。そしてエレベーターのドアが開くと、私を軽く抱きしめてくれた。一瞬の出来事だったが、エレベーターのドアが閉まって一人になったとき、彼女の別れ際の抱擁がどれだけの励ましと別れの惜しさを含んでいたかを感じ、涙が出た。
金魚のような瞳をキラキラと輝かせながら家に戻った。足音一歩一歩に、惜しいという感情がスタンプのように押されていくのを感じた。
痛み。
別れってこんなにも悲しい気分になるんだ。まるで、初めて感じる感情のように新鮮だった。
著者紹介
イ・ウンジュ 이은주

1969 年生、作家、翻訳家。日本に留学し、1998 年に日本大学芸術学部文芸学科を卒業。20 代から翻訳家になることを夢見て、家庭教師として働きながら翻訳した『ウラ読みドストエフスキー』(清水正)で夢をかなえる。その後も仁川国際空港の免税店で働きながら、休憩時 間は搭乗口 31 番ゲートで訳し、仁川への通勤電車でも訳し続け、『船に乗れ!』(藤谷治)、 『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(山極寿一)をはじめ、十数冊もの日本書籍を韓国に広める。おばあちゃんっ子だったイさんは祖母の逝去をきっかけに、高齢者施設でボランティア活動を始め、その後療養保護士の資格を取得。昨年からは認知症になった実母の介護を行う。「ケア」と「分かち合い」について、文学の一形態として追及してみたいという気持ちから、高齢者のケア現場についてのエッセイを三部作で発表し、韓国で共感を呼ぶ。現在、
