住まいの支援‐考え方と取組み 居住支援って何? 第9回 住まい支援の実際
2025/07/22
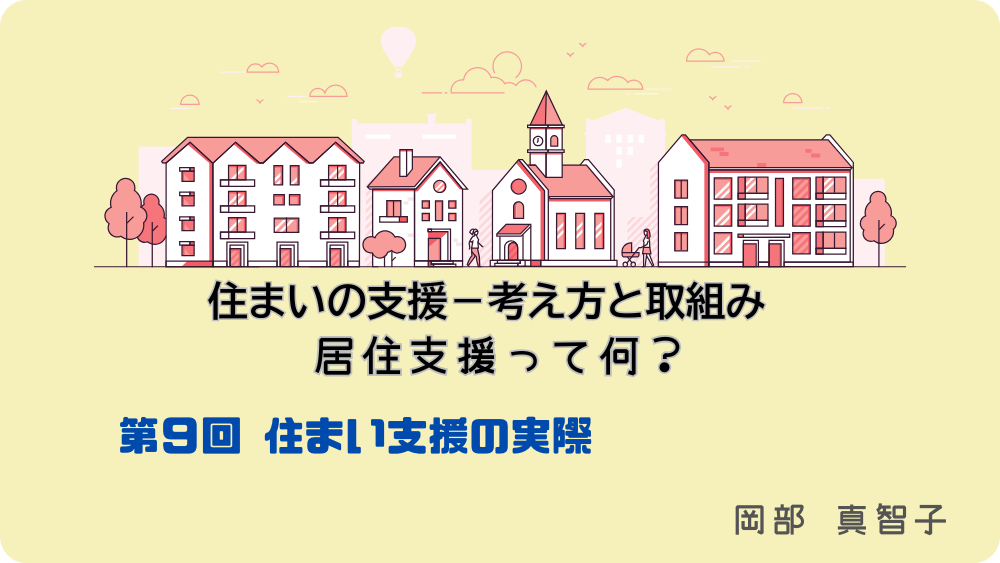
著者岡部 真智子(おかべ・まちこ) 地域で安定的な居住継続を支える研究を続けている一方で、社会福祉専門職養成に関する研究にも力を入れている。 連載にあたって人が生活を営む場となる住まいは、安全・快適で安心できる環境であることが求められます。 住まいは、食べる、寝る、くつろぐ、身をまもるための拠点となることはもちろん、住所があることは、福祉サービスや行政サービスを利用する際の絶対条件となります。 |
これまで、住まいの種類の多さや、住まいと私たちの暮らしとの関係に触れ、住まいに関する支援をさまざまな角度から捉えてきましたが、今回は、実際に住まいに困っている人への支援の事例を2つご紹介します。
ここでは、「居住支援」を、住まいに関する課題を抱えている方に対する、①住まいに関する相談、②物件の紹介・内覧同行・家賃債務保証等の入居前の支援、③見守り・トラブル対応・残置物処理等の入居中(退居時)の支援を、連続的・一体的に提供する取組みとして考えます(
居住支援協議会設立の手引き作成委員会「居住支援協議会設立の手引き~居住支援協議会 はじめの一歩~」
)。
なお、紹介する事例は架空の事例であり、実在するものではありません。
精神障害のある人への居住支援
40代女性のAさんは、アパートで一人暮らしをしていました。
20代の頃より統合失調症を患い、受診をしながら安定した暮らしを送っていましたが、半年ほど前から容態が悪化し、定期的に受診していた病院への通院も途絶えてしまいました。
ある日、同じアパートの住民から、「Aさんが朝早くから大音量でテレビをつけている。ベランダから物を投げているため何とかしてほしい」と、不動産会社に連絡がありました。
不動産会社の社員がAさん宅を訪ねてみると、テレビの大きな音が家の外にまで聞こえてきました。そして、ベランダの外には、ゴミのようなものが投げられているのを見つけました。不動産会社の社員は、連絡の内容が事実であることを確認し、Aさん家を訪れ、「音を小さくしてほしい」「部屋の外にものを投げないでほしい」と伝えました。
その後も、同じアパートのほかの住民から何度か不動産会社に連絡が入ったため、不動産会社の社員は再びAさん家を訪問し、「同じことが続くようであれば、アパートを退去してもらうしかない」と話しました。
それでも、Aさんの同様の行動は続きました。

不動産会社から市役所への連絡をきっかけに
Aさんの様子がおかしいと感じた不動産会社は、市の障害福祉課に連絡し、一部始終を伝えて相談をしました。相談を受けた障害福祉課の担当者は、Aさん宅を訪れ、Aさん本人と家の中の様子をみて、「早急に医療機関を受診したほうがよい」と考えました。そこで、Aさんが半年前まで受診していた病院を聞き、病院の相談員に相談をしました。
Aさんの様子を知った病院は、「早期に入院が必要である」と判断し、Aさんは入院することになりました。また、入院にあたってそれまで住んでいたアパートは退去することになり、遠方に住む姉がAさん宅の片づけを行いました。

退院後の住まい確保
Aさんは、3か月ほど病院に入院して療養したことで、落ち着いた様子が見られるようになりました。病院の医師からも「通院するのであれば、退院しても構わない」と言われました。
病院の相談員がAさんに退院後の意向を確認したところ、Aさんは「元の家に戻りたい」と答えたため、相談員はアパートを管理する不動産会社にその旨を伝えましたが、「前のように問題を起こされると困るので、絶対に入居させられない」との返事がありました。
相談員は別の不動産会社にもAさんの入居の相談をしましたが、2社から同様の理由で断られてしまいました。しかし、3社目のX不動産店は、社長の身内に精神障害を持つ人がいたこともあり、Aさんの入居に理解を示してくれました。
そして、Aさんがきちんと受診を継続すること、何かあった時には支援者が必ず対応することを条件に、入居が認められました。
相談員とAさんは、病院からの外出の許可を取り、X不動産店が紹介してくれた物件をいくつか見て回りました。その中にAさんが気に入る物件があり、無事に入居できることになりました。

退院後の生活
Aさんの退院にあたり、相談員は支援担当者会議を開くことにしました。相談員はAさんと相談の上、退院後に利用することが望ましいと考えた訪問看護ステーションの職員や地域活動支援センター(※1)の職員に呼びかけ、病院の医師にも参加してもらい、支援担当者会議を開きました。
その結果、退院後には訪問看護が定期的に入ること、日中の活動の場として地域活動支援センターに通うことが決まりました。そして、何かあった時には病院の相談員が対応することとなり、そのことがX不動産店に伝えられました。Aさんの姉は「経済的に余裕がないから保証人にはなれない」と言いましたが、緊急連絡先になってもらうことができました。
退院後、Aさんは定期的に通院しており、訪問看護師による服薬管理も行われています。また、地域活動支援センターに通い、そこで新たな友人ができました。Aさんは、環境を整えたことで安定した生活を営むことができています。

刑務所出所者への居住支援
窃盗を繰り返し、これまで2回刑務所に入った過去がある70代の男性Bさんが、3回目の出所に際し、地域生活定着支援センター(※2)の支援を受けた事例です。
刑務所に入ったいきさつと生活歴
地域生活定着支援センターの担当者(以下、担当者)が、Bさんにこれまでの生活を聞き取ったところ、若い頃から建設現場で働いてきたそうですが、50代後半に事故で腰を負傷してからは現場での仕事ができなくなってしまったようです。
20代で結婚をして子どもも設けたものの、30代で離婚してからは、妻や子どもとの接点は全くなくなっているようです。また兄がいましたが、その兄も5年ほど前に亡くなり、身寄りといえる人は一人もいない状態となっているようです。
その後、日雇いの仕事で食いつないできたものの、60代で大病をしてから仕事ができなくなり、何度か飲食店で無銭飲食をしたことで、刑務所に入ることになったそうです。
Bさんは、刑務所を出所した後、更生保護施設(※3)に入所したこともありましたが、仕事が見つからず、施設を出た後は無銭飲食をして刑務所に入る、そうしたことを繰り返していました。
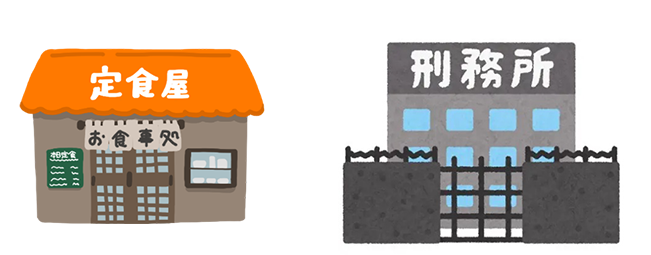
出所後の住まいの確保に向けて
Bさんは、刑務所を出所する前から担当者と面談を行い、出所後は「生まれ育ったY町に戻りたい」と話していました。しかし、Bさんに親族はなく、実家も取り壊され、帰る家はありません。また、貯金もなく金銭的にも困窮している状態です。
そこで担当者は、生活保護を利用することについてBさんの同意を取り、Y町の福祉課に生活保護について相談したところ、受給できる見込みが立ちました。

次に担当者は、Y町の不動産会社に、家を探しているBさんの代理で来たこと、Bさんがこれから生活保護を受給する予定であること、Y町内の住宅扶助の上限3万円以下の家賃の物件を探したい旨を伝えました。
不動産会社からは、「その金額で入居できる物件はあるが、緊急連絡先となる人を必ずつけてほしい」と言われました。
Bさんには緊急連絡先になってくれるような親族や知人はいません。そこで、担当者は、Y町にある居住支援法人に緊急連絡先について相談しました。
居住支援法人からは、Bさんの生活の見守りをしてくれる人がいることを条件に、「緊急連絡先になってもよい」と返事をもらいました。

再犯を繰り返さない、「住み続け」のための支援
担当者は、Bさんに、生活保護を受給できそうであること、家も見つかりそうだが緊急連絡先が必要であること、生活の見守りをしてくれる人がいれば居住支援法人が緊急連絡先になってくれると言われたことを説明しました。
Bさんは、出所後の住まいが見つかりそうだと聞いて喜びましたが、「見守りといって誰かに見張られた生活は送りたくない」と主張しました。
Bさんの身体は不自由ですが、なんとか自立した生活はできるため、介護保険サービスを使うこともできません。担当者は、どうしたらBさんが納得した中で見守りができるか悩みました。また、「Bさんが出所後の生活を送る時には、人とのつながりのある中で生活してほしい」と願っていました。

担当者がY町について調べてみたところ、市民農園があり、農園を借りている人たちでグループを作ると、グループを対象に講習会を開いてくれるということがわかりました。
Bさんにそのことを話したところ、「農園で作物を育てることに興味がある」「講習会に参加すればいい野菜がつくれるだろうから、グループのメンバーになる」と了解してくれました。
担当者は、居住支援法人に市民農園のグループを通じて見守りができることを説明し、緊急連絡先となってもらうことができました。またその結果、不動産会社から家を借りることもできました。
その後、地域生活を送るBさんからは、「農園で畑仕事をすることや農園のグループメンバーと作物の育て方について話をすることが毎日の楽しみである」といった話を聞くことができました。
Bさんは、以前のように無銭飲食をすることもなく、穏やかな生活を送っています。

おわりに
2つの事例を見ていただきましたが、共通するのは、複数の人が関わり、その人たちがつながりながら支援を行うことで住まいを確保し、その後、安心・安定した「住み続け」ができているということです。
では、そうした支援のつながりは、どうしたらできるのでしょうか。
次回は、住まい支援の地域への広がりに着目します。
※1 地域活動支援センター
障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活し、社会参加や自立を図れるよう、日中活動の場を提供し、生活訓練・就労準備・仲間づくりなどを支援する福祉施設(通所型サービス)です。
※2 地域生活定着支援センター
刑務所・少年院などの矯正施設等を出所・退所(退去)する高齢者や障害者など、福祉的支援を必要とする人が地域で円滑に生活できるよう、福祉サービスとの橋渡しを行う支援拠点です。
※3 更生保護施設
刑務所を出たばかりで住まい・仕事・生活基盤が不安定な人を一定期間受け入れ、宿泊・食事・生活指導・就労支援などを行いながら社会復帰を後押しする民間の社会内処遇施設です。
