死をことほぐ社会へ向けて 第12回
2025/07/11
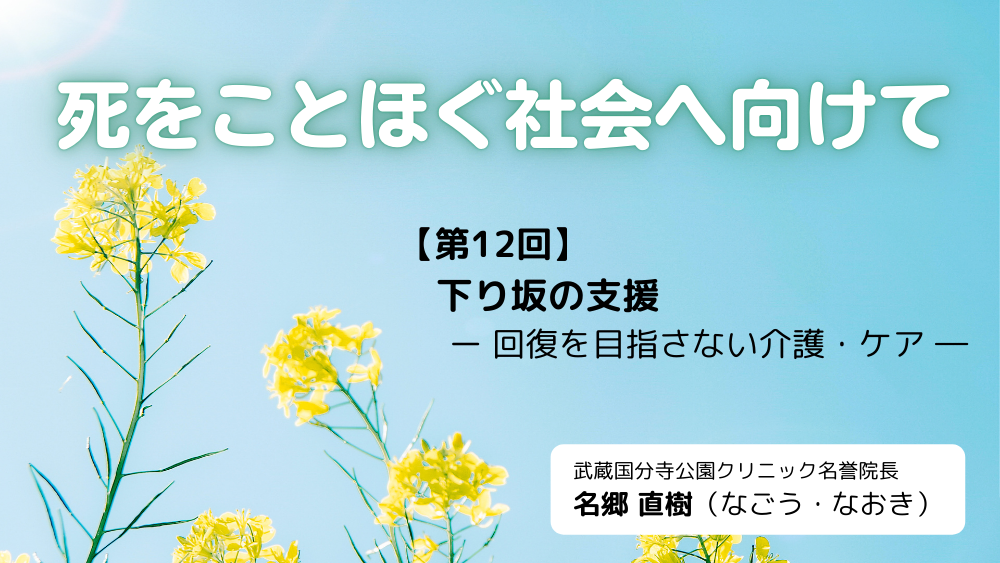
下り坂の支援 ……回復を目指さない介護・ケア
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
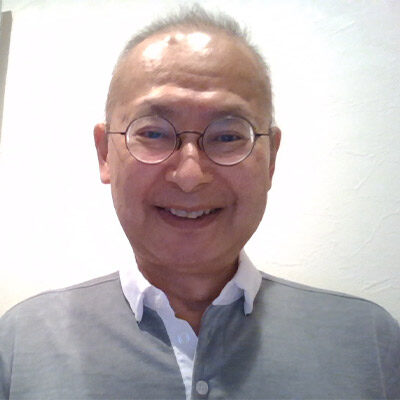
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
2025年7月に『名郷先生、臨床に役立つ論文の読み方を教えてください!』(共著、日本医事新報社)が発売!
YouTube
X
支援という言葉から連想するものは、どんなものだろうか。例えば自立支援という言葉がある。それに対して他立支援という言葉はない。そもそも「他立」という言葉はないかもしれない。『新明解国語辞典』(三省堂)を引くと「他律」「他力」という見出し語はあるが、「他立」はない。しかし支援自体は将来の自立を目指すとしても、その場は他立がスタートである。
支援が必要になるのは自立が困難だからだ。自立できない状態から、自立できるようになるための支援、つまり自立支援とは支援が必要でなくなることを目標にしている。しかし、その目標はいずれ変更を迫られる。回復が困難になる時こそ、継続的な終わりのない支援が必要になるからだ。
上りと下り、2つの支援
医療機関における、病気の診断、治療も自立支援である。リハビリテーションも重要な自立支援である。この流れでの介護・ケアによる支援は、自立して生活できることを目標にする。これは重要な介護・ケアによる支援である。これを回復を目指すということで「上り坂の支援」と呼ぼう。
回復のための支援が受けられることは重要だ。しかし、回復できない時こそ、継続的な支援が必要だということも同様に重要だ。回復が困難な状況で「できることはもうありません」というのは「上り坂の支援」しか考えていないからだろう。しかし、回復が困難であっても支援は可能である。回復不能どころが、徐々に悪化する中でも支援は可能である。むしろそこでこそ支援が必要だ。老いるという点では下るしかない死まで続く支援、この回復を目指さない支援を「下り坂の支援」と呼ぼう。
この「下り坂の支援」「上り坂の支援」の視点で見た時に、介護・ケア現場の支援の現状はどうか。徐々に老化が進んでいくのを感じることができないくらい安定していれば、下りを意識しなくても結果的に「下り坂の支援」が実現している。食事の介助をし、着替えを手伝い、トイレに誘導し、入浴を手伝う。
問題は下りが明らかになった時である。介助してもご飯が食べられない。トイレまで介助があっても歩くことができない。さらには、息苦しい、痛い、熱が出たというような変化が起きた場合もそうだ。あるいは、安定した日々も最後まで続くわけではなく、死が間近に迫れば、下りは明らかになる。こうした状況でも、上りの支援を受けることで回復が見込める場合もある。しかしその見極めは難しく、個別の状況での正解はない。
医療の面でいえば、どこまでも医療を受ける権利は保証されるべきだ。筆者が担当する特養でも、病院へ搬送する場合もあるし、施設でできる限りの医療を提供することもある。介護・ケアの面でも同様だ。どこまでも介護・ケアを受ける権利が保障されなくてはならない。
しかし、介護・ケアの権利が話題にされることは少ない。入院すると介助なしで口からの食事が困難だと点滴になる。着替えも昼間と夜で替えることも難しい。トイレもおむつということになりかねない。入浴もできなくなる。回復以前に、とても苦しい毎日を過ごすことになる。
施設で看る場合に十分な医療が受けられないことを問題にすることは多いが、病院に入院して十分な介護・ケアが受けられないことを問題にすることは少ない。回復を目指す「上り坂の支援」が優先されるのは、介護・ケアの現場でも似たようなところがある。
実際の介護・ケアの現場でも、急な悪化に対して、「入院しないと無理だ」と介護側から言うこともしばしばだ。しかし、入院すると十分な介護・ケアを受けられないことについて、介護側からですらあまり発せられないのではないか。
下り坂の支援の重要性
上り坂の支援によって、下り坂の支援が犠牲になる。そのことについて、介護・ケアの担当者が改めて自覚する必要があると思う。下ることが必然であれば、医療の提供とは別に、どんな状況になろうとも、たとえ改善の見込みがなくても、支援を続けるということを伝えていくことが重要ではないだろうか。少なくとも医療を受けることによる苦痛は少なくなるし、介護・ケアの継続によって快適さを提供できることも多い。改善が見込めないなかで提供される「下り坂の支援」としての介護・ケアについて、この先も考え続けていきたい。
