死をことほぐ社会へ向けて 第9回
2025/05/30
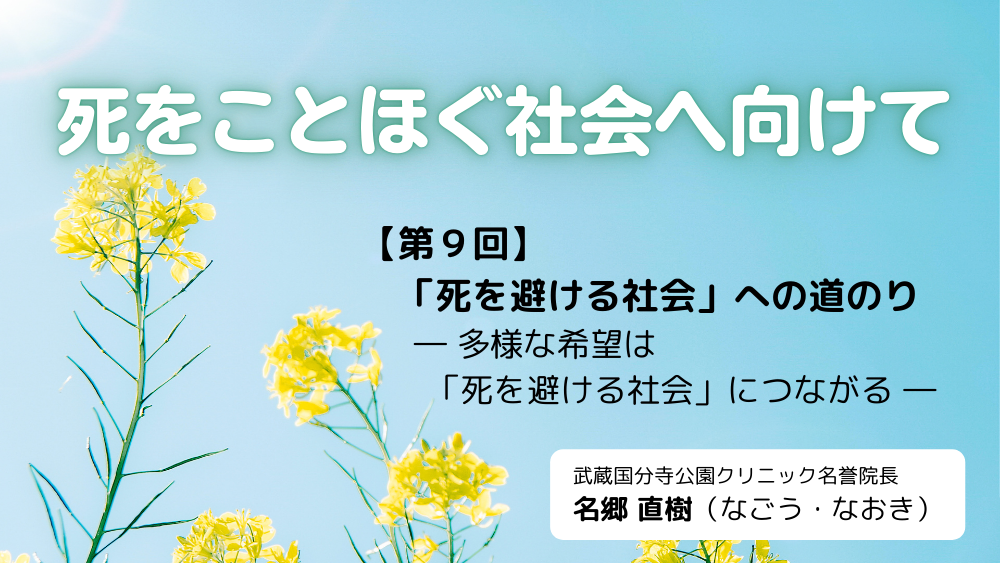
「死を避ける社会」への道のり ……多様な希望は「死を避ける社会」につながる
誰にもいずれ「死」は訪れる。多死社会を迎えた現在の日本において、いずれくる「死」をどのように考え、どのように受け止め、そして迎えるか。医療、介護・ケアの問題とあわせて、みなさんも一緒に考えてみませんか。
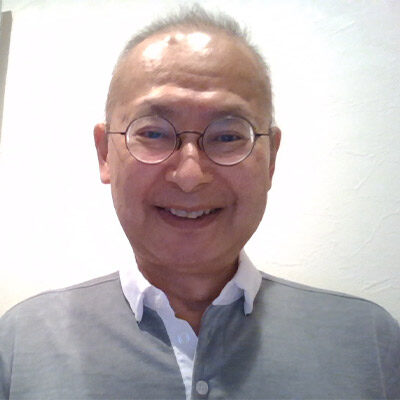
名郷 直樹(なごう なおき)
武蔵国分寺公園クリニック名誉院長
1961年、名古屋市生まれ。自治医科大学卒業。へき地医療に従事した後、2011年に西国分寺で「武蔵国分寺公園クリニック」を開業。2021年に院長を退き、現在は特別養護老人ホームの配置医として週休5日の生活。
著書に『いずれくる死にそなえない』(生活の医療社)、『これからの「お看取り」を考える本』(丸善出版)など。
人生の困難さに対処する方法を、YouTube(名郷直樹の診察室では言いにくいこと)で発信中。
YouTube
X
死を避ける社会と死を避けない社会、健康をコントロールしようとする医療とコントロールを目指さない介護・ケア、健康第一の社会と生活第一の社会、まずこうした対立を明確にすることで、「死をことほぐ社会へ向けて」話を進めてきたが、今回は「死を避ける社会」に至るプロセスについて考えてみる。
「死を避ける」という希望
いつかは死ぬという現実が動かしがたいことであっても、「できるだけ健康で元気に活動できる生活を長く続けたい」という希望を持つこと自体は自然なことだ。ただその考えは、その先の「健康であればできるだけ長生きしたい」、「死を遠ざけたい」、「死を避けたい」という希望に容易につながる。
それに対し、「元気に活動ができるうちは死にたくない」という希望もある。その先は、「元気に活動できなくなれば死んでもいいよね」という「死を避けない」方向がある。しかし、その方向だけではなく、「元気に活動できるうちは死にたくはない」が「元気に活動できる時間を引き延ばして、長生きしたい」と変化することもあり、そうなると先の「できるだけ健康で元気に活動できる生活を長く続けたい」という希望につながってしまう。医療の進歩が、元気に活動できる時間を引き延ばす期待を増大させ、その変化を後押しする。「元気に活動できなくなれば死んでもいいよね」という方向には進みがたい。いずれにしても、死を避ける希望に多くの人が吸い寄せられていく。
あるいは「元気に活動ができようができまいが、とにかく生きていることが大事だ」ということもある。これは健康とか生活とかを飛び越えて、生死がすべてという考え方だ。ただこの考えも、行く先はできるだけ「死を避けたい」ことにつながる。
また「元気に活動できなければ死んだ方がまし」というのはどうか。「元気に活動できなくなれば死んでもいいよね」に似ているし、「元気に活動できる生活を長く続けたい」という希望が叶わないとなったその先にありがちだ。「死を避ける」希望は、容易に「死にたい」に反転する。これは「死を避けない」ということとは微妙に異なる。「死を避けない」には、あえて死に向かおうという感じは希薄だ。「死を避けない」の背景は「死ぬまでは生きたい」であって、「死にたい」ではない。また「死にたい」という反転だけでなく、「元気に活動できなくても生きられる」という方向に変化することもある。とりあえず「生きていられる」というところだ。しかし、これもまたとにかく生きていられればいい、「死を避ける」という方向に逆戻りしたりする。
両極に振り切れる希望
ここまでを少しまとめてみる。医療が進歩し、これからの進歩も期待できる世の中で、多くの希望は「元気に活動し続けて死を避ける」方向へ向かいやすい。その中で「死を避けない」希望もあるが、そこにとどまることは難しく、「避けない」を飛び越して「死を希望する」となりがちだ。「死を避ける」から「死を希望する」の両極端の希望だけしかない世の中になる。
かつては「死が避けられない社会」が長く続いた。妊婦や赤ちゃんが亡くなることも多く、こどもが亡くなることもまれではなかった。さらに災害、事故、病気、いずれも現在よりも避けがたいものであった。妊婦や赤ちゃんが亡くなることは悲しい。それはできるだけ避けたい。その悲しみが医療を進歩させ、妊婦や赤ちゃんが亡くなることは激減した。そうした社会が、妊婦、赤ちゃんに限らず「死を避ける」方に向かうのは当然のことだ。そしていまだその途上にある。まだ避けられる死がある。避けるための努力が今も続けられている。もちろんそれは重要なことだ。しかし、「死を避ける社会」の実現には終わりがない。それはどれだけ医療が進歩しても、安全な社会が実現されても、「避けられない死」があるからだ。
「死を避ける社会」での「避けられない死」に対する対応は、できる限り死を遠ざける努力をしたうえでの死でないと「避けられない死」とはいえない状況を生み出した。どこまでも医療に依存する社会である。その医療への依存の一部が、今度は医療による「希望する死」、安楽死へと向かう。健康をコントロールし、生死をコントロールする、放っておけない社会だ。「死を避ける」と「死を希望する」の両極端しかない世の中とは、なんでもコントロールしようとする現在のことである。ここから、「死を避けない社会」、さらには「死をことほぐ社会」へとどう向かっていけばいいのか、もう少し考え続けたい。
