Q&Aでわかる!介護施設の看護実務 【Q7】
2025/05/09
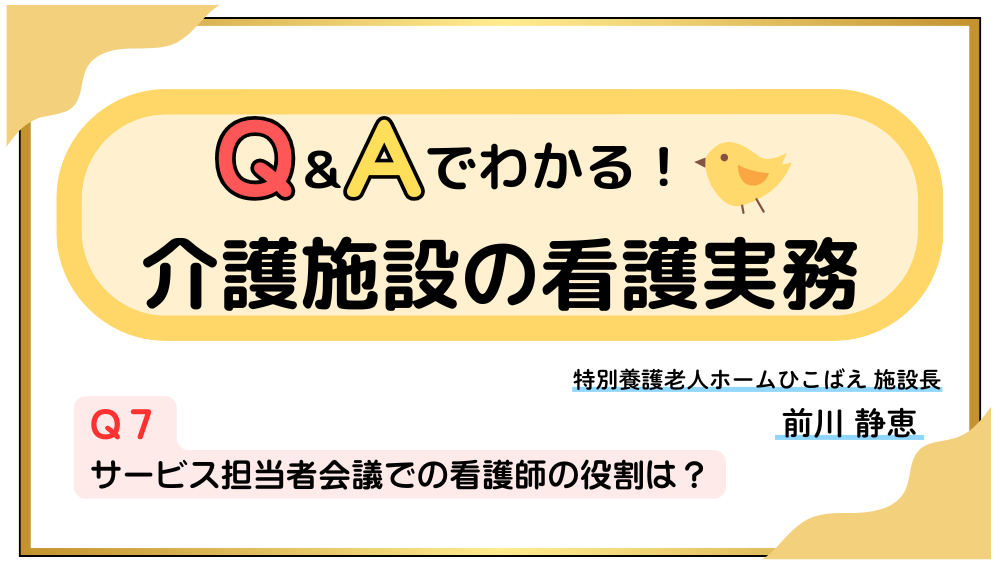
「看護師」の職場といえば、真っ先に病院が思い浮かぶと思います。しかし、実際の職場は多機にわたり、介護施設もその一つです。本連載では、介護施設に勤務する看護師の業務内容や考え方、介護職などの他職種との連携について、特に重要な項目をピックアップしてQ&Aの形で紹介していきます。
【著 者】
前川 静恵(まえかわ・しずえ)
社団法人是真会病院病棟師長、慈恵病院看護部長、長崎市医師会保健福祉センター、老人保健施設ハーモニーガーデン副施設長、有限会社Gracias かいごの花みずき施設長、株式会社パールの風代表取締役、社会福祉法人鳳彰會副理事長などを経て、現在社会福祉法人鳳彰會理事、特別養護老人ホームひこばえ施設長、ケアハウスひこばえの苑施設長。看護師、介護支援専門員。
主な著書に、『訪問介護事業所サービス提供責任者仕事ハンドブック』中央法規出版、2006、改訂版2009、三訂版2013、『デイサービス業務実践ハンドブック』中央法規出版、2014、改訂版2015、など。
Q7 サービス担当者会議での看護師の役割は?
[Answer]
サービス担当者会議でケアマネジャーと情報交換する際には、医療面からのケアの評価や提案がポイントとなります。
[解 説]
サービス担当者会議は、施設サービス計画書のサービス提供の内容の確認や、新たな課題など評価の目的で、看護師、介護職員、生活相談員、栄養士、機能訓練担当者、医師、家族などの関係者全員がそれぞれの立場からの意見を交換し、適切なサービスの提供がなされるために行われるものです。
そこでは、医療面からの評価、新たな課題の提言が、看護師の役割となります。例えば、バルーンカテーテル留置者の場合、尿路感染が起きやすいということから、「水分量はどうなのか」「排泄時の清潔保持はできるのか」「尿漏れ等の観察」「尿の性状の変化、尿量の確認」などの評価をします。また「褥瘡が完治したので処置は中止し、その後のケアについて検討する」「片麻痺のため、腕を三角布で固定しているが、三角布が緩んで良肢位に保たれていないときがあるので、気づいたらきちんと結びなおしてほしい」などと課題の提言をします。
状況の変化に伴って看護師の視点から、あらためて医療面での注意事項や気づきを情報提供し、情報の共有を図ります。それらをサービス提供内容に反映してもらうことで、利用者にとってよりよい施設サービス計画書の作成につなげることができます。
※本連載は、前川静恵先生の著書『Q&Aでわかる!介護施設の看護実務―特養の実地指導・連携・ケア』(中央法規出版、2022年10月発行)をもとに作成しています。施設看護師の業務をさらに深く知りたい方は、本書をぜひご覧ください。
