Q&Aでわかる!介護施設の看護実務 【Q2】
2025/04/25
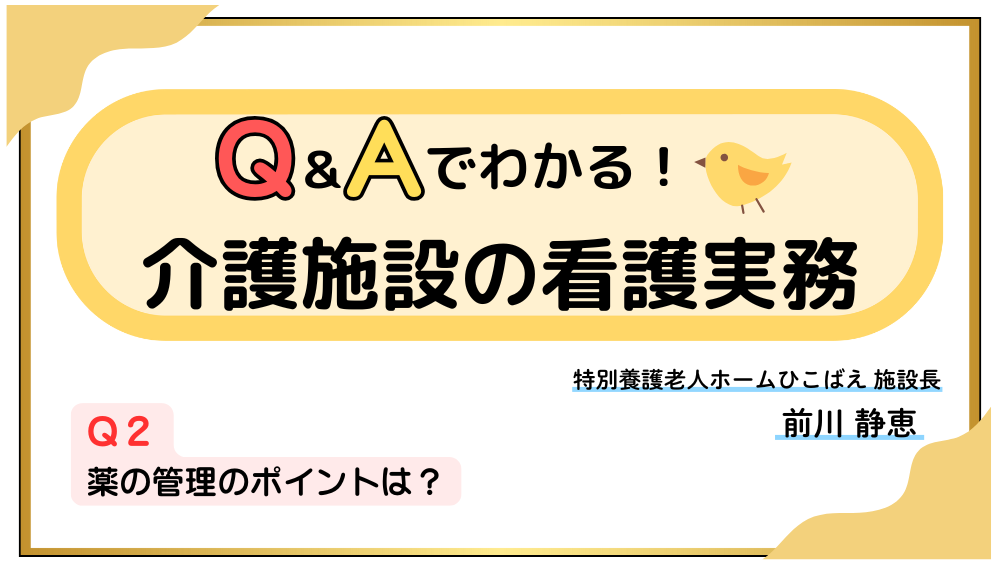
「看護師」の職場といえば、真っ先に病院が思い浮かぶと思います。しかし、実際の職場は多機にわたり、介護施設もその一つです。本連載では、介護施設に勤務する看護師の業務内容や考え方、介護職などの他職種との連携について、特に重要な項目をピックアップしてQ&Aの形で紹介していきます。
【著 者】
前川 静恵(まえかわ・しずえ)
社団法人是真会病院病棟師長、慈恵病院看護部長、長崎市医師会保健福祉センター、老人保健施設ハーモニーガーデン副施設長、有限会社Gracias かいごの花みずき施設長、株式会社パールの風代表取締役、社会福祉法人鳳彰會副理事長などを経て、現在社会福祉法人鳳彰會理事、特別養護老人ホームひこばえ施設長、ケアハウスひこばえの苑施設長。看護師、介護支援専門員。
主な著書に、『訪問介護事業所サービス提供責任者仕事ハンドブック』中央法規出版、2006、改訂版2009、三訂版2013、『デイサービス業務実践ハンドブック』中央法規出版、2014、改訂版2015、など。
Q2 薬の管理のポイントは?
[Answer]
確実に確認を行うことです。特に以下に注意しましょう。
・複数の目での確認
・セット時のミスの防止
・配薬、服薬時の確認
・誤薬の怖さの認識
・薬の収納場所は、鍵付きで、利用者の手が届かない所で保管
[解 説]
原則として薬の管理は看護師が行いますが、一包化されたものであれば介護職員による服薬援助も可能です。近年、薬局による与薬車の無料貸し出しや薬剤師による個別セットなどのサービスが増えており、多忙な看護師の負担軽減に繋がります。しかし、任せきりにせず看護師による再確認が必要です。確認者がサインする「確認チェック表」を作成すると良いでしょう。「配薬・服薬チェック表」を作成することで、誰が行ったかの重複確認となり、また、分包された薬の「氏名」、「日付」、「時間帯」を確認して与薬することで、薬に対する責任意識を持つことに繋がります。忙しいからといって安易な配薬は誤薬に繋がる可能性があります。
介護職員も薬の作用や用法についてある程度の理解が必要であり、看護師は申し送りなどで薬の情報伝達を行うことが重要です。介護職員が服薬の重要性を認識することで事故防止に繋がります。例えば、利尿剤では服用時間や排尿状態の観察、血栓予防薬では納豆などの禁止食品などの情報をわかりやすい言葉で具体的に伝えることで、介護職員の薬への理解が深まります。また、誤薬のリスクに対する意識を高め、薬の管理は看護師だけでなく介護職員も同時に行っているという認識を持つことが事故防止に繋がります。薬は必ず施錠できる場所に保管し、利用者の手が届く場所に放置しないことも重要です。
※本連載は、前川静恵先生の著書『Q&Aでわかる!介護施設の看護実務―特養の実地指導・連携・ケア』(中央法規出版、2022年10月発行)をもとに作成しています。施設看護師の業務をさらに深く知りたい方は、本書をぜひご覧ください。
