Q&Aでわかる!介護施設の看護実務 【Q1】
2025/04/25
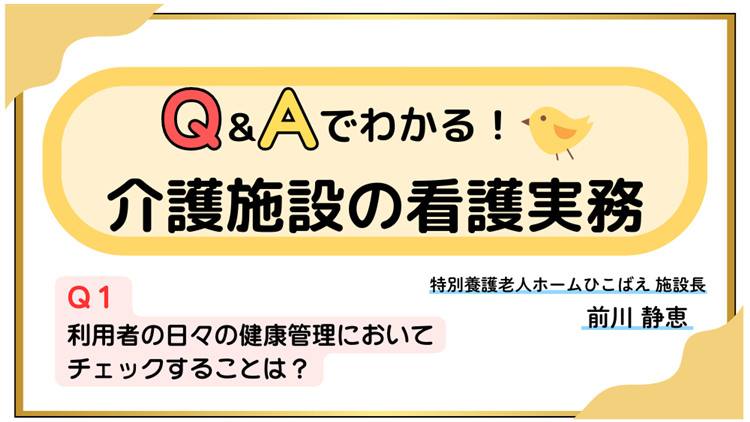
「看護師」の職場といえば、真っ先に病院が思い浮かぶと思います。しかし、実際の職場は多機にわたり、介護施設もその一つです。本連載では、介護施設に勤務する看護師の業務内容や考え方、介護職などの他職種との連携について、特に重要な項目をピックアップしてQ&Aの形で紹介していきます。
【著 者】
前川 静恵(まえかわ・しずえ)
社団法人是真会病院病棟師長、慈恵病院看護部長、長崎市医師会保健福祉センター、老人保健施設ハーモニーガーデン副施設長、有限会社Gracias かいごの花みずき施設長、株式会社パールの風代表取締役、社会福祉法人鳳彰會副理事長などを経て、現在社会福祉法人鳳彰會理事、特別養護老人ホームひこばえ施設長、ケアハウスひこばえの苑施設長。看護師、介護支援専門員。
主な著書に、『訪問介護事業所サービス提供責任者仕事ハンドブック』中央法規出版、2006、改訂版2009、三訂版2013、『デイサービス業務実践ハンドブック』中央法規出版、2014、改訂版2015、など。
Q1 利用者の日々の健康管理においてチェックすることは?
[Answer]
利用者の健康管理は、施設看護師の重要な役割です。施設での健康管理は、病院のように治療を重視するのではなく、心身ともに楽しく生活ができるように支援することにあります。利用者個々の疾患を把握し、毎日のバイタル値を参考に起こりえる健康上のリスクを予測し、いち早く対応することによって、毎日を施設で安全、安楽に過ごせるよう、健康管理はとても重要です。
[解 説]
単にバイタルチェックをするだけでなく、介護職員は疾患の基礎知識を持ち、個々の環境や症状の違いを踏まえてバイタル値を捉える判断が必要です。看護師の視点から介護職員へ助言することで、日々の健康管理に繋げられます。日常生活を安全・円滑に送るためには、食事量、飲水量、排泄状況、動作などのわずかな変化も見逃さず、訴えが難しい利用者の精神的な悩みや苦痛、希望などを的確に把握することが求められます。
高齢者にとって水分確保は重要であり、1200~1500mL/日を目安に摂取します。嚥下困難な方にはトロミ剤、拒否がある方には甘味を加えるなどの工夫で水分摂取を促します。脱水症状の兆候として、爪を押して離したときの色の戻りが遅い、手の甲の皮膚をつまんで離したときに元に戻りにくいなどが挙げられます。
室温は28度以下、湿度は50~60%を目安に管理し、高齢者の体温調整にも注意が必要です。厚着や発汗、冷えなどの観察を行い、顔が赤く汗をかいている場合は体温が高すぎるサインです。日頃から個々の状態を把握し、「いつもとの違い」を早期に察知することが重要です。訴えを明確にできない利用者も多いため、安心して毎日を過ごせるよう指示をすることが健康管理の役割です。バイタル値、食事量、ケア内容などを一目で把握できるフローシートの活用も有効です。その他、施設では排泄や飲水量のチェック表なども利用者の健康管理に役立ちます。
※本連載は、前川静恵先生の著書『Q&Aでわかる!介護施設の看護実務―特養の実地指導・連携・ケア』(中央法規出版、2022年10月発行)をもとに作成しています。施設看護師の業務をさらに深く知りたい方は、本書をぜひご覧ください。
👉 Q2はこちら
