道なき道をゆく! オルタナコンサルがめざす 強度行動障害の標準的支援 第16回 標準的支援の実装は難しい③――構造の問題としてとらえ直す
2025/10/02
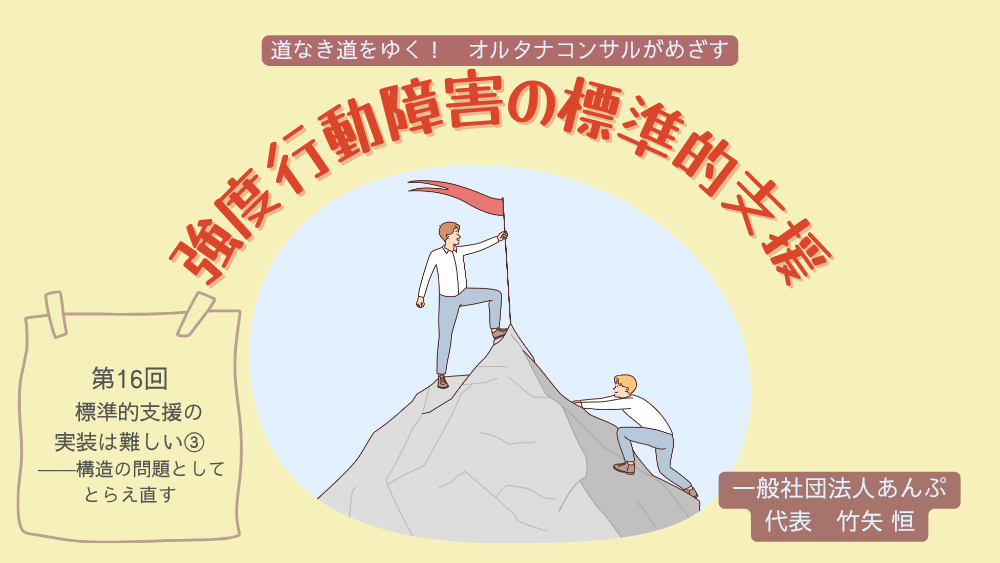
この記事を監修した人

竹矢 恒(たけや・わたる)
一般社団法人あんぷ 代表 社会福祉法人で長年、障害のある方(主に自閉スペクトラム症)の支援に従事。厚生労働省「強度行動障害支援者養成研修」のプログラム作成にも携わる。2024年3月に一般社団法人あんぷを設立し、支援に困っている事業所へのコンサルテーションや、強度行動障害・虐待防止などの研修を主な活動領域とする。強度行動障害のある人々を取り巻く業界に、新たな価値や仕事を創出するべく、新しい道を切り拓いている。
前回の連載では、現場アセスメントの重要性を「支援→チーム→組織」の三層の順序性という視点から問題提起しました。これは、支援する皆さんが日常の仕事で直面しやすい課題の順です。しかし実際には、その逆の「組織→チーム→支援」という順序で見ると、なぜ支援が安定しないのかの構造が理解しやすいと思っています。
組織の基盤がなければチームはまとまらず、そのチームが機能しなければ知識や技術は根づかない。今回はこの三層の課題を、「現場アセスメント」という視点から立体的に見つめ直してみたいと思います。
組織マネジメントの課題――改善が進まない事業所の構造
私がかかわってきた事業所の多くは、運営体制を整え、職員が安心して働ける工夫をしています。ほとんどの事業所は健全に取り組んでいますが、一方で改善が進みにくい事業所も残念ながら存在しています。そこには共通する特徴が見られ、それが結果として問題を生じやすくさせていると考えています。
例えば、施設長やリーダー層が経験主義にとどまり、新しい挑戦に消極的な場合。過去のやり方を重視しすぎると、現場の工夫や外部からの知見を受け入れにくくなり、改善は停滞します。
また、会議が意見交換や合意形成の場として機能せず、上からの説明だけで終わることもあります。職員の声が反映されず、会議が「伝達の場」に留まれば現場の主体性は弱まり、改善のサイクルも機能しません。
さらに、決定のプロセスが不透明で「どこで誰が決めたのか」が見えないまま方針が下りることもあります。その結果、「どこで決まったのかわからない」「意見を出しても無視される」「若手が発言できない」といった声が広がり、不信感から退職につながることもあります。
もちろん、ここに挙げたものは一例に過ぎません。組織マネジメントが不全な事業所では、様々な課題が重なることで、現場の困難感を強めていきます。
一方で、ボトムアップで提案を出せる会議体制をもつ事業所は、雰囲気が大きく異なります。決定が尊重され、実践を検証するサイクルが回ることで、職員が安心して意見を出せる環境が育ちます。こうした文化があれば人材は定着しやすく、やりがいや自律性も高まります。私自身、そのような「見える化」が整った現場でチームワークが向上する姿を何度も見てきました。
現場の困難を振り返ると、課題は必ずしも職員の知識不足だけではなく、組織としての仕組みや文化の未成熟が影響しているのだと感じます。これはまさに、三層の課題のうちの「組織マネジメントの課題」です。
支援マネジメントの課題――属人化を超えられないチーム
現場では、支援の方法や知識が「個人名に紐づいたまま」になっている事業所が見られます。誰か一人の工夫や経験がチーム全体に共有されず、その人がいなければ成立しない支援。これが属人化の典型です。
属人化を招く要因は多様です。支援手順書が整備されず、ベテランの「口伝(くでん)」に頼ると、経験の少ない職員は、それを真似するしかありません。アセスメントの書式が統一されていなければ、支援の評価が職員ごとに異なってしまいます。記録フォーマットがバラバラなら利用者の状況も共有されません。会議や申し送りでの情報伝達が不十分なら、せっかくの工夫も広がらず「できる人だけの支援」で終わってしまいます。
属人化が進むと支援は一貫性を欠き、利用者にとっては日によって支援者の対応が変わる不安定なものになります。職員側も「やり方が違っても問題ない」という雰囲気が広がり、チームとしてのまとまりを失います。つまり属人化の蓄積はチームマネジメントの不足につながり、現場の組織的な動きを阻害します。その結果、ノウハウが蓄積されず、現場の進化は止まってしまいます。
重要なのは、組織マネジメントは整っていても属人化が起こり得る点です。規程や体制があっても、支援をチームで共有して実践に落とし込む仕組みが弱ければ、支援は依然として“できる人”任せから抜け出せないままです。
本来、支援の知識や技術は個人のものではなく、チームの財産として共有されるべきです。しかし仕組みがなければ属人化は避けられません。これはまさに三層の課題のうちの「支援マネジメントの課題」だと考えています。
支援・技術の課題――標準的支援を実装するために
利用者の特性を理解し、適切な支援技術を活用することは現場の基本です。そして、それが定着し効果を発揮するためには、支援マネジメントの仕組みが大きな役割を果たします。
支援マネジメントが機能しているチームでは、学んだ技術や知識が支援手順書や記録に落とし込まれ、情報共有を通じてチームの共通財産になります。誰が支援してもズレが少なく、利用者にとって一貫した安心感が生まれます。また、それにより支援の効果が安定し高まっていきます。
逆に支援マネジメントの機能が弱いと、せっかくの知識や技術も「人によってやり方が違う」ままで終わり、標準的支援の実装は形骸化したものになってしまいます。
つまり、支援・技術の課題とは、個人の専門性の不足よりも、それをいかにチームに広げ、日々の実践に根づかせるかにあります。支援マネジメントが整った現場ほど、標準的支援の実装が可能になり、支援の効果も大きくなるのです。これも三層の課題の一部です。
三層の順序性――「なぜ続かないのか」を考える
前回の連載でもふれましたが、これら三層の課題は単なる並列ではなく、明確な順序をもっています。
まず組織マネジメントがなければチームマネジメントは成立しません。方針や規程、業務の枠組みが整っていなければ、会議や合意形成はその場しのぎになり、支援は場当たり的になります。
そしてチームマネジメントが機能しなければ知識や技術は定着しません。支援の方法が仕組みとして共有されないため、せっかくの工夫も「その人だけの支援」に終わります。
現場でよく聞く「研修を受けても成果が出ない」という声は、この順序の逆転を端的に示しているのかもしれません。表層の「知識不足」だけを補っても、背後にあるチームや組織の課題が放置されれば、改善は続かないものだと思います。
個人の努力に還元しない視点が大切
現場で起こる困難は、多くの場合「知識や経験の不足」として、つい個人の力量に結びつけて語られてしまいます。しかし実際には、その背後にあるチームや組織の課題が見過ごされていることが多いと感じています。
三層の課題を意識して現場をアセスメントすれば、「なぜ続かないのか」「なぜ属人化するのか」が整理しやすくなります。コンサルタントの大切な仕事の一つは、この三層を丁寧に見立て、どこにボトルネックがあるのかを一緒に探ることだと思っています。
そして私が現場をサポートするときに常に意識しているのは、課題を「個人の努力不足」ではなく、「構造の問題」としてとらえ直すことです。個人の頑張りに依存するのではなく、組織やチームの仕組みを整えることで持続可能な支援体制を築く。せっかく手に入れた知識や技術を最大化できるのも、このマネジメントの力です。ここにこそ、私が現場と向き合ううえで最も大切にしている「三層の課題」へのアプローチの軸があるのです。
次回は、いよいよ私の主戦場である「コンサルテーション」について、まとめていきたいと思います。
